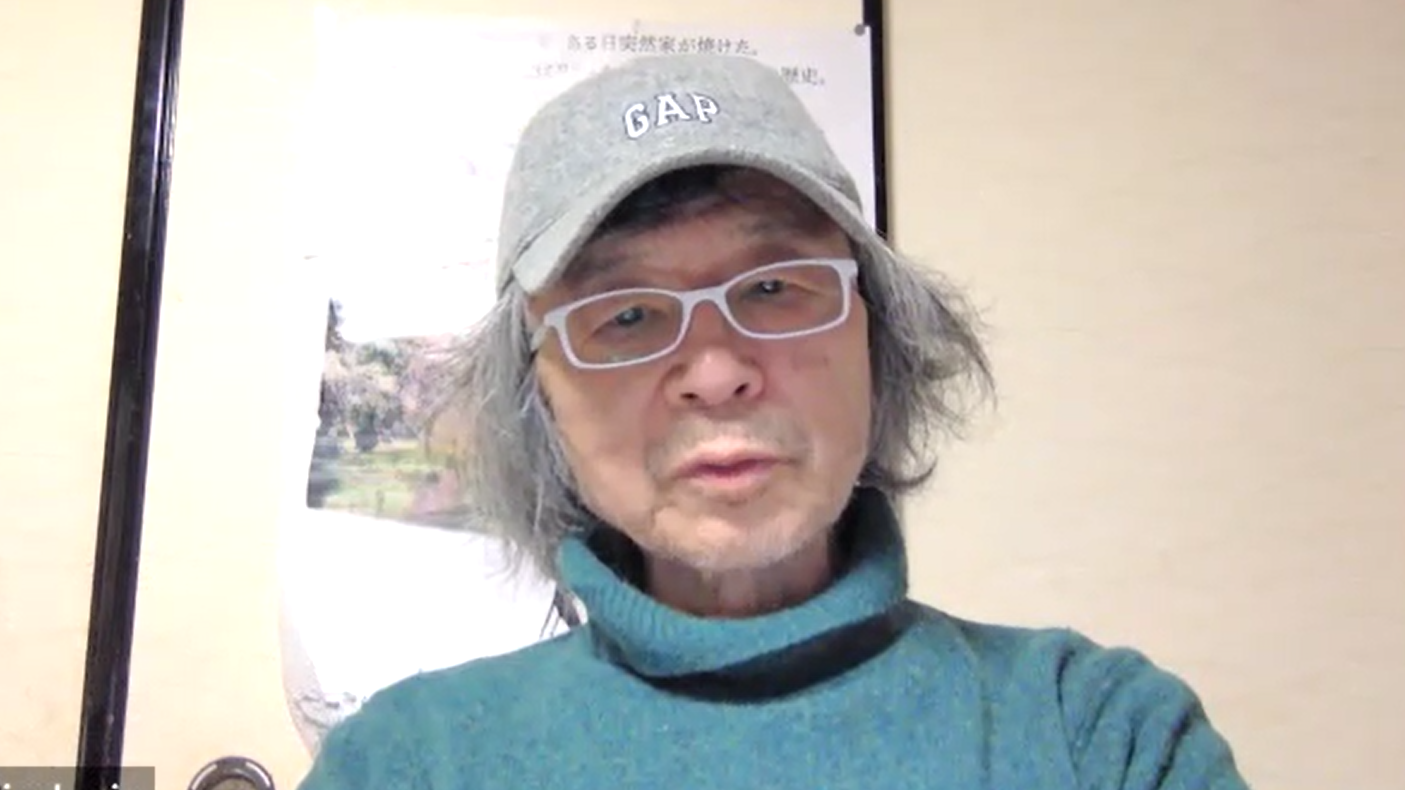
原將人監督
2018年夏、不慮の火事で自宅が全焼し、50年にわたる映画人生をかけたオリジナルフィルム、脚本、創作メモ、映画機材を失った原將人監督。
しかし原監督は、火事の痛手を創作への力に変え、新作『焼け跡クロニクル』で映画の舞台へと戻ってきた。『焼け跡クロニクル』の公開、また原將人の代表作を集めた「伝説的映画監督、原將人特集上映」に際し、原將人監督、原まおり監督、そして原監督を8年間にわたり追ったドキュメンタリー映画『映画になった男』の監督であり、批評家・neoneo編集委員である金子遊氏の鼎談が行われた。

金子遊氏
金子:今日は原將人の作品群について、クロニクル的にお話を伺っていきたいと思います。まずは『初国知所之天皇(はつくにしらすめらみこと)』について。この作品は原さんが高校卒業後、10 代で大島渚監督『東京战争戦後秘話』の脚本・予告編の演出を手掛けるなどした後、16ミリでの映画制作にとりかかったものですね。ジェイムス・ジョイスの「ユリシーズ」のように、古事記に残る最初の天皇「はつくにしらすめらみこと」の起源をめぐる映画を制作しようとしたものの、途中で頓挫して、撮影で行くはずだった北海道から鹿児島までをひとりでヒッチハイクしながら撮ったロードムービーとして結実する。
『初国』は通常の上映形態のほかに、生演奏つきの映画上映、20 代前半の若き日の自分が映っているフィルムに、現在の原さんがライブでナレーションを読み上げ、歌を歌うというライブ上映のスタイルがありますよね。その、生身の自分の声はどんどん歳をとっていくのに、スクリーンの中の自分は若いまま変わっていないというのは、どんな気持ちなのですか。
原:今回上映される『初国知所之天皇2022デジタルリマスター版』は、2021年のイベント「初国完成47周年記念劇生ライブ上映」を入れ込んで編集したものなんです。22歳の原將人が映っている脇で、71歳の原將人がしゃべっている。その「年の差」がまた良かったんです。スクリーンのなかの原將人と、ナレーションを語る原將人との落差。時間の体積が見えるという良さですよね。50年経つとこんなに老いてしまうものか、時の非情さというものが感じられて。自分でも客観的に観て面白かったです。今回のバージョンには2008年、『マテリアル&メモリーズ』の時に作った短歌も組み込んでいます。
金子:最初に8ミリフィルムで撮ったものが、16ミリにブローアップされて、次に35ミリのプリントになって、今度はデジタルにという流れを見ていると、何度でも形を変えて甦る、メディアが変わっても残り続ける『初国知所之天皇』という映画の息の長さ、年を経て変わっていく生身の原さんとの対比も含め、50年以上も上映を続けていくというのは非常に不思議な感覚なんじゃないかな、と思います。
『映画になった男』の中で原さんが「『初国』がスローモーションを発見した時に映画として成立した」と仰っていて、原さんはこの「映画として成立した瞬間がある」という言い方をよくされるのですが、映画として成立した瞬間というのは、何の手応えをもってそう感じているのでしょうか。
原:観客としての僕が面白いと思った瞬間です。僕のように映画を観る事が好きで、そこから映画に入った作家というのは、映画会社に就職して仕事として映画を覚えていった作家とは少し違うと思うんですよね。まず、観客である自分に向けて、自分で映画を作るという事だと思うんです。作る事が表現行為じゃなくて、観たい映画を観る事が、それに先行する表現行為だ、みたいな所があって。それで僕が最初に出した映画の評論集は「見たい映画のことだけを」っていうタイトルなんですけどね。映画が成立した、と思う瞬間は、観客としての原將人が「ああ、これはいい!」と思った瞬間ですね。
『20世紀ノスタルジア』は脚本よりサントラが先に出来ていた?

『20世紀ノスタルジア』
金子:僕の撮ったドキュメンタリー映画『映画になった男』の中で、『20世紀ノスタルジア』プロデューサーの西村隆さんが当時のエピソードを語っているのですが、企画段階で原さんがシナリオより先にサントラを完成させていたと(笑)。曲と歌詞が出来て、そこから映画が始まったというような事を仰っていましたが、本当のところはどうなのですか。
原:本当のところは、最初に曲は全部出来ていました。脚本の最初の段階では、男の子はオーストラリアに行ってしまうのではなく、死んでしまって、残された女の子が彼と2人で撮った映像を見ながら旅をする話だったんです。だけど、男の子を殺さない方がいいっていう意見が多くて、それなら男の子を死なせないで成立させようと脚本を書き直したんですよ。
金子:転校生の風変りな男の子と放送部の女の子が恋をして、宮沢賢治の「双子の星」に出てくるチュンセとポウセという名でお互いを呼び合うんですね。そこから印象的なラストシーンにつながっていく。宮沢賢治の原作がベースにあって、そこに高校生たちの恋愛物語を載せていくのかなと思いきや、原さんの場合はちょっと違う。どういう風にシナリオを作っていったのですか?
原:宮沢賢治の「双子の星」は名前を借りただけ。映画の最後で双子が生まれる、映画内映画の結末のために「双子の星」の名前を借りただけで、中身は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』なんですね、よく考えてみると。最後に出てくる「20世紀にありがとう」というセリフは、『百代の過客』のラストと同じ。「ノスタルジー。映画賜いし20世紀に感謝」という歌から持って来ているんです。『百代の過客』も、僕と息子の2人で映画を撮っていて、最後は、俳句。『20世紀ノスタルジア』は『おかしさに彩られた悲しみのバラード』と『百代の過客』をつぎはぎしながら自己模倣している感じかな。
『あなたにゐてほしい〜Soar〜』製作中の原將人との出会い
金子:『20世紀ノスタルジア』の前に、山形国際ドキュメンタリー映画祭で評価された『百代の過客』があって、『20世紀』の後に、3面マルチスクリーンで上映する実験映画『MI・TA・RI!』がきて、そこから再び劇映画に戻って『あなたにゐてほしい 〜Soar〜』が出来て、という流れになるのでしょうか。僕が原さんに初めてお会いしたのは2009年の秋で、『あなたにゐてほしい』の製作で2000万円の借金を背負って苦境に立たされ、さらに63歳にして双子の娘が生まれて、という時期の少し前になりますね。『映画になった男』でも『あなたにゐてほしい』を取り上げていますが、あの作品はどんな風に始まったのでしょうか。
原:まおりのおじいさんが、九州の大分県日田市の山奥の村で電気屋をやっていたんですが、そのおじいさんが「日本にテレビが普及し始めたころ、村でテレビが映らないので、山に共同アンテナを立てた」という話をしてくれたんですよね。それがすごく面白かった。1958年くらいかな、僕がまだ小さい頃、目黒の家の窓から東京タワーが見えてたんですよ。タワーが完成するとテレビ局が2つか3つ増えると聞いて、それがすごく楽しみで、毎日学校から帰ると窓から東京タワーを観ていた。その記憶も重なって、自分が育ったころの戦後をもう一度思い出してみようか、と思ったんです。テレビの普及。天皇制が象徴天皇制に変わったこと。旧かなづかいが新かなづかいに変わったこと。その3つが戦後の日本の在り方を象徴していて、それを取り上げたいと思ったのが『あなたにゐてほしい』です。
まおり:もともとは私が「仲良き事は、美しき哉」という脚本を書いて動いていたのですが、それを原が完全に無視して、ロケでシナリオをつけていました。挙句に、タイトルも変えられました。最初はちゃんとした劇映画として、役者さんも決まって動いていたのですが、ロケが4回バレて、もうぐちゃぐちゃになってしまって。
原:主役がいなくなったんです(笑)。でもすごくいい楽曲がたくさん出来ていたんですよ。それで代わりにまおりに演じてもらった。彼女が歌えばすごくいいミュージカルになると思って、今のような形になったんですけどね。
金子:確かに、『あなたにゐてほしい』は原さんの物語ではないな、と思っていました。大分の山奥でアンテナを立てるという発想は原さんらしくない。でも観ていると、どんどん原さんの映画になっていくんです。まおりさんの脚本をベースにしながら、原さんがそれを自分のものにしていったプロセスなんでしょうね。この映画でおふたりは『MI・TA・RI!』に続いてコラボレーションをしていたのですね。



















