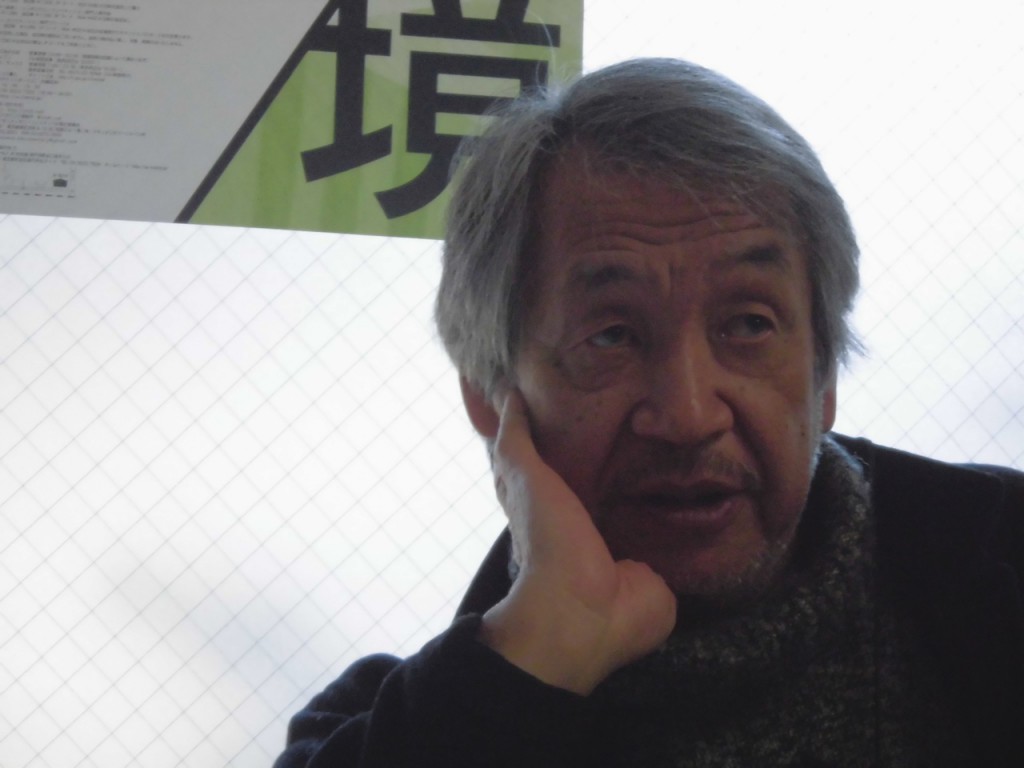2月7日から開催される『第4回 座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル』。
この映画祭のプログラム・ディレクターは山崎裕。neoneoの読者には、是枝裕和・河瀨直美らの作品のカメラマンとして、あるいは『トルソ』(2010)の監督としての側面の方が有名かもしれない。しかし、テレビの草創期から数多くのドキュメンタリー番組も手掛けてきたこのベテランカメラマンは、そのキャリアの初期に、これまた伝説のカメラマン・三木茂(1905-78)の現場に参加していた。さらにいえば、牛山純一や木村栄文とも仕事をしているというから驚いた。
今回の『座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル』では<特集 三木茂>として『上海』『柳田国男と遠野物語』が上映される。そこで、三木さんとの思い出や今回の映画祭の企画意図を語ってもらうことにした。豊富な現場経験に裏打ちされたカメラマン山崎裕のドキュメンタリーに対する深い見識に魅了され、あっという間の2時間が過ぎた。
(取材・構成 佐藤寛朗)
——そもそも山崎さんと三木茂さんとは、どのような形で出会ったのですか?
山崎 何の縁だったかはよく分からないけど、誰かの紹介で、三木映画社が作るPR映画の撮影助手を頼まれたんだ。1965年頃の話です。
いきなり話が横道にそれるけど、僕は大学を出てからずっとフリーの撮影助手をやっていて、同じ頃、若くして日展に入った天才日本画家の中村正義さんが小川益王さんと作った自主映画で、はじめてカメラマンとしてデビューしているんです。タイトルは『日本の華 浮世絵肉筆』(1967)。このあいだ『父をめぐる旅』(2013/共同監督:武重邦夫・近藤正典)という映画を見て、ようやくこの正式タイトルが分かったのだけど。
『日本の華 浮世絵肉筆』は、当初はベテランと言われる40代後半のカメラマンが撮影につく予定だったんだけど、中村正義という画家の言葉を、そのカメラマンは理解できない。正義さんが浮世絵にみている着物の袖とか、襟足とかのフォルムや、線の魅力を撮ってほしい、というんだけど、カメラマンにとっては、それは袖や首のアップでしかない。正義さんはイタリアで現代絵画に触れていたものだから、抽象概念と拮抗する意識みたいなものを探していたんだけど、映画のカメラマンは、肩口ですね、とか、袖ですね、とか、あくまで名称としてとらえるわけ。そういう正義さんの感覚が理解できる人、ということで、日大映研でアバンギャルドをかじっていた僕のところに話が回ってきた。
当時の日大映研は実験映画の全盛期で、城之内元晴の『プープー』(1960)とか、足立正生の『椀』(1961)の時代です。僕は中核メンバーではないけれど、技術スタッフとして彼らを応援していた。撮影をやりたがる人はたくさんいたから、そこには割り込んでいけないと思って、学生時代は現像ばかりをやっていました。劇映画ごっこをやるよりは、実験映画とか、わけの分からないことをやる方が面白い、と思う流れにいたものだから、それを知っていたあるカメラマンが、山崎なら、正義さんの言葉の意味がわかる。会話ができて、的確な画を作れるだろう、ということで、カメラマンに抜擢してくれたんです。画を撮るだけで、助手には先輩のプロの方がついてね。
正義さんの言っていることはものすごく新鮮だったし、撮影をしていると、本当に分かってくるんですよ。版画では出ない、一流の浮世絵師の肉筆の線の勢いを、フォンタナのキャンバスを切り裂いた作品の勢いとかに比較したり、いろいろ教わりました。彼は有名な画家と無名の画家では、筆の裁きが明らかに違う、とも言っていた。確かにアップの画で覗くと全然違うんです。
そこで映像に対する感覚を学んだ、というのかな。カメラにとってのサイズの在り方、バストとかアップショットとかフルショットというのは、人間の形が基準なんだけど、本来はそんなことは関係ないし、そもそも劇映画用語でしょ。向き合っている世界が何かという事のはずだし。
昔、宇宙から地球を撮った写真を見た時に、この地球の写真はクローズアップなのかロングショットなのか、ということに私は思いをはせました。宇宙から見たら、あれはクローズアップなんだけど、地球という地上の視線でみたら、あれはロングショットでしょう? だけど画は同じものだよね。映像における対象との関係性を、自分でどう認識して向き合うかで、地球のクローズアップなのか、大ロングなのか、という認識が変わってくる。そういうことをいろいろ学んでいる頃に、僕は三木さんに出会ったんだと思います。
――現場での三木茂さんは、実際にどのような方でしたか。
山崎 今でも僕は尊敬するカメラマンとしては、三木さんの名前を必ず入れるんだけど、それはもう、初めて出会った時から、魅力的な、劇的な感動がありました。もちろん好きなカメラマンや、うまいと思う人は沢山いるけど、誰かひとりを選べ、と言ったら三木さんだな。それはもう、最初の出会いの時からなんですよ。60年代の半ば過ぎでしたかね。
その頃、三木さんは三木映画社というプロダクションを経営なさっていました。私がついた仕事は低予算のPR映画で、オイルシール製造メーカーのPR映画の撮影助手として呼ばれたんです。低予算だから、三木さんは、1人で製作から演出、撮影までやっていました。その時、彼が使っていたカメラはボレックスH-16です。元々ゼンマイ式の16ミリ。そこに今のカメラのバッテリーぐらいの小型モーターを取りつけて、電動にしていた。それにアンジェニーの10倍ズームレンズをつけ、木だけど軽い三脚を使ってました。バッテリーも自分で持って、ズームもフォーカスも自分で決める。全部、ワンマンでできるんです。今の時代で言えば、民生のデジタルビデオカメラとか、あれを回す感覚だよね。それを1965年のあの当時にやっていた。そこに感動したんです。
その頃は、他の現場ではカメラマンに、えっ、ボレックスで撮るの?とか言われる時代だった。高級アマチュア用の安いカメラだし、アリフレックスじゃないと嫌だ?とか言われるのが普通。そういう撮影所的な権威主義が根強い時代に、巨匠の三木さんが、ボレックスを自分の身の丈に合わせてチューンナップして使っているわけ。
そんな三木さんの助手だから、現場ではやることがあまり無い(笑)。カメラは自分で持っちゃっているし、ズームも自分で合わせちゃうからさ。とにかく露出と位置関係だけをチェックしていればよくて、あまりやることがないんですよ。
オイルシールというのは、ベアリングの回転を滑らかにする為の、潤滑油を染み込ませたスポンジ状の金属部品です。プレス機でガッチャンガッチャンと作られているのだけど、機械の動き自体が面白いわけ。僕はすることが無いから、その機械の仕組みや動きをずっと見ていたんだよね。
ところが三木さんは、いつ回すか分からない。若い照明マンを連れてきて、彼も一生懸命やっていて、ライトを置いて、影が出るなぁとかいって、ライトを持ち上げて動かそうとする。するとその瞬間に「動くなァ!」と声が掛かって、カメラのスウィッチを入れてしまう。僕は慌てて露出を合わせなければならない。
カメラもライトの位置も決まって、さて回すか、という時に、パッとカメラを持って機械の反対側、いわゆるドンデンに入って、そこで回し始めるんです。照明マンがオロオロしている間に回し終わって「お前の照明はこっち側から撮るもんだよ」と言ってニヤッとする。とんでもないカメラマンだと思ったけど、凄いなと思った。
いつ回すか分からないから、いつも絞りはこのぐらいと想定していなければならなかったですよ。
その機動力と、一瞬を逃さない洞察力と、当時60歳を超えたぐらいだったのかな、老人としての自分の体力とか、経済性とかを全部計算して、道具をチューンアップし、作品のクオリティを守る。その発想が、単なる技術屋じゃないんだな。カメラマンというだけじゃなくて、プロデューサーも会社経営もやっているし、そういうことも全部含めて、道具をひじょうにうまく使っていた。もちろん溝口健二の『瀧の白糸』(1933)の話とか、無声映画時代に初めて移動車の上で手持ちをやったとか、歴史的な伝聞は僕も知っていたけど、そういうカメラマンからすれば、おもちゃみたいなカメラだけど、それを上手く使いこなして、作品のクオリティを守る。そこに感動したんですよね。
撮影が終わって、ギャラをもらいにいって、その頃はみんな現金支給ですから「飯でも食おうか」という話になって、銀座アスターで、そばとかシュウマイとかをいろいろご馳走してくれた。その時に「助手だったら、もうちょっとオレの面倒を見てくれよな」と言われちゃった(笑)。
こちらはすみません、と謝るけど、「確かにあんまりやることなかったかも」と笑いながら「でも、カメラマンになるなら、それでいい。好奇心を失わないうちにカメラを回せ」ということを言われた。その言葉は決して忘れられないですね。
助手をずっとやっていると、助手のルーティーンみたいなのができちゃうでしょう? でも三木さんは、僕が面倒を見なかった理由として、機械に好奇心を持って見ていたことを知っているわけ。自分ではジーッとカメラを回しているくせに、こいつは対象の機械に興味を覚えているのかとか、見ていたんだね。口では「何でオレのことを手伝ってくれないんだ」と言いながら、ちゃんとそこを見てくれていたんですね。
その次は、大阪の門真かなんかの工場で、象印のしっかりしたPR映画の仕事。監督は秋元憲という、亀井文夫と三木茂の有名な「ルーペ論争」(*2)の時に『文化映画研究』という雑誌で間に入って書いていた人だけど、三木さんとは親しくて、記録映画やPR映画を一緒にやっていた。カメラマンは中尾駿一郎さん(1918-1981、カメラマン。今井正監督作品を多数撮影)です。僕は劇映画のカメラマンにつくのが初めてだったから、きちんとやらないとなめられるな、と思って、セカンドの助手に自分の日芸の同級生だった仲間を呼んできて、体制を作ったわけ。
ミッチェルというアメリカ製の、劇映画では定番の35ミリカメラの16ミリ版、を使うんだけど、三木さんは、それを質屋に預けていた。質屋の倉庫というのは、預かった物の品質管理のために、温度も湿度も一定に保たれている。質屋の蔵からカメラを出してくる、というところから我々の仕事がはじまった。
つまり、合理主義者なんですよ。体裁とか世間体とかそういうことじゃなくて、物事を合理的に考えて、自由に判断する。面白いなあ、と思ってね。三木さんの事務所は狭い銀座の小さなビルの一室だったから、置き場に質屋の倉庫を使うという発想は、なかなかなものだと思いました。
そのミッチェルと、愛用のボレックスと、2台を渡されて持って行かされたんです。中尾さんはミッチェルに慣れているから、ボレックスは結局使わなかった。手持ちがあまり好きじゃなかったのかもしれないね。撮影を終え、銀座の事務所でオールラッシュを見た時に、三木さんは見終わった瞬間、「中尾くん、映画のイロハから勉強してきたまえ」と言って、16ミリのフィルムをリールからバッと外して、編集用の白バックに投げ捨てた。中尾さんは、黙って大きな身体をすくめていた。その横に僕もいました。
三木さんは「何のためにボレックスを渡したんだ」と怒った。ミッチェルだと、せいぜいタイトバストぐらいの大きさしか撮れないわけ。今の時代、こんなものはアップじゃない、何でボレックスでアップを撮らないんだ!と。この話は、中尾さんは後に映画学校で、自分の体験談として話していたみたいだけどね(笑)。
映像に対するセンス、道具に対するセンスがね、大ベテランなのに若いんですよ。今はオレの方がその頃の三木さんより歳を取っているんだけど、当時の感覚でいえば最長老ぐらいの人が、そういう感覚やセンスを持っている。そのことに感動したわけ。
そのあとも、僕は結構カメラを回させてもらったんだ。リテイクにいってこいとか、実景を撮りに行けとかいって、工場の再撮なんかをさせられた。その1年後、今度はPR映画を1本まるまるカメラマンとして任された。日大映研の仲間を演出に使ってね。
部屋の中でパンをするというカットがあって、パンの終りに鴨居の上の物が写るのが気持ち悪くて、それを修正ズームしたんですよ。パンをしながらチョロっとズームしたら、オールラッシュで三木さんにそれを指摘された。「お前は映画を分かっていない!」と、今度は僕がフィルムをバーンと投げ捨てられた(笑)。
そういうカメラワークはみっともない、オーソドックスなカメラワークとしては下品だと、そういうことでしょう。こちらも若かったから、あまり深く考えずごまかしたら、そういうごまかしはやるな、ということを指摘された。もちろんそれだけではないけれど、そこをいちばん怒られた。
三木さんとの付き合いはその作品までで、その後僕は別のところで回し始めたから、そこで終わっています。1年半とか2年ぐらいの本当に短い付き合いだったけど、三木さんの持っていた柔軟さとか、撮影や道具に対する自由さとか、合理主義とか、そういうもの全てに僕は影響を受けました。カメラマンって、だいたい保守的じゃないですか。権威主義やブランド志向みたいなものがある中で、三木さんはその時代に合わせた目的に対応する発想を持っていた人だったのね。
それと、単なるパートに凝り固まっている人じゃなくて、演出的な視線もあった人だよね。カメラマンとして自立して仕事をしながら、スタッフとして常に全体を考えている。戦前の『上海 –支那事変後方記録–』(1938)は自分だけで行っているよね? 柳田國男さんなんかとも仕事をしたし、戦後は原爆の記録もやる。いろいろなことに興味があるから、プロデューサーも演出も企画も全部できるし、他の演出家とも仕事ができる。たまたまカメラはいちばん得意だからカメラマンだった、というような、広い意味での自分のパートを越えていく意識とか、その在り方が、自由さを持っている感じがするんだよね。
――三木茂さんといえば、亀井文夫さんとの有名な「ルーペ論争」の当事者でもあります。そのことについて、三木さんから直接聞いたことはありますか。
山崎 ルーペ論争自体は有名だから、僕も当時から知っていたけど、細かいことは、あまり言っていなかったな。そういうことを亀井くんとやったよね、ぐらいの話で、「俺は撮らなかった」という以上は聞いていない。だから後年、国会図書館で論争を調べたのだけれども(*3)。
『戦ふ兵隊』(1939/監督:亀井文夫 撮影:三木茂)のエピソードで聞いたのは、従軍映画で、砲弾がドンパチ飛び交う中、弱虫な自分はおろおろしているのに、撮影助手の瀬川順一さん(1914−95、カメラマン。『雪の結晶』『留学生チュア・スイ・リン』など撮影)は、戦場の塹壕のなかでチェンジバックを出して、平気な顔をしてフィルムチェンジをしていた、これは大物になるな、と思っていたと言う話。実際に瀬川さんは大物になったよね。『ルーペ』(伊勢真一監督、1996)のなかで、晩年の瀬川順一さんが「なぜ三木さんは回さないのか、俺だったら回すのに、とその当時は思ったけど、何年かたって、あのとき回さなかった三木さんはすごいと思った」という話をしていたよね。それを観て、瀬川さん、若い時はイケイケだったんだな、と思ったけど(笑)。
「カメラマンは目隠しされた馬のようなもの」という、いわゆるカメラ馬車馬論に関しては、三木さんも、それが全て当たっていると言っているわけではないんだけど、そういう側面がある、と。カメラマンのことをとやかく言う前に、演出家たちが、ほんとうに演出家の資格とか能力とか見識を持って責任のある仕事をしているのか。ちょっとした知恵や勉強ができたとかで、偉そうなことを言っている空気に憤慨する面がある、と。よく読むと、三木さんは消極的な反論なんだよね。演出家批判というよりは。
とにかく僕は、三木さんが、亀井文夫に羽交い締めにされている中国の少年を撮れなかった、というのはとても正しい、と当時から思っていた。そんなものを回して何の意味があるんだと思っていました。
その後30歳になるかならないかの頃、NTVの牛山純一さんの仕事でインドネシア領のイリアンジャヤに撮影に行く事になりました、私の初の海外取材場番組だけど、元々、僕は市岡康子(1939- ディレクター。『多知さん一家』『クラ』など)さんのクラ交易のB班として、沿岸部の定着民の生活の撮影が担当でした。クラ交易の本体の方は転覆したりして、結局、翌年の撮影になるんだけど。
ニューギニア島のイリヤンジャヤへの撮影は、牛山さんがインドネシア政府に働きかけ、撮影許可を戦後初で貰い、イリヤンジャヤの横断の撮影班が山間部に入っていました。東ニューギニアは牛山さんは既に横断する番組を作っていて、これを成功させればニューギニア全島の横断が成立するわけです。
その撮影班の通訳は、インドネシアと原住民の混血の子なんだけれども、撮影が終わってから、私達の班についたんだよ。その時に、山間部のディレクターが拳銃を持っていた、と言うんですよ。危険な場所ということで腰に下げているんだけど、村の酋長と駆け引きをする時に、何となくちらつかせながら交渉をすると。通訳は、その話を訳すのは良い気分ではなかった、と憤慨していたわけ。
彼に、だったら俺は、そのディレクターを撮るけどなって言ったんだよ。原住民からディレクターに、カメラを振っちゃうぞ、という話をした。取材対象との関係性の中で何を撮るのか、どのように撮るのかという、ドキュメンタリーにおける関係性の問題というのは、若いときからものすごく考えたよね。演出のため、目的のためなら、関係性を壊してでも何かをするということに関しては、カメラマンとしては絶対に亀井さんの側には立てない。絶対に立てないと思ったから、三木さんが当時、厳然とそれを拒否したというのは凄いなと思った。カメラマンとしては、なかなかそれを拒否できないじゃあないですか。
話がものすごく飛ぶけど、90年代に、NHKの、ムスタンやらせ事件(*4)の時に、放送を見ていておかしいと思ったんだけど、高山病になっているスタッフを日なたに置いて、カメラマンは三脚付けて、ズームアップしていた、ということがありました。
まず人命の問題がある。そもそも高山病の人は日陰に置くのが普通でしょ。それを地べたに寝かせて、三脚をつけて撮っている。カメラマンとしては、手を出せないにしても、大騒ぎしている状況を少し外側で撮るとか、手持ちで撮るのが普通の態度なんだけど、カメラがゆっくりズームして、顔にアップしていくんだ。ドキュメンタリーでは、そんなことあり得ないよね。倫理として、撮れるわけがないだろ、って。
そのやらせをめぐっては、カメラマンたちの座談会があったんですよ。撮影監督協会の主催か何か。その座談会に呼ばれた時に、多くのカメラマンが「ディレクターに撮れと言われたら、断れない」というんだよ。何で断れないのだろう?やっぱり、監督とカメラマンというヒエラルキーが劇映画の世界なんかで作られているの?ドキュメンタリーは、そういうものではないよね。もちろんディレクターの、あるリーダーシップというのは必ず現場にあると思うけど、価値観とかモラルとか、人間としてどう判断するかというのは、カメラマンが個々に判断をしている部分もあるんだ。単に技術者としてのカメラマンとか、ディレクターとか、そういうところに優劣や権力構造があるわけではないのでね。
――その後の山崎さんの現場において、「ルーペ論争」を想起させるような経験をしたことはありましたか。
山崎 そんなにはないですねえ。戦争とか、そこまで切羽詰まったところに行くことがないから。
いちばん面白かったのは、北アイルランドに行った時に、アイルランド側の人間なんだけど、暴力闘争を止めようという運動をしている女性運動家(編集注:マイレッド・コリガン・マグワイアとベティ、ウイリアムズのこと)を撮影した時かな。まだIRAの爆弾闘争が盛んだった頃の話です。
ある爆弾事件か何かがあって、それをきっかけに、IRAサイドの政治組織の事務所に非暴力のデモをかけると。それを取材する時に、彼女が条件を付けてきた。とにかく最初はカメラを出さないで、カメラがあると、そのことが相手を刺激する、と。ただし、どこかの新聞社が嗅ぎ付けて、別のクルーが来て撮影を始めたら、あなたたちを止める権利はないから、と言われた。
仕方がないから、車でくっついていくと、さっそく小競り合いが始まるわけ。アイルランドのおばちゃんたちが、女同士エキサイトして水をぶっかけられたりするからさ、回したいなと思っていたけど、ずっと我慢していた。いよいよ激しくなってきた時に、あるイギリスの新聞社がカメラを出して撮り始めたから、それでよし行け!といって、撮影を始めたんです。彼女たちはそれを見ていたんだな。
翌日にその組織の地方支部で集会があって、その時に、未だかつてそういう約束を守ったメディアの人間に会ったことは無いといって、集会の前で僕らを紹介してもらったんだ。それから後は、もう何を撮っても良い、という状態。
もちろんノーベル平和賞をとった彼女たちの考え方を紹介する番組ではあったけど、僕らとしては、彼女たちを全面的に支持しているわけでもなかった。ある運動にシンパシーを感じて、そこに加担してドキュメンタリー映画を作るようなやり方もあるけど、テレビだから、そういう関係でもない。単純に、撮る、撮らない、の関係の中でお互いの信頼関係をどう作るか、という状況です。そこで何を守り何を守らざるべきか、という問題に対しては、いつもナーバスになりましたよね。
――「ルーペ論争」は、対象とカメラの関係性とともに、演出家とカメラマンの関係についても問われると思いますが、山崎さん自身、それについてはどう思われますか?
山崎 僕は自分自身でも演出をやっているので、この企画は他人に渡せない、というのがあるんですよ。もちろん自分で思いついても、あのディレクターとやった方が面白い、というものもあるけど、ベーシックなところからいちいち他人に説明していたら伝わらない、という時には、自分で全てやっちゃう。劇映画の『トルソ』(2010/監督:山崎裕)なんかもそうだけど。
ドキュメンタリーでも、イスラエルに入植しているユダヤ人の家族を撮る、という企画をやった時に、なぜユダヤ人の入植者を撮るかを説明するのが、面倒臭くなったことがありました。その時は、広河隆一(1943-、ジャーナリスト)さんなんかには、ユダヤ人の反戦主義者もいるからそれを撮ったらどうだ、みたいなことも言われたけど、そういうふうに、自分の感情で、何かの運動に加担するためにドキュメンタリーを撮るというのには、僕はどこか抵抗があるんだよね。
もの作りのエネルギーとしては、それは全うであるとは思うんだけど、所詮は何をやってもプロパガンダだろう? という僕なりの疑問がある。そもそも、カメラと対象というのは、物理的にも絶対的な溝があって、決して一体にはならない。対立する軸がカメラのこちらと向こうに必ずあるから、基本的には一体になるわけがないと、僕なんかは思っている。だけどその溝は、必ず何らかの批評性を持っている、と思います。
演出家とカメラマンの間にも、それぞれ別の人格の部分があるわけだけど、それをどう共同正犯にもって行くか。もちろん共犯としてただ演出のお手伝いをする、ということもあるけど、それを共同正犯にするような関係で仕事ができた時がいちばん面白い。テーマも解釈も全く同じではないけれども、ある対等の関係で、演出の狙いもよく理解して、ある種、共同正犯的な関係をつくるのね。別な人格があって、いろんな価値観の中で対象と向き合っているということが大事なんじゃないかな。
ひとりでカメラを持って、ひとりで演出をやるということも最近ではよくあるけど、一つの価値観の中だけで向き合って、その結果生まれてくる映像というのは、純粋な部分がある一方で、か弱い部分もあるような気がする。映像というのは、もうちょっとぶれたり迷ったり悩んだり、そういうプロセスが映ることも含めて、基本的に曖昧さを残したままうつるもの、なんですよ。明確で、分かりやすい画なんて誰も喜んで見やしないんだ。そういう意味では映像には、2つとか3つとか、複数の視点がある方がいいよね。
――さて、今年で4回目を迎える「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」ですが、プログラムディレクターとしての“狙い”を教えていただけますか。
2010年の第1回目は、ドキュメンタリーの歴史的な流れの中で、力のある60年代70年代の名作を見ていこうという企画でした。2回目は、歴史の流れを調べてみると、逆にその中での意味というか、ターニングポイントとして「1969」という、時代に絞った特集を組んだ。
去年の「まなざし」あたりから思っているのは、ドキュメンタリーには作り手がいる、その存在の意識を広めたい、ということです。誰が、何を、記録するか。作家性やいろいろなことも含めて、そこに見るべきポイントを置きたい。
ドキュメンタリーというのは、作り手の表現における精神とか方法論だと思うから、単なる記録とか、そういうことでは無いんですね。現実に今の時代、もう何年も前からいろんなところで、ドキュメンタリーの周辺では、ボーダーを意識した表現が広がってきた。それならば、今回は本人が意識的だろうが無意識だろうが、イメージとしてボーダーを越えている人に焦点を当てようと。
例えば鈴木昭典さんみたいに、ドキュメンタリーだけれどもスタジオでやる、とか、想田和弘監督みたいに、テレビから映画表現に変わっていくとか、実際にそういう人がたくさんいる。最近はテレビドキュメンタリーから上映用の映画として公開する人もたくさん出てきているし、ヤン・ヨンヒさんみたいに、国境という現実にあるボーダーを意識している人もいる。女性、という点では、映像の世界はずいぶん早くから、女性が参加しているんだよね。男女同権とか戦後言われていてもなかなか実現しなかった世界が、60年代には実現されていた。それが渋谷昶子さんだったり羽田澄子さんであったり。羽仁進さんの『不良少年』は完全に劇映画だけど、本物の不良を使ったり、演出も台本通りにやらないなんてことを、あの時代から実現していた。
今回はじめて特集する佐藤輝さんも、ライブの中で、独特な彼のまなざしで、あるものを拾って捉えている。単なる舞台中継ではなくて、ライブ・ドキュメンタリーだと僕は思うんだよね。本人も最近はそういうことを言っているみたいだけど。
僕自身、ドラマをやるにしても何にしても、カメラが本来持っている、対象を記録する機能、複製芸術としてコピーする、という機能を考えると、メディアであるとかそういうものを、常に越境しているような感覚がある。僕はカメラマンだけど、対象に向けてシャッターを押すときは、「疑似」ということにいちばん興味があるのね。役者であろうが素人を撮っていようが、今、何をしているかがそれらしくうつる。つまりカメラで捉えられるのは「の、ようなもの」なんですよ。これが私のおばあちゃん、という時に、本当に私のおばあちゃんとして信じられるか。映っているもの自体からは分からない。そっくりさんでも成立する、虚像なんだよ(笑)。
虚像をもっともらしく思わせるための方法論として、ドキュメンタリーがある。映っているものが信用できるか? 中途半端でやっても、信用されないんだよね。そういうことが、ものすごくベーシックに、表現のベースにあるのがドキュメンタリーなんだよ。単なる記録じゃないというけど、記録がないと、ドキュメンタリーにはならないしね。今年はそれを問う意味でも、越境というテーマにしてみようかと思った。
そもそもドキュメンタリー自体が、メディアとか何かの枠に縛られているものではないんだよね。三木茂さんの場合も、三木さんそのものが越境者みたいな生き方をしてきたわけだし。ドキュメンタリーにはもっともっと可能性がある。今までもあったし、これからもあるんじゃないか。
テレビではドキュメンタリーが減っているなかで、逆に劇場公開や上映の機会は増えている。だったらテレビとか教育映画とか文化映画とかプロモーションビデオとか、そういうくくりは無しにして、ドキュメンタリーという枠だけで、スクリーンで大画面で見て楽しもうよ。ドキュメンタリーは、固くて面倒臭いし説教臭いし、みたいなものだけじゃないんだぜ? そういう思いで、この映画祭を開催しています。
(脚注)
*1:ルーチョ・フォンタナ(1899−1968)。イタリアの彫刻家、画家。空間主義運動の創始者。
*2:「ルーペ論争」:ドキュメンタリー映画において、演出家とカメラマンの関係を考える上で、長く語り継がれてきた、亀井文夫と三木茂の有名な論争。1939年、『戦ふ兵隊』の撮影時、監督の亀井は、日本兵におびえる中国の子供の顔を撮りたいと、子供を羽交い絞めにして三木に「撮れ!」という指示するが、三木は全力でこれを拒否。亀井が後に「キャメラマンはルーペからしかものを見ない、目隠しされた馬のようなものだ」と非難することで論争になる。
*3:この論争は1940年「文化映画研究」誌上で交わされた。その一部始終と考察は、山崎の後輩にあたるカメラマン、辻智彦(『9.11-8.15 日本心中』『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』など)のブログhttp://ameblo.jp/cinematic-neo/entry-10380296904.htmlで知ることができる。
*4:1992年に放送されたドキュメンタリー番組・NHK特集『奥ヒマラヤ禁断の王国・ムスタン』の演出に、多数のいわゆる「やらせ」行為がある事が発覚、社会問題となる。
【映画祭情報】
第4回 座・ 高円寺ドキュメンタリーフェスティバル
2013年2月7日(木)–11日(月)開催
会場:座・高円寺(中央線高円寺駅下車徒歩5分)
プログラム詳細:http://webneo.org/archives/7425
公式HP: http://zkdf.net/