 隔年で開催され、今回も約2万人を集め、去る10月に閉幕した<山形国際ドキュメンタリー映画祭2013>(※以下、ヤマガタ)。この開催期間中、市川昭男山形市長が手にとったことを開会式の挨拶時に明かすなど、ある一冊の本が話題を集めた。大月書店刊『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』。ヤマガタに第1回から通訳者として参加している山之内悦子さんが書き下ろした本書は、これまでのヤマガタの歩みを記すとともに、ヤマガタに集う人々とその上映作品から映画祭の全体像をとらえたヤマガタ論にもなっている。また、ヤマガタと縁の深い人たちとの優れた対談集としても、ひとりの女性の半生記としても楽しめるといっていい。この本に込めた想いを著者の山之内さんに訊いた。(取材・構成=水上賢治)
隔年で開催され、今回も約2万人を集め、去る10月に閉幕した<山形国際ドキュメンタリー映画祭2013>(※以下、ヤマガタ)。この開催期間中、市川昭男山形市長が手にとったことを開会式の挨拶時に明かすなど、ある一冊の本が話題を集めた。大月書店刊『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』。ヤマガタに第1回から通訳者として参加している山之内悦子さんが書き下ろした本書は、これまでのヤマガタの歩みを記すとともに、ヤマガタに集う人々とその上映作品から映画祭の全体像をとらえたヤマガタ論にもなっている。また、ヤマガタと縁の深い人たちとの優れた対談集としても、ひとりの女性の半生記としても楽しめるといっていい。この本に込めた想いを著者の山之内さんに訊いた。(取材・構成=水上賢治)
【関連記事一覧】特集★山形映画祭2013
――ヤマガタには第1回から通訳者として参加されてきたわけですが、最初のヤマガタ体験はどういったものだったのでしょう?
山之内 今回、ヤマガタについての本を書いていながら、ほんとうに申し訳ないんですけど(笑)、1989年の記念すべき第1回のことはほとんど覚えていないんです。当時、フリーランスで通訳や翻訳の仕事をしていて、登録していたエージェントから偶然派遣されて行ったというのが実状で。映画がものすごく好きなわけでも、ドキュメンタリーに興味があったわけでもありませんでした。覚えているのはオープニング上映の『風の物語』(1988 監督:ヨリス・イヴェンス、マルセリーヌ・ロリダン/フランス)が強く心に残ったことと、帰りの空港でシグロの山上徹二郎さんが映画祭のネームプレートをつけっぱなしだったので、「ついてますよ」とお声をかけたことぐらい(笑)。実は第2回のこともほとんど覚えていないんですよ。でも、何か心がグッとひきつけられたことがあったことは確かだと思います。
――では、著書に書かれていますが、ヤマガタにどっぷりはまるきっかけはやはり1993年の第3回の特集プログラムとして組まれた<世界先住民映像祭>だと?
山之内 はい。そのころ、私はイギリス系カナダ人と結婚していてカナダのバンクーバーで移住者として暮らしていました。その中で、自分も差別の対象となることもあり、先住民差別問題や人種問題をなくす活動などにも参加していたので、世界各国の先住民のおかれている状況が他人事とは思えませんでした。また、この年は、国連が国際先住民年と定めた年。先住民の間で自身の手で自らのことを描こうという気運が高まってきていたころでした。その動きをヤマガタが支援し、しかも本に“英断”として書いたように、プログラミングすべてを世界先住民映像作家連盟に委ねたんです。
それまで彼らは歴史学者らに一方的に撮られる存在で、アメリカの西部劇をはじめ映画やドラマで偏見に満ちた視点で描かれてきました。それを考えると、先住民が自ら主導して自身で自らのルーツを描いた作品を中心に組まれたこのプログラムはほんとうに画期的で。この通訳を担当できたことは自分の人生においても大きかった。この経験が「何があってもヤマガタには参加する」と心に決めた理由のひとつであったことは間違いありません。
――その体験は、同年に大賞を受賞した『黒い収穫』(1992 監督:ボブ・コノリー、ロビン・アンダーソン/オーストラリア)をめぐっておきた大論争と合わせて、詳しく述べています。(※パフアニューギニアの高地人をどこか見下ろした視点を含んでいると思われたこの作品に、世界先住民映画祭に参加した先住民映像作家たちは異議を唱え、審査員の間でも賛否があったことが書かれている)
山之内 この本を書きたいと思った大きな理由は二つあります。ひとつは、ヤマガタというすばらしい映画祭をもっと多くの人に知ってもらい、この感動をたくさんの人と分かち合いたいと思ったこと。そして、もうひとつは、この世界先住民映画祭であり、この年のヤマガタで起きたことやカナダの先住民事情についてやはり書きたい気持ちがすごく強かった。あのとき起きたことを、きちんとまとめて書き残しておきかったんです。
――僕は当時を知らない人間ですが拝読して、今へと続く“ヤマガタ”という映画祭の場をひとつ形成したエピソードだと思いました。この議論の熱さはやはりヤマガタならではでしょう。単に最新のドキュメンタリー映画を観るだけの映画祭ではない。作品を通して、世界を知り、見識を深め、異論も反論も含めて意見を交わす場となっていることがよくわかります。こういう体験を共有することで、ひと言で言えば“香味庵”が象徴だと思うんですが、映画の作り手も映画祭のスタッフも、そして観客も垣根なく集い、語りあえる場へとなっていったんだと思いました。
山之内 本にも書いたのですが、私がヤマガタに行かずにはいられないのは “同志”と思うような人々と出会えるから。そう思える人は監督や映画祭スタッフに限ったことではない。そういう人がたくさん観客としても来ている。私自身にとって大切な価値観を共有している人達と出会い語り合えるのが、私にとってのヤマガタ。こういうこと感じているのは私だけではないと思います。
――文中では『ミツバチの羽音と地球の回転』(2010)『六ヶ所村ラプソディー』(2006)などで知られる鎌仲ひとみ監督を引き合いに出されていましたが、“物事をあきらめず辛抱強く努力し続ける人”にはシンパシーを?
山之内 シンパシーというか、すごいなと思います。私もそうありたいと。これは日本に限ったことではないと思うんですけど、人間はどうしても忘れてしまう。
――東日本大震災にしても、あれだけの出来事でありながらすでに風化が始まっているように感じます。
山之内 その通りです。例えば鎌仲監督だったら「原発」に関する作品を発表して、忘れられないようにその実状をいろいろな人に伝えていく。でも、この伝え続けていくことってすごく難しい。先住民差別問題などの運動に関わっていた経験から察するに、「こんなことやっていても世界は変わらない」と心がくじけることが多々あると思うんです。「自分がやる必要なんてないかも」とか。
でも、鎌仲監督をはじめとする多くのドキュメンタリストたちは、少しでも世界がいい方向に進むよう作品を通して訴え続けている。時に飲み込まれそうになる大きな力に抗いながら。しかもほとんどが経済的にも恵まれない状況の中で。この思い続ける情熱とあきらめない心には感服しますし、私も見習いたい。そういう志をもった監督たちの作品が集まっているのもまたヤマガタだと思います。
――それほど強い思い入れがあると、むしろ1冊の本にするのは難しかったのではないでしょうか?
山之内 書きたい気持ちはやまやまでしたけど、ためらいがあったのは確かです。映画の批評家でもドキュメンタリー映画の専門家でもない私のような一介の通訳者がヤマガタについて書くなんておこがましいのではないかと。でも、ある宴の席で、ヤマガタの東京事務局の藤岡朝子さんが「映画祭全体のことをわかっている人なんて誰もいないですよ」と言うのを聞いて、「そうか、事務局の人でさえ映画祭のすべてなんてわからないんだ」と思ったら、なんだか勇気が出たというか(笑)。少なくとも自分がヤマガタで体験したこと、感じてきたことを書く権利はあるかなと。そして、そう思って踏み出してみたら幸運なことが続いたのも大きかったですね。
まず、何があっても書きたかった、先ほど話に出た『黒い収穫』をめぐることで、カナダの先住民映像作家、アラニス・オボンサウィン監督にインタビューをしたいと思っていたら、監督が偶然にも私が暮らすバンクーバーにワークショップで見えるということで。その合間の長い時間を私のインタビューに割いてくださったんです。そのあと、1993年当時、審査員をつとめられた原一男監督に、この作品についての見解を今一度伺いたくて、取材のお願いをしたら、お忙しいのに原監督はわざわざ今一度作品を見直した上で、私の問いにきちんと答えてくださった。実はこういう幸運が続いていったんです。ほとんど頓挫した取材がなくて。ほんとうに皆さん協力的で私のような無名の存在の取材を快く引き受けてくださいました。こういうところからもヤマガタを支える人たちのヤマガタへの並々ならぬ愛情をひしひしと感じました。
――『黒い収穫』をはじめ個人的に思い入れのある作品をピックアップしながらも、ただ自分の意見を押し付けるのではなく、自分とはまったく違う否定的な見方の人の意見にもきちんと取材してその声に耳を傾ける。また、取材対象も監督といった表舞台の関係者だけではなく、ボランティアスタッフなどの裏方まで分け隔てなく対話をされている。そこから不思議とヤマガタの歩んできた歴史をはじめとする全体像や実像が浮かび上がるとともに、『黒い収穫』のような今も語り継がれる伝説的な出来事の再検証と詳細、取材した方々の魅力や人物像も垣間見える。“対話”の形式をとったことで実に味わい深い内容と多様な側面を持つ本になったのではないでしょうか。
山之内 うわあ、褒めちぎりですね。有り難うございます。結局、自分自身にとってヤマガタがなぜこれほど大きな意味を持つのか? 今回の本は、いわばそのことを探す旅でした。書こうと思ったらヤマガタで出会ったいろいろな人の顔が頭に浮かんで、実際に会ったり電話したりメールを交わしたりして話をしたくなったんですね。だから、このような“対話”を反映させた形になったのは自然な流れでした。でも、ページ数の関係で随分と削らざるを得ませんでした。馬鹿高い本にはしたくありませんでしたから。
例えば第5章のヴィンセント・モニケンダム監督との『マザー・ダオ』(1995)での“対話”もすごく要約してあるんです。(※オランダの植民地支配をテーマにした作品で世界の国際映画祭で多数受賞した。1997年のヤマガタで上映される際、税関による検閲で20秒近くのカットが命じられた。問題のカットは、中国人苦力が植民地に到着後、全裸でシャワーを浴びさせられるシーン。本書ではその一連の流れと、モニケンダム監督が当時、検閲問題についてメディアから取材を受けていた際、突然中座して姿を消したことの真意が明かされている)ほかにも紙面が足らず零れ落ちた言葉がいっぱいあります。
――その削る作業は苦しかったでしょう?
山之内 その点に関してはそうですね。でも、書いている間は幸せでした。わけあってこの期間、薄暗い地下室のような部屋が仕事場で(笑)。お世辞にもいい環境といえない状況での執筆だったんですけど、書いていると次々とヤマガタでのすばらしい体験が甦ってきたり、ヤマガタで出会った人たちの顔が浮かんだりで。
――それにしても取材力というかインタビュー手法がすごい。躊躇なく踏み込んでいくというか(笑)。第5章に登場する森達也さんなどは若干ですけど煙たがっているぐらいです(笑)。
山之内 そこは無知のあまりの怖いもの知らずだったからでしょう。私は映画評論家でもドキュメンタリーの研究者でもないので、ちょっとそういう立場の人だと監督に失礼に当たると思ったり、恥ずかしかったりして聞けないことでも聞けちゃうんですね。また森達也監督や安岡さんは古くからの知り合いですから、そこはちょっと甘えさせていただいたというか、大目にみてもらって聞きづらいこともこの際だから聞いてしまおうと(笑)。自分の聞きたいことを中心に置きながら、ファンの方たちが聞きたいけどなかなか聞けないことも意識してインタビューには臨んでいましたね。
――そういうところからこの本は山之内さんのパーソナルな部分も見えてきます。
山之内 本を読んでくれた知人のエッセイストが“好きに生きていいんだと読者を勇気づける本”と感想を寄せてくれて。これがとてもうれしかった。
――山之内さんのユニークな経歴も包み隠さず書かれているので、ひとりの女性の半生記としても読めるんですね。ですから映画に興味のない人にも手にとってほしいと思いました。
そう言っていただけるとありがたいです。
――ところで通訳というお仕事ですが、この本を読んで気づかされることが実に多かった。中でも山之内さんが気をつけられていることはありますか?
山之内 ヤマガタの上映後の質疑応答を例にとるとしたら、観客はいろいろなところから集まって来ている。遠い他県からわざわざ来ている人もいるわけです。ですから、その人たちの貴重な時間を少しでも有意義なものにしたい。話者が直接口にはしていないけど、口ぶりやニュアンス、言葉の選択から読み取れるその姿勢までも聞く側に伝えたい。なかなかできないんですけどね(苦笑)。
それから、なるべくわかりやすく伝えたい。例えば観客席に高齢者が多いなら、安易に外来語を使わないとか。うちの父はすごく新聞好きでしょっちゅう投書したりしているんですけど、私が実家に帰るたびカタカナ語の長いリストを見せて、ひとつひとつこれはどういう意味かときくんですよ。敵国語であった英語の教育を受けてこなかった世代ですから、例えばセーフティ・ネットとかプラシーボとかいわれてもピンとこない。
――確かにいま普通に使われている横文字も多くは“なんとなく”わかっているだけで、きちんと意味を言えとなるとほとんど出てこないかもしれません。
山之内 これは由々しき事態だと私は思っています。ですから、なるべく日本語の言葉に置き換えて伝えることを心がけています。
――最後に今後考えられていることを?
山之内 この本の英訳の出版をどうにかして実現できないかと思っています。さきほどもお話に出た『マザー・ダオ』のヴィンセント・モニケンダム監督が、すごく本に興味を持ってくださったので1冊お送りしたところ “自分について書かれた章の見出しだけでもいいから、英訳して送ってくれないか”という依頼が来ました。それで英訳をお送りしたら、「審査員としていろいろな世界の映画祭に行っているが、通訳者が映画祭について書いた本なんて見たことがない。映画祭のデータをまとめた資料的な本はいくらでもある。でも、これは違う。君自身のヤマガタ体験を主観で書いているところに価値がある。英訳すべきだ。」と強く勧められたんです。なんでもオランダのアムステルダムにある映画博物館にこの本を持って行ってくださったそうです。それから今回のヤマガタで出会った陳彦楷(チャン・インカイ)監督(※アジア千波万波部門『怒れる沿線:三谷』)や、古くからのヤマガタファンにはおなじみのイグナシオ・アグエロ監督(※今回のヤマガタではコンペティション部門『サンティアゴの扉』)らに、英訳を出すべきだと後押しされたこともあり、どうにかして実らせたいと思っています。
【書誌紹介】 『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』
『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』
山之内悦子 著
2013年9月27日発売
定価 本体2000円+税
46判 288ページ
ISBN 978-4-2726-1229-1
“アジア初の国際ドキュメンタリー映画祭”として1989年から隔年開催されてきた〈ヤマガタ〉。同映画祭に通訳者として初回から参加しつづけている著者が、ヤマガタのはらむ「熱」の秘密を、臨場感とユーモアにとむ筆致で綴る。
「山之内悦子のヤマガタへの愛は、怖いほどに気高く、時に挑発と痛快の雑居であり、そして、計り知れないほどの優しさに満ちている。異文化間コミュニケーションを繋ぐ、いや、紡ぐ通訳者の物語は優れたドキュメンタリー映画そのものだ」――崔洋一(映画監督)
【著者プロフィール】
山之内悦子(やまのうち・えつこ)
1954年愛媛県生まれ。英語通訳者。山形国際ドキュメンタリー映画祭には初回以来、毎回通訳者として参加。慶應義塾大学文学部在籍中のカナダ留学が縁で、25年以上バンクーバーに暮らす。字幕翻訳も手がける。
【聞き手プロフィール】
水上賢治 みずかみ・けんじ
映画ライター。「ぴあ映画生活」、ガイド誌「月刊スカパー!」などで執筆中。
『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』(大月書店)
出版記念イベント 第4弾!
ヤマガタとドキュメンタリーを肴に忘年会!
~坂上香監督をお迎えして~
山之内悦子さんの著書『あきらめない映画 山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々』刊行記念イベント第4弾! これまで、小林茂監督、崔洋一監督、原一男監督と3度にわたって対談を重ねてきましたが、今年最後にお迎えするのは『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』で知られる坂上香監督です。
第1部は、坂上監督との対談。監督の最新作『トークバック 女たちのシアター』やクラウドファンディングによる製作、そしてもちろんヤマガタについて語ります。第2部は懇親会&芋煮忘年会。 おいしい温かい鍋を囲んで、この1年を締めくくりましょう!
【日時】2013年12月19日(木) 午後7時15分開場
第1部:午後7時30分~
第2部:午後9時~11時(第2部のみの参加も可)
【会場】スペースneo(千代田区神田小川町2-10-13 御茶ノ水ビル1F)
【参加費】1500円 芋煮ほか美味おつまみの数々&ワンドリンク付き(予約制)
【お申し込み方法】
1. 氏名 2. 住所 3. 電話番号 4. メールアドレス 5. 参加人数 を明記のうえ、
メールまたはFAXで18日までにお申し込みください。
MAIL:info@otsukishoten.co.jp/FAX:03-3814-2926
【会場へのアクセス】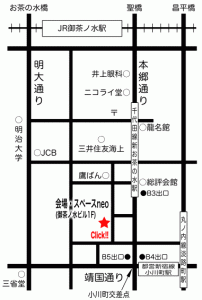 ①都営新宿線「小川町駅」、千代田線「新御茶ノ水駅」、丸ノ内線「淡路町駅」、B5出口より徒歩1分
①都営新宿線「小川町駅」、千代田線「新御茶ノ水駅」、丸ノ内線「淡路町駅」、B5出口より徒歩1分
②JR「御茶ノ水」駅、聖橋口より徒歩5分
■主催:大月書店
〒113-0033 東京都文京区本郷2-11-9
TEL: 03-3813-4651 FAX: 03-3813-4656![]()


















