児童養護施設「光の子どもの家」を8年かけて撮影したドキュメンタリー映画「隣る人」が、5月12日からポレポレ東中野で公開されている。
――公開まで8年という長い時間をかけて、子どもたちとそれぞれの「関係」を、一人ひとり丁寧に積み重ねている。それは映画を撮る上でひとつの手法と言えるのかもしれないが、刀川監督の、子どもたちへのやさしいまなざしの軌跡であるとも思った。
音楽やナレーションなどの情報がない中で、私はいつのまにか子どもたちの内面を見つめていくことに夢中になり、自分の中でそれを「想像する」という作業をしながら、映画を見続けていた。自分にとって「隣る人」とは何だろうか? という、監督によって蒔かれた種は、映画を観終えた今も、私の中で、答えを見出そうと育ち続けている。今回、監督の刀川和也さんにお話を伺った。(聞き手・構成:山森 亜沙美)
「隣る人」という言葉のもつ意味
―― 今、公開されている「隣る人」が初監督作品とお伺いしていますが、どのようなきっかけや経緯があり、児童養護施設「光の子どもの家」を撮影したのでしょうか?
刀川 もともと僕は「アジアプレス・インターナショナル」というフリーランスのジャーナリスト集団にいて、アフガニスタンやフィリピン・インドネシアで取材していました。そこには親を亡くした子どもや、路上で顔を真っ黒にしながら働いている子どもたちがたくさんいて、その一生懸命な姿に惹かれていったんです。それが、自分の中にベースとなっていきました。
そういった取材経験を経て2000年前後に帰国したのですが、その時の日本に、閉塞感や鬱屈さを感じたのです。ハッピーじゃないなと。そんな時に、児童虐待のニュースに触れて、これってどうしてなの?ということを考えるようになり、もう少し詳しく知りたい、と思ったんです。
それで「家族」について調べていた時に、芹沢俊介さんの書いた本「『新しい家族』のつくりかた」に出会いました。そこには、子どもと本気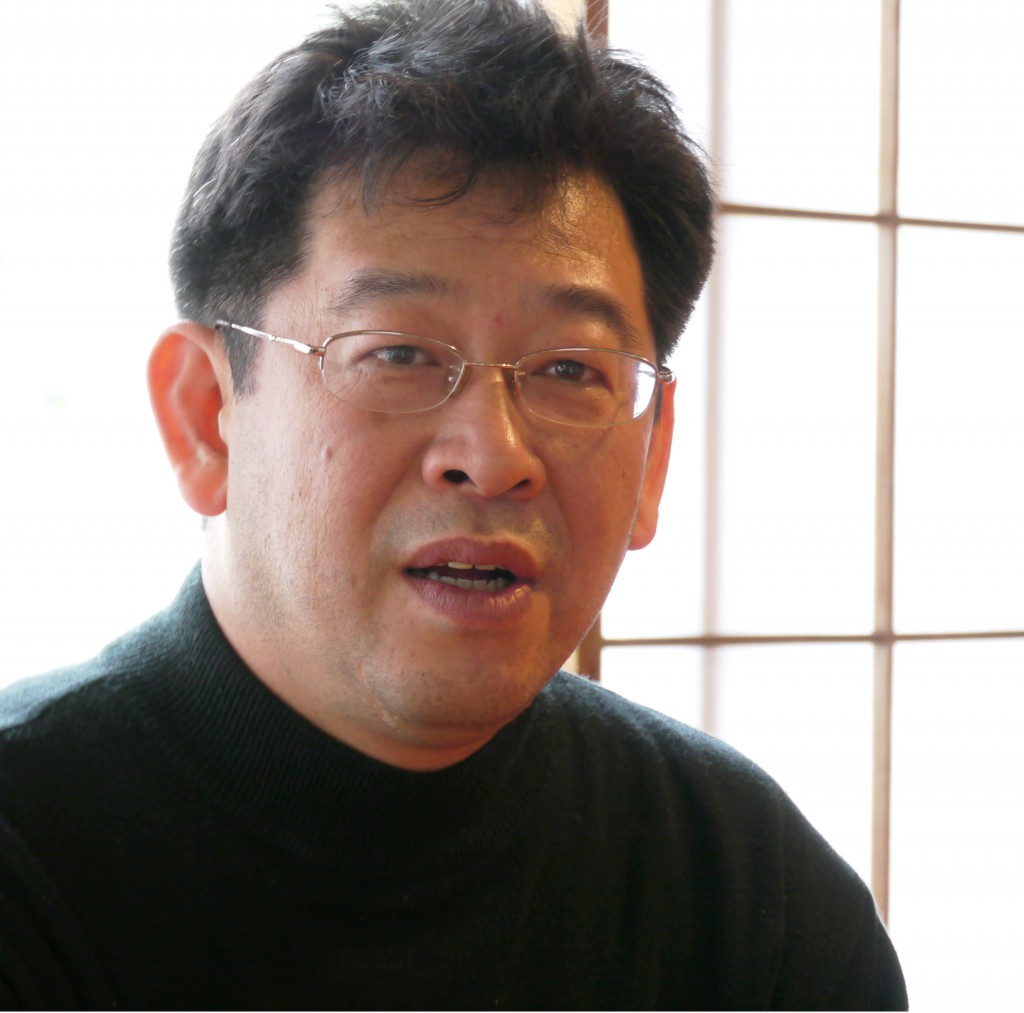 で暮らすためには、そばにいて「居続ける」存在が必要だ、ということが書かれてあり、その時は「隣る人」という言葉より「居続ける」という言葉が頭に残りましたが、これはおもしろいなと思いました。
で暮らすためには、そばにいて「居続ける」存在が必要だ、ということが書かれてあり、その時は「隣る人」という言葉より「居続ける」という言葉が頭に残りましたが、これはおもしろいなと思いました。
菅原哲男さんという方が「隣る人」という言葉を作ったのですが、その菅原さんが当時、施設長(現・理事長)を務めていた児童擁護施設「光の子どもの家」に興味を持ち、取材申し込みの手紙を送りました。それが、この映画を撮ることにしたきっかけです。
―― 「居続ける」という言葉がより印象に残る中で、タイトルを「隣る人」にした決め手は何だったのでしょうか?
刀川 「職員と子ども」が3組出てきますが、撮っている内容はそれぞれの関係性であり、「隣る人」そのものなんです。僕自身、撮影している時から「撮ろうとしているのは『隣る人』だ」と感じていましたし、このタイトルが一番フィットするなと思い、決定しました。
―― 映画を観ていて、「隣る人」と「生きづらさ」という言葉に、何かつながりがあると思いました。
「隣る人」の感覚が希薄だと「生きづらさ」という言葉になるのではと感じました。自分は、人とどうやって関わればいいのかわからないと感じるし、人と人とのあいだに馴染んでいくことに、心がどこかで抵抗する。そうなると自分は孤独だと強く感じる。だけど自分がどうしてそうなるのか、原因が不明瞭だったり、自分は他人と違って何らかの感覚が欠けているなと思ったりします。そういった漠然とした不安感が拭えず、生きづらさを感じます。監督ご自身はどのように思われますか?
刀川 僕もそう思うんですよ。「あの人なら、わたしを見ていてくれる」っていう感覚・経験がないか、あるいは不足していたりする。それは、どこかでみんな抱えているんだろう、と思います。「居場所」とか、「居場所づくり」っていう言葉が言われているけど、そもそも「居場所」って相手との「関係」だし、「他者」がいるから「居場所」がある、とも言えると思います。居場所って、一人でいてもできないですしね。
他者と関わることって、うっとおしいことも多くを占めるわけじゃないですか、気を遣ったり、時間を使ったり。でもそれはそういうことも含むんだ、ということが少しずつわかるようになってきました。ですが、現代はそのうっとおしさを、とてもなくしていると思います。それが逆に「生きづらさ」につながっているのではないか、と思います。
「光の子どもの家」で−「関係」を撮る
 刀川 「光の子どもの家」にいると、日常しかないんです。でも長く子どもたちと付き合っていると、子どもたちの何らかの不安が、ぱっと噴出していく時に遭遇します。でもそれは、まず居合わせなければ、その瞬間には立ち会えない。
刀川 「光の子どもの家」にいると、日常しかないんです。でも長く子どもたちと付き合っていると、子どもたちの何らかの不安が、ぱっと噴出していく時に遭遇します。でもそれは、まず居合わせなければ、その瞬間には立ち会えない。
あそこで「暮らしてる」ということに興味が向かった時に、 何を撮るか?という問いを自分に投げかけると、「人と人との関係」を撮りたくなってくるんです。あの映像一つひとつに、子どもたちとスタッフ、それぞれの関係が映っていると思います。それは短い期間の関係のものもあるし、長い期間の関係もあります。
―― スタッフの間で決めごとを設けていたというよりも、その時のありのままって感じで撮ったのですか?
刀川 そうです。撮影が3人いるのですが、撮影をしながらも、まず自分たちをあの場所に馴染ませていくという時間だったと思うんですね。その時間を積み重ねていくにつれて、ある時、個別に興味の焦点が向いている、ということに気づいたんです。スタッフそれぞれの、被写体との関係が残っているはずです。編集の中で削ぎ落とした部分はありますが、「この関係の中で撮っているんだ」というのは、映画の中でいくつか残しているんです。それは多少、僕が話しかけながら撮るという形をとっていることもあります。
―― 映画の中ではスタッフが直接話しかける、というところがあまり多くなかったように感じていましたが、どのシーンで残しているんですか?
刀川 例えば、マリナとムツミが「ママなんてもういないじゃない」と言って泣いているところで、スタッフが「撮ってんじゃん」「恥ずかしいじゃん」って言われながら撮影していますが、「彼女たちが意識をしながら、スタッフが撮っている」というところに関係があったりするんです。
―― カメラを向けられて、最初はいやがったりする子もいたのではないかと思います。子どもたちの、カメラへの意識や反応は変わっていきましたか?
刀川 基本的に幼稚園の子どもたちは、単純に「撮られてる、恥ずかしいよ」くらいのリアクションだと思うんです。でも小学校の中学年になってくると、「これは恥ずかしいかな?」と自分で考えられるようになってきます。よくカメラに向けてピースをするのは「恥ずかしくないよ」というリアクションです。そういうレベルのものもあるし、例えば、なわとびが100回跳べるので、「これは自慢できるから撮ってほしい」という子どももいます。でも、親のことになったら、敏感に反応します。それは、「やっぱりこれは見られたくない」というものは小学生にもありますし、時間を経てもそれは変わらず存在する、ということだと思うんです。
僕とムツミ、ムツミとマリナ、というように、相手が違えば「いや!」と感じる部分も全然違います。それは関係の中で探っていたというのもあります。当然ドキュメンタリーの撮影をする時には「撮りたい!」と思って撮影に臨みますが、時に子どもから「撮らないでよ!」と言われていても、許してもらえる 「撮らないでよ!」というのがあるんです。それは、僕とムツミの関係や、僕とマリナの関係の中でしかないという領域です。逆に本気で子どもが「いや!」という時は、空気で感じ取ることができます。それが時間を積み重ねるということだし、「私とあなたの関係だよね」という中で撮ることだと思うんです。
―― ムツミ・マリナ・マリコさんが物語の主軸ですが、そのほかにも2組の職員と子どもが出てきます。どうしてあの2組を物語に組み込んだのでしょうか?
刀川 あいだにコウキという男の子と、マイカという女の子が入ってきますが、僕の中ではひとつながりになってるんです。子どもたちって、それぞれまったく違った状況の中でやってきますが、親と暮らせない環境や、自分を受け止めてくれる存在を求めるという意味では、共通するんです。
マイカが担当のマキノさんと別れるシーンで、別れる瞬間をムツミが見ているシーンがありますが、そのムツミも、もしかしたらマリコさんと…っていうことを、同時に感じていたかもしれません。
―― ムツミがノートに「大好き、大好き」って書きなぐっていたところですよね?
刀川 ええ。だから子どもが抱えている不安や感情というのは、一本の線でつながっているはずなんです。
ですが、子どもが成長していくという物語としては、編集でつなげていないんです。そのような見せ方はしていない、と思っているんです。実は最後のショットは、8年の積み重ねがあったうえで決めることができたんですが、僕の中で「8年」という時間は、「『隣る人』という一つの作品自体ができあがるために必要だった時間」だと思っています。ですので、「子どもたちが8年で成長した」という見せ方ではないんです。
「想像する」という見方がある
―― 今おっしゃられたような演出の方向性は、いつ頃定まっていったのでしょうか? 音楽やナレーションがまったく入っていないですし、子どもたちの気持ちを見つめるのに余分なものがないので、ムツミやマリナたちの内面をずっと見続けられる感じがしました。
 刀川 最終的に定まったのは編集過程ですが、基本的に音楽は使いたくない、と最初から思っていました。音楽は時に映画を凌駕するし、単体でも意味をつけられるぐらいの影響力があるからです。
刀川 最終的に定まったのは編集過程ですが、基本的に音楽は使いたくない、と最初から思っていました。音楽は時に映画を凌駕するし、単体でも意味をつけられるぐらいの影響力があるからです。
ナレーションやテロップもそうで、できるだけない方がいいと思っていたんです。ただどこかで説明をしないとわからないところも出てくると思ったので、当時から、ナレーションに近いものになるようなインタビューを心がけていたというのはあると思います。例えば、ムツミがお母さんと会って、そのあとマリコさんの言葉が入るシーンがありますが、マリコさんに「あの時どうだったんですか?」と話を聞かなければ、当然、 「ムツミがお母さんの家へ帰った時のシーン」はなくなってしまいます。その現場に行ったのはマリコさんだけでしたから、それを補いたい、というのもありました。なので、マリコさんにその状況を説明してもらい、且つ何を感じたかを語ってもらいました。これは、誰かに頼んだナレーションとは違う何かになると思ったんです。マリコさんの言葉、菅原さんの言葉は、そういう使い方ができるだろうなあという意識をしながら、インタビューをしていました。
あと、もう一つの理由は、距離が遠いと感じさせたくなかったからです。遠いところにある児童養護施設の職員のマリコさんで、親元で暮らせなくてここに来たムツミさんです、と、映画の中で説明してしまうと、想像力を奪ってしまいます。謎解きとまでは言わないですが、ある意味で関係を探りながら把握して行く見方もあると思います。
ムツミの感情を想像しながら、自分のお子さんのことを考えたり、子どもであった時の自分を感じたり…。見ている人が自由に、色んなふうに考えて想いを馳せながら、自分に照り返してくるような見え方がしたらいい。それは僕が強く想っていた、ひとつの大きなポイントです。
答えはないし、誰も本当のことなんてわかりようがないですが、それは僕もそうですし、映画を観てもらった方にとっても、想像するしかない。と思っています。
監督:刀川和也 製作:アジアプレス・インターナショナル
2011年/日本/DV/カラー/85分
ポレポレ東中野にて公開中 11:00/13:00/15:00/17:00/19:00
他全国順次公開 公式サイト http://tonaru-hito.com/
【執筆者プロフィール】山森 亜沙美 都内の映像制作会社に勤める傍ら、ライター・若木氏の誘いをきっかけにドキュメンタリーマガジン「neoneo」の編集に携わる。週末はコピーライターのスクールも受講している。



















