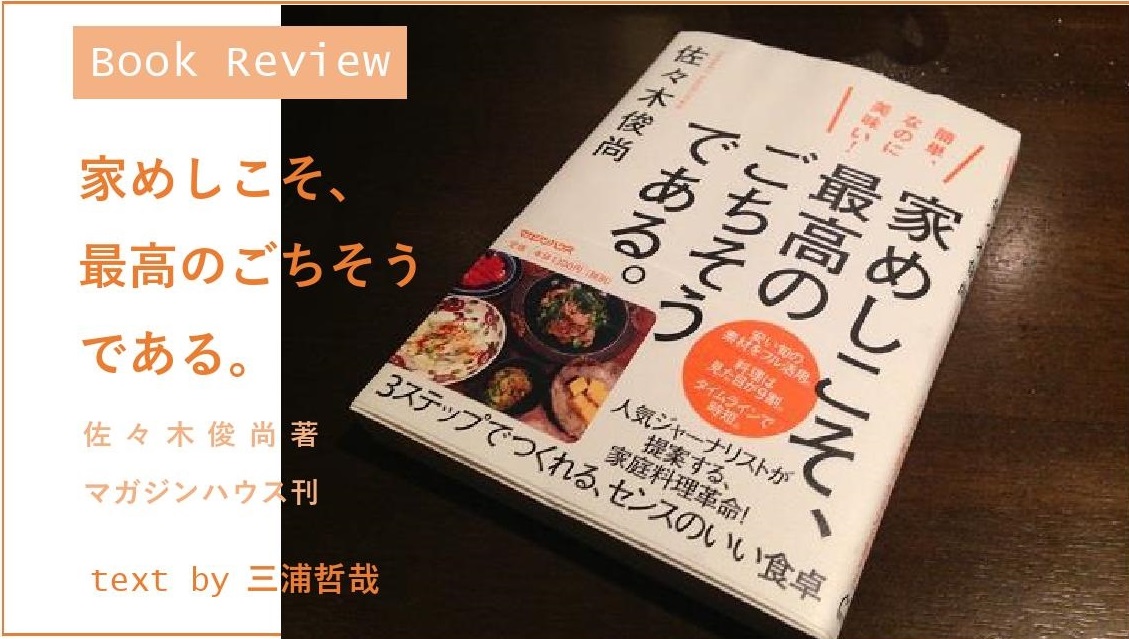
|うまいにはちがいないのだろうけれど
手にとって読み始めれば、実践に裏打ちされた、リアルな料理書だということがわかる。現代日本社会について書かれた著者の本は読んでおり、どれも役に立つものだということを知っていたので、はじめから信頼感はあった。素材を活かし、時間をかけない、シンプルな料理こそが現代において望ましいという主張には筋が通っていて、その機能美の徹底ぶりは清々しいほどだ。すべてがスマートで、情報はシビアに取捨選択されている。
しかし、どうしてだろう。一抹の違和感がある。何かが足りない、という思いが拭えない。頁をめくり、その食の哲学と実践について読み進めれば読み進めるほど、納得の度合はたしかに増してゆくのだが、同時に、ノドに何かがひっかかったような感じも募るのである。だがそれを言い当てるのはなかなか難しい。
まず、うまいかまずいかでいったら、ここで紹介されている料理はすべてうまいはずだと断言できる。それがどのようにうまいか、という「うまさの質」についても著者が自ら解説している通りで、そこに疑問の余地はない。調理を最小限に留めるかわりに、いい素材を選ぶこと。素材自身が語り出すような一皿を目指すならば、畢竟、手は掛けすぎないほうがよい。その通り。ただし飽きがこないよう変化とアクセントをつける技術も入念にレクチャーされる。歯ごたえや香り、舌触り、濃淡の組み合わせの創意工夫をめぐるくだりは、すべて具体的なセンス(感覚)に裏打ちされたもので、著者の食べもの全般への愛情が伝わってくる。
しかし、それでも違和感が消えることはない。端的に言ってしまえば、やはりあまりに素っ気なくはないか、と思えてしまうのだ。たとえば「焼いた厚揚げにしょうがのすりおろしをのせて」というシンプル料理の一例は、単体としてみれば、うーん、あえて書物で紹介するにしてはシンプルすぎるのでは、と感じられる。うまいにはちがいないのだろうけれど。
―
|究極でも至高でもなく、天然でも自分らしくでもなく
独創性のなさ、を問題にしたいわけではない。本書は、ナンバーワンの一皿を目指すのではないし(「究極」とか「至高」とか)、さらにはオンリーワンに拘泥するのでもなく(「天然」とか「自分らしく」とか)、日々の食卓でコンスタントに無理なくおいしいものを作りつづけるためにはどうすればいいか、その方向性を示すことを目指す本だからだ。他のどの料理書にも載っていない、驚くべき料理がなくとも当然である。この薄さの本の中に合理的な調理の心得がコンパクトに手際よくまとまっていればそれでいい。
男性の著者によるシンプルクッキングのすすめには先例があり、本書でも言及されている丸元淑生、玉村豊男などの本が思い出されるが、たぶん生まれた年代のせいだろう、彼らの主張はたまに行き過ぎというか、それ本当に真似できますか、という過剰なところに行き着くこともしばしばである(とくに丸元。私は愛さずにいられないが)。本書はバランス感覚に優れ、無理な要求は一切ない。逆に要求が少なすぎると思うぐらいである。
「素っ気なさ」と言ったが、それはあえて打ち出された倫理的姿勢であるとも思う。類書とのはっきりした違いもここにあるのだが、本書は素材重視を謳いながら、いわゆる「自然」志向からはっきり距離を取る。「自然」をめぐるあれやこれやの「神話」と本書はまったく無縁であり、その点が貴重だと思う。とくに震災と原発事故後に顕在化した、「自然」の観念をたてにした都市部のある種の消費者の傲慢さにげんなりしていたこともあって(それは自己嫌悪でもある)、私には本書のクールさがとても好ましく思えた。
「自然」だけではない。あらゆる「神話」に縛られない料理書を本書は目指していると言えるかもしれない。ル・クルーゼの鍋を使っているけれど、それはファッションとしてではないし、「フランス的なもの」への憧れをスパイスにするためでもない。フォルムが美しいのでテーブルにそのまま出せるとうこと、そしてあくまで加熱において機能的だという理由からである(料理研究家の男性が、ル・クルーゼでは気恥ずかしいからがっしりした黒のストウブを使いたい、などと主張しているのを読んだことがあるが、そういう態度も、著者にはほとんどない)。
本書の料理にはナショナリティーがない。フランスとか、イタリアのどこそこの地方風とか、そういう「物語」だけで食わせる料理がほとんどないのだ。ラタトゥイユの作り方は紹介されているけれど、それはあくまで野菜の優れた調理法だから取り上げているだけで、南欧気分に浸るためではない。
ひるがえって、世の料理書の多くは、「物語」や「神話」の付加価値で食べ物を変身させようとすることにあまりに重きをおきすぎている(カボチャの馬車のように)。本書はその対極を行く。料理の「脱神話化」を目指す点においてこそ、本書には、ジャーナリスとしての著者の仕事との一貫性を見ることができる。
―
|魚の不在、断食の過重?
そう、それはいいのだが、その姿勢をよくよく理解してもなお、何かが足りない、という思いが消えてなくなることはない。料理に「神話」はいらない、むしろ無駄である。それはわかった。しかし、これだけ料理や食文化に造詣の深い著者にしては、少し作るものが無欲すぎるのではないか、という疑問が浮かぶのだ。
実際、著者が自身の外食経験について触れているところでは、いかにも食いしん坊が選びそうな店と料理が紹介されている。お気に入りの料理本の引用箇所に関しても、理屈抜きによだれがたれてきそうな、つまり料理の官能的な悦びがはちきれそうなところばかりが選ばれている。外食と「家めし」の役割が分かれているということはわかるが、しかしその美味への貪欲さと、実際に本書で紹介されているレシピの間に、いささかギャップがありはしないか。
魚の不在、ということもある。ただしそれは、本当に魚が好きだとかえって日々の献立にシステマティックに取り入れられない、ということなのかもしれない。揚げ物とか濃い味の煮付けなどなら多少鮮度が悪くても目をつぶれるかもしれないが(私はいやだが)、素材が語るシンプル料理に使えるほどの鮮度の魚がいつでも手に入るのはよっぽど恵まれた場所に住んでいる方か、金に糸目をつけない方だけだろう。
本書で取り上げられている魚料理の素材は、首都圏ならば比較的鮮度のよいものが手に入りやすいアジなどに限られており(相模湾が近いから)、しかもそのまま食べるのではなく、マリネにするとか、香味野菜と混ぜ合わせるとか、一手間がかけられている。魚の素材そのものを味わう快楽は、外食に割り振っているということなのかもしれない。
「断食」のウェートが大きすぎるのではないか、という疑問もないではない。著者は、年に数回、それぞれ数日間の断食を自らに課しており、そのときに研ぎ澄まされる感覚──味覚が非常に鋭くなり、素材の微細な味わいを聴き取ることができるようになるという──が、現在たどりついた食のスタイルにおいてとても重要な役割を果たしている、と冒頭で述べている。
だから、本書のレシピを実践する前にみんな断食しなければその本当の良さがわからないのではないか、という言い方だってできかねないところはある。だがここでのポイントは、食とそれを味わう身体は連動しているということを理解しなければならないということだ。
たとえば著者と同様、素材重視のシンプル料理を指南する料理研究に魚柄仁之助がいるが、彼の場合は「断食」ではなく、「3ヶ月我慢」という標語をレシピ集のまくらに掲げていたのだった。動物性脂質やこってりした調味料のたぐいを一切使わない料理は最初、物足りなく感じるかもしれないが、3ヶ月で劇的に変わる、と魚柄は言った。だんだんと体がそれに慣れてきて、舌が鋭敏になるというのだ。同じようなことは丸元淑生もすでに主張していた。そしてこれらはすべて本当のことなのだと思う。「断食」は、実際にしてみたら劇的効果がありそうだが、そうでなくとも、こういう料理を食べながら慣れていけばいいだけのことだ。


















