
「戦争するな!」路上で声を揃えて絶叫する群衆。「どこ見て政治やってんだよ!」声を枯らしながら怒鳴る男性。2015年6月から毎週金曜日に国会議事堂前で安保関連法案に対する抗議活動を開始した学生団体「SEALDs」(シールズ : Students Emergency Action for Liberal Democracy-s / 自由と民主主義のための学生緊急行動)のひと夏を追ったドキュメンタリー映画『わたしの自由について~SEALDs 2015~』(2016)を知ったのは、昨年春のアップリンクでのこと。
ちょうどそのころ私は同館で同時期に公開された『LISTEN リッスン』という、ろうの監督がろう者を集めて撮影したドキュメンタリー映画の宣伝を担当していたので、監督やスタッフたちとよくアップリンクに行ってはその予告編動画を目にしていた。その時に、「ろう者にだって選挙権はあるんだから!」と、ろう者たちが『わたしの自由について』の販促ブースの前で手話を繰っていたことを覚えている。
「興味があっても(邦画の自主映画は)日本語字幕が付いてないから見られない」。そんな言葉がどこかを巡って西原監督の耳に入ったなんてことはないだろうけれども、彼のつくった新作は『もうろうをいきる』という、盲ろう者とその周辺の人たちの生活と気持ちを写しとったドキュメンタリー映画であり、その上映には各回音声ガイドと日本語字幕が付いているという。巷にあるハウツー本ではないけれど、口にすれば何かが変わる。なんていう、不思議な力が働いたのか。ただその一方で、安保関連法案の方は北朝鮮のミサイル発射問題(2017年8月29日)により、いよいよどうなるかというところまで来ているのだが。
「秀子さんを救ったのは、言葉の力でした」。劇中で一番印象に残ったのは、西原監督が自らナレーションを務めて語ったその一言だった。秀子さん(58歳)は生後2カ月で耳が聞こえなくなり、38歳の時に病気で目が見えなくなった盲ろう者だ。洗濯機を前に、凹凸でボタンを探り、振動でその運転を確認する。彼女は母親と兄との三人暮らし。家事や洗濯は彼女の仕事なのだという。慣れた手つきで食器を洗い、庭に出て物干し竿に洗濯ものをかけていく。手探りで物の在りかを確認し、こともなげに作業をこなす。カメラは少し離れた位置から彼女の日常を写し撮る。

本作には秀子さんと同様に、西原監督が全国を回って取材した盲ろう者が登場する。柔道青年。能や歌舞伎を楽しむ女性。大学教授。日本には少なくとも1万4000人の盲ろう者がいると言われている。彼らはいつ「盲ろう」になったのか、その時期によって、それぞれがそれぞれに異なるコミュニケーション方法をとる。はじめはろうで、あとから目が見えなくなった人。初めは盲で、あとから耳が聞こえなくなった人。生まれたときから目が見えなくて耳が聞こえない人。全盲ろう、弱視ろう、盲難聴、弱視難聴。手のひらに文字を書いて伝える「手書き文字」、手話が分かる人であれば互いに手の動きを伝え合う「触手話」、通訳者が盲ろう者の指を直接たたく「指点字」、あるいは聴力や視力が若干ある人ならば音声言語を用いてコミュニケーションをとる場合もある。
映画の冒頭では2016年に福岡県北九州市で行われた第25回全国盲ろう者大会の会場の様子が映し出される。寝ている盲導犬。白杖をついて歩く人。手を触り合う人。一語で記される「盲ろう者」の一言では言い表せない姿が目の前に広がる。1991年に設立された社会福祉法人全国盲ろう者協会の支援によって、引きこもりがちな傾向にある盲ろう者が世の中に出て、まわりの人たちと会話を楽しむ場が全国各地でつくられているという。笑っている人もいるし、会場にいる秀子さんも居心地よさそうで、なんだかとても楽しそう。一体何を、話しているのだろうか。映画は総体としての「盲ろう者」を捉えると共に、介助者を通して、盲ろう者個々人の胸の内に迫っていく。
「死にたい。死にたい」。盲ろうになったばかりの秀子さんは、タンスの中で自傷行為に走るほど混乱した時期があったという。「生命維持そのものは、比較的なんとかできるんですよ」。映画の中盤、盲ろうの大学教授である福島智さんは、盲ろう者についてそう語る。もちろん、身体や家庭環境によりそうではない人もいるだろうけれど、前出の秀子さんの家事の様子を含めて、映画の中でも食べて、移動して、くつろいで、日常生活をある程度独力でこなす盲ろう者たちの姿が散見される。ただそんな中で、生物学的な生のほかに、「どうやって盲ろう者の人生を意義あるものにしていくか」。福島さんは問題提起する。
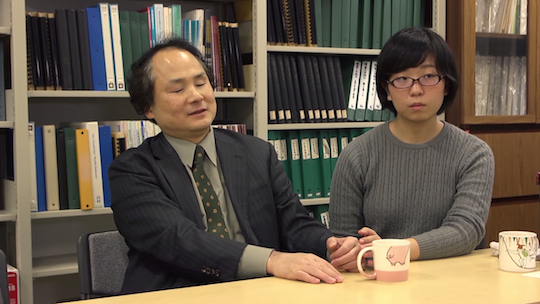
生後まもなくして聴力と視力を失くした娘をもつ父母はこう語る。「まわりにとって便利なのはどっちなのかと思って考えて育てるよりも、もうちょっとコミュニケーションがとれたら、もっと世界が開けるんだっていうことを、やっぱり(娘に)教えてあげたいなと思う」。連れられるまま歩き、だらんと首を垂れる24歳の女性。音声言語、手話言語、点字が用いられることはなく、いかにして意思の疎通が取られているのか。抱きかかえて起こす。手をとってモノに触れさせる。繰り返される当てどないコミュニケーションの毎日。彼女の妹は、姉が自分のことを姉妹だと認識しているのかどうか訝しく思うと言う。ただそれでも、たまに姉が彼女の頭を撫でることがあるのだと、はにかみながら言う。それはまるで、画面のこちらにまでその手のぬくもりが伝わってくるような、健やかな笑みだった。「一緒に生きているっていう感じがありますよね」。触れる。互いの熱を感じあう。言葉にならないコトバによる、ささやかなコミュニケーションがそこに生まれているのだろうか。
「結婚したい」「その前に自立したい」。25歳の青年は触手話で介助者を通してカメラに向かって自分の悩みを吐露していた。27歳の女性は「本当のことを言うと、聴者に生まれたかった」と手話で胸の内を語っていた。秀子さんは撮影隊に向けて点字と平仮名と漢字で「とても楽しかったです。ありがとうございました」と別れを惜しむように手紙を書いていた。

本作の中では、『わたしの自由について』の中で映し出されたような大声は聞こえてこない。また、いつかのTV番組のような、盲・ろう者が練習に励んでヨサコイを一緒に踊るというような劇的な演出も見当たらない。辛抱強く、被写体をフレームに収めて、淡々と日々を過ごす盲ろう者の姿を追いかける、近づくカメラの動きがあるだけだ。ただそれでも、この映画は決して物静かな作品なんかではなく、強く、烈しく、勇ましい声の数々が、スクリーンやスピーカーから木霊してくる。盲ろう者たちの、触手話による言葉。音声による言葉。点字による言葉。彼らの胸の中の言葉がこぼれ出してくる。秀子さんが触手話を繰って話す時に見せる生き生きとした姿がいつまでも目に焼き付いて離れない。福島さんの詩「指先の宇宙」の中にある一節が眼前に広がる。
「ぼくが指先を通してきみとコミュニケートするとき そこに新たな世界が生まれ ぼくは再び世界を発見した」
「コミュニケーションはぼくの命 ぼくの命は いつも言葉とともにある」
ただ、映画館を出てから先、盲ろう者たちの言葉に対して、彼らの言葉を、誰がどれだけ受けとめることができるのだろうか。映画の中では、盲ろう者と共に、介助者たちの率直な言葉も映し出される。支援を頻繁に行いたくても仕事ではないので生活上難しいこと。社会的にも、法的にも、「盲ろう者」の定義が確立されていないため支援が行き届いていないこと。現行の社会制度を生きる盲ろう者たちのことを、福島さんは「牢屋の中にいる」ようだと例える。誰にも声が届かない、暗く密閉された空間にいる人たち。むろん、映画館のスクリーンに映し出された人たちだけが盲ろう者なのではなく、光の当たっていない幕外の暗闇にはさらに、言葉を求める盲ろう者たちが沢山いるということも、気に留めねばならない。
全編を通してナレーションを自ら務めた西原監督の、盲ろう者の姿と彼らの言葉を真摯に語り続けたその言葉が、盲ろう者への、ひいてはそれを取り巻く介助者たちへの法的、社会的処置の変化につながればいいと願う。言葉が新たな世界を生む。言葉によって世界が開かれていくことを、願う。
 【映画情報】
【映画情報】
『もうろうをいきる』
(2017年/日本/日本語/カラー/ステレオ/91分)
監督:西原孝至
企画・製作/山上徹二郎、大河内直之、北岡賢剛
プロデューサー/小町谷健彦、山上徹二郎
撮影/加藤孝信、山本大輔
音楽/柳下美恵
協賛/NPO法人バリアフリー映画研究会
協力/社会福祉法人全国盲ろう者協会、認定NPO法人東京盲ろう者友の会、東京大学先端科学技術研究センター・福島研究室、NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター(MASC)、Palabra
製作・配給/シグロ
写真は全て© 2017Siglo
ポレポレ東中野にて公開中、9/16(土)より渋谷アップリンク他、全国順次公開
公式サイト:http://mourouwoikiru.com/
【筆者プロフィール】
大久保渉(おおくぼ わたる)
1984年生。ライター・編集者・映画宣伝。執筆・編集「映画芸術」「ことばの映画館」他。宣伝『LISTEN リッスン』「東京ろう映画祭 事務局」他。「neoneo」#09【完全保存版 「いのちの記録 障がい・難病・介護・福祉】にも寄稿しました。他寄稿者の鋭い文章と併せてぜひ。![]()


















