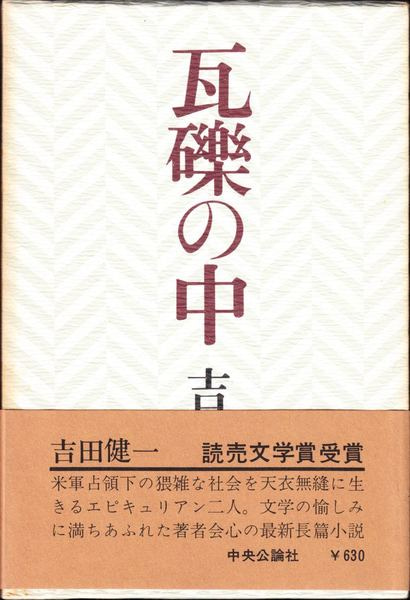
小説の舞台としてかつての町や都市のすがたが描かれているとき、それを知るのもまたおもしろさのひとつである。たとえば吉田健一は、小説「瓦礫の中」や「絵空ごと」、「東京の昔」などにおいて作品ごとに時代を設定して東京を描いてきたが、作品内においてはその舞台となる時期のさらに以前の東京について言及されることも多い。ここで取り上げる「瓦礫の中」(一九七〇)(*1)は、敗戦から幾年、焼け野原に町が立ち現れるまでの変遷の記録でもあり、またその題名にある通り、瓦礫の中から人間が立ち現れる小説である。なぜそのような題名にしたのか、冒頭で次のように語られる。
「こういう題を選んだのは曾て日本に占領時代というものがあってその頃の話を書く積りで、その頃は殊に太平洋沿岸で人間が普通に住んでいる所を見廻すと先ず眼に触れるものが瓦礫だったからである」
空襲を受けた焼け跡にはいまだ崩れ落ちた建物の残骸や、焼けて外形を損じたものが散らばっており、「その瓦礫の中に人が住んでいない訳ではなかった」という記述とともに、暮らしをたてる場所として防空壕があげられた後、つぎのようにつづく。
「ここで人間を出さなければならなくなる。どういう人間が出て来るかは話次第であるが、先に名前を幾つか考えて置くことにしてこれを寅三、まり子、伝右衛門、六郎に杉江ということで行く」
こうして作中に現れた寅三は、まず防空壕の外に出て焼け野原の風景を見渡した。つまりは、地下の防空壕から瓦礫の中に現れ出たのであり、その周囲に人はいない。高台の無人の焼け野原の風景は、下を見れば瓦礫が散らばり、遠くを見遣れば地平線に箱根連山の上に富士が浮かび上がる。そこで寅三は現にいま立っている土地へ思いを巡らし、「自分が生れて今まで住んで来た土地が全く違った新しい場所に変った」ように感じ、あるいはまた、「そこに就て自分が知っていた一切を吹き消して別なものになったのであり、それをもとの場所と言えるかどうかも多分に疑問の余地」をもった。そのとき寅三の頭の中にあったのは、かつての土地や場所のすがたであり、いまではその土地や場所と紐づいていない人間とまでいうのは過言にしろ、寅三はその土地や場所を連続する時間の中で捉え難くなっている。(作中ではもちろん「昨日」のことが描かれているわけではないが、「昨日」も寅三が同様の感慨をもったとしてもふしぎではない)。ここではまず寅三を連続する時間の中にいない人間、あるいはかつての土地や場所とのつながりを失った人間として捉えることにする。
そして腹が減った寅三が防空壕へ下りていくとつぎに現れるのが寅三の妻・まり子である。二人が暮らす防空壕に窓がないのは当然だが、防空壕を掘る作業自体に面白みを感じた寅三が幅を広く掘り進め、屋根を支える柱も何本か立てたため、人が背を伸ばせるほどの深さがあった。
「土の側面に杭を打ち込んで板を張ったり腰掛けを取り付けたりしたので住むのにそう不愉快なことはなくて今は床にも板を並べて畳が敷いてあった。その畳の上にちゃぶ台を持って来てこれから寅三とまり子の朝の食事が始る所である」
これが二人の生活の場であるのだが、英語の教師だった寅三が占領軍の機関から得た翻訳の仕事をする際は、ちゃぶ台で書きものをする。まり子によれば、防空壕の生活に不自由がないこともないが、問題は自分と寅三がそこにいることであり、そのまわりに焼け野原があり、その中心が防空壕だった。後に思わぬことから大金を手にした寅三が家を建てると決めたとき、「併し壁に窓なんていうものがある家に住んだら初めのうちは不思議な気がするだろうね」と言うのに対し、「直ぐに馴れますよ。この窓がない防空壕にだって馴れたんだから」とまり子は即座に返している。このまり子という人間のものの考え方が明確に述べられているのは次の場面である。
「まり子にとってはそれまでいたどんな所も消えてなくなったのではなかったとも言えるので、まり子の頭には隅田川もセーヌ河も曾てその岸で一生の一部を過した河という形で残っていた」
かつてあったことが記憶に残っていればそれはそこにある。まり子にとって「凡ては現在で普通に現在であるものが過去の集積に向けてまで拡がっている」ということになる。それゆえに防空壕の暮らしにおいても我慢や辛抱というところに帰着せず、新しい家を建てる際にはその暮らしを懐かしみ地下室を設えようとする。また、生活という訳ではないが、まり子の記憶に戦争中のことがよみがえった場面がある。空襲を受けて燃え上がる家の防火をあきらめたあと、寅三とまり子が家の門を出た途端に隣家が家に崩れかかった。二人にとって危険が迫る渦中に身を置いていたと気づくのは危険が去った後のことであり、「そうするとその危険はなかったのと同じことになる」。しかしながら、寅三が仕事で別の場所で寝泊まりしているときは、空襲で寅三の仕事場の方角の空が赤く染まるのを眺めていると荒涼としたものをおぼえる。
「人間が一人でやって行けさえすれば別に問題はないのに、どっちが自分か解らないような相手が出来るのはどうにも困ったことだという感じがした。そういう相手を作るというのは無謀なことでもあり、どれだけ論理をこねくり廻してもそれはいいことになるものではなかった。これも人間にとって諦めなければならないことの一つだろうか」
まり子にとって起点は現在にあり、現在を起点として記憶とともに過去の拡がりとのつながりも保っている。一方で寅三がそこにいることが問題だという自覚もあり、連続するつながりを失った寅三を傍らでどのように見ていたのだろうか。寅三という人間を探るうえでも、作中に現れる人間たちをもうすこし見ていきたい。
作中において三番目に現れるのは、伝右衛門という隣人である。隣人といっても、伝右衛門が暮らす防空壕と寅三とまり子が暮らす防空壕の間には距離があり、高台から谷間そしてまた高台へとつづくその間には誰も住んでいないという理由から、隣人と呼ばれている。伝右衛門の防空壕はかつての防空司令部でありいまはアメリカの屯所となっている建物がある高台の一角にあり、間の谷間にあった貧民窟は焼け出されて跡形もなくなった。その焼け跡のなかで、寅三が「少くともそこに住んでいて生き延びたもので昔を懐かしがるものなどいないに違いない。その中には一旗揚げて都会議員か何かになっているものがあるかも知れず」、あるいは焼け残った大きな屋敷にかつてここに住んでいたものが納まっているというのもあり得る、と考えるところなど、「戦後」というものへの寅三の見方がよく表れているがそのことは後述する。
登場時の伝右衛門は、防空壕の入り口に腰掛けて日向ぼっこをしているが、寅三が来たので二人でまた防空壕へ下りていく。そこは防空壕といっても寅三のところとは規模が違い、次の間から次の間へと連続していく豪華なものであった。というのも、伝右衛門というのは戦時中に軍需産業で全盛を築いたため、その防空壕の建設には軍部の協力もあった。その伝右衛門が寅三と親しくなったのは当時闇市同様に違法だった飲み屋で、それから近所付き合いがはじまった。そのなかで寅三をどのように観察したのか、作品の後半では、「貴方は政治はやる気がないのかね」と寅三を誘う。寅三には断られるが、その後も寅三を政治の場のどこに配置し、どこで思いがけない働きをしてもらえばといった考えに誘われるが、その背景には寅三という人間に対する次のような信頼があった。
「寅三の政治評論は常識だけを頼りに、又その常識に自信を持つだけで書いたもので、これは政治評論家ということで人の注意を惹くには適していなかったが政治に携わるのにそれ以外の何もなくてよかった」
それでもしまいには伝右衛門も寅三を政治へ誘うのを諦めるが、伝右衛門の寅三とまり子への信頼は揺るがず、その付き合いのうちに六郎を運転手として雇うことになる。
この六郎というのは、寅三が占領軍の機関から翻訳の仕事をもらっていたときに親しくしていたジョーの運転手兼通訳であり、もとは「戦争浮浪児」かどうかまでは明確ではないが、「浮浪児」だったところをジョーを介して日本人の家族に引き取られた。ジョーがアメリカに帰国した後は占領軍の運転手となり、作品の後半で登場するときには円タクの運転手を勤めている。六郎はかつて翻訳の仕事で機関に出入りする寅三のことをスパイだと信じこんでいたが、あれは方便で実は翻訳の仕事をもらって食っていたんだと寅三に打ち明けられると、「そんな簡単なことだったのか」という思いとともにこれまでの月日が長いもののように感じられて次のようにいう。
「貴方をその為に偉い方だと思ってたんです」
このとき二人は互いにそれまで知らなかった人間と会っているのとおなじことになり、それぞれに好意を持つ。まり子もまた六郎を見たときから素直な人間だという印象を受けており、六郎と伝右衛門の間を取り持つ。結局、六郎は伝右衛門の敷地にあった車庫を改築した二階家に住みこむ運転手として働くようになる。
こうして高台と高台の距離は変わらずに、登場人物たちがそのなかに見事に収まっていくのだが、何年間とは明記されていないそのあいだに寅三の身になにが起きていたのか。作中には変貌していく東京のすがたやかつての東京との対比も描かれているが、ここでは高台と高台のあいだの風景の変遷から、寅三のなかで生起されていく家への考察をその端緒としたい。
はじめは焼け跡の瓦礫のなか、寅三とまり子の防空壕と伝右衛門の防空壕のあいだに住人はおらず、寅三の防空壕に招かれた伝右衛門が歩いてくるのも遠くから見渡せた。やがて伝右衛門が家を建てたころには焼け野原にもところどころに家が建ち、街灯のあかりも灯るようになり、そうした家や家の窓から明かりが洩れるのを見るうちに、防空壕は人間が住むために作られたわけではないという気持ちが寅三の心に芽生えてくる。そのことで伝右衛門の家を訪ねると道の両側にはほとんど家が建ち並び、街灯も立ち、一帯が町になっていた。
「こういうことは直ぐにそうなる訳では勿論なくて、どこかに家が一軒建ち、建ったなと思うのを何度か繰り返しているうちに道の片側でもが家で埋められ、その一軒毎にもう見馴れているからすっかり埋まったということに気が付くまでに時間が掛る。それならばその辺一帯が野原だった時からこうしてどこを向いても家があるようになるまでにどの位たったのか。(中略)もしそれが何年間かであるならば、それを他所に寅三がまり子と今もこれから戻ろうとしている防空壕で平和に暮らして来たということは事実であるようだった」
自分が暮らす防空壕のまわりも次第に家に囲まれてくるなかで、その家に住む近所の人々はどうやって家を建てたのか、自分にもその真似ができなければ家は建てられないのではないか、という考えを寅三はやがてもつようになる。
「その人達が何かの意味で戦後の人間である証拠にそこが焼ける前に寅三達が付き合っていたのは一人も戻っていなかった。そうするとそういう戦後の人間にならなければ尋常な手段で家を建てることなど望めないのだろうか」
つまり、家を建てるには「戦後の人間」にならなければならない。この「戦後の人間」とおなじ人間であるという感覚を寅三は備えておらず、それは町への視点からも窺える。寅三の目には、焼け野原のあとにできた町がたとえ元の道に沿って出来ていたとしても以前の町とは似ても似つかぬものと映り、むしろむかしのおもかげを消え去らせる別なものがそこに現れているように思えた。寅三にとって確かなことは、焼け野原がどこかの町に変わったということだった。
「或は地下で暮すのが少し長過ぎたのかも知れなかった」という一文をどのように捉えればよいのか。作中には、占領時の不思議として、占領軍の出動が必要なほどの反米デモが起こった記憶もないとして、「言わばそれは居候の気安さだったのだろうか。それで居候は居候で自分のことにだけかまけていられた」という箇所があるが、その意味において寅三が「居候」生活の終焉を徐々に自覚し、建ち並ぶ人家を眺め、「戦後の人間」という考えに駆り立てられるなかで、家を建てるという行為によって文字通り地下の生活を切り上げようとしたのだろうか。じっさいに家を建てられることになったとき、「もう駄目だと思っていた航海の終りに港に近づく船の船長の心情というようなこと」が寅三の頭に浮かぶ。そしてしかしそれではまり子との防空壕の生活がそれほど辛かったのかと問い、そうであれば隣に家が建つのを見るのも嫌だったはずであり、少なくとも防空壕の生活には住むということへの不足はなかったと考える。寅三にとって、防空壕の生活の土台になっていたのは「家などというものはもうないという間違いない認識」だった。うらを返せば「戦後の人間」たちが現れたのもその認識が崩れた表れだったのだろうか。
まり子にとって、問題は自分と寅三がそこにいたことであり、まわりが焼け野原から家並みに変わってもその中心には変わらずに防空壕があったはずである。では寅三にとってはどうだろうか。防空壕でまり子と伝右衛門と三人で宴会をしているさなか、寅三は防空壕を一向にみじめにも感じず、自分が生きているのを感じられれば吹き込む夜風も気にならず、たとえ家のなかで三人で飲みながら話していても別にどうということはないと思う場面がある。つまり問題は自分とまり子と伝右衛門がそこにいることであり、自分が生きているのを感じるという「間違いない認識」である。かつて焼け野原の風景を見渡し、「自分が生れて今まで住んできた土地が全く違った新しい場所に変った」と感じた寅三は、防空壕の生活において「間違いない認識」を土台としてきた。作中で具体的に描かれることはないが、焼け野原の跡にどこかの町が立ち現れ、「戦後の人間」たちがつぎつぎに現れ、そのなかで寅三が土台にしてきたものが崩れていく。さきに述べた「船長の心情」が寅三の頭に浮かぶように、寅三は作中で危機のさなかにあり、その途上から家への執着を道行きの同行としたのではないだろうか。また、その危機というのは、もうこれいじょうは寅三というものではいられないという認識ではなかっただろうか。
骨組みだけの家のなかに入り、自分の部屋になる場所に立った寅三は、却って行きどころのない思いに捉われる。
「それは彼が防空壕での生活に馴れたように今度は家に住むことに馴れなければならないということだった」
家を建てたのちに、評論家と呼ばれる仕事をしていくなかで寅三から危機が去ったのか定かではないが、光の射す変化が起こる箇所を最後に引用して終わりたい。政治評論について教えを請いに、寅三が伝右衛門の家を訪れた場面である。
「この別な寅三にとって政治は外の騒音であり、従って政治評論などというのはもっと遠くにあってないも同然のものになり、その代りに寅三が家を出る時にいたまり子が今寅三が向い合っている伝右衛門さんと結び付き、そこの家は寅三の家の延長でそのように実際に存在して息づくものばかりの世界が出来上った。或は出来上ったのではなくて寅三はもう前からそこにいた。又その世界を維持する手段である限りでは政治は伝右衛門さんが暗いので立って行って付けた電燈の光と選ぶ所はなくて、ただその光の方が遥かに具体的なものに思われた」
*1 吉田健一「瓦礫の中」(『瓦礫の中』、中央公論社、一九七〇)
【書誌情報】
『瓦礫の中』
中公文庫 1977年8月発行 入手は古書のみ 文庫判 190p
ISBN 978-4-12200-479-5
【執筆者プロフィール】
中里 勇太(なかさと・ゆうた)
文芸評論、編著に『半島論 文学とアートによる叛乱の地勢学』(金子遊共編、響文社)。



















