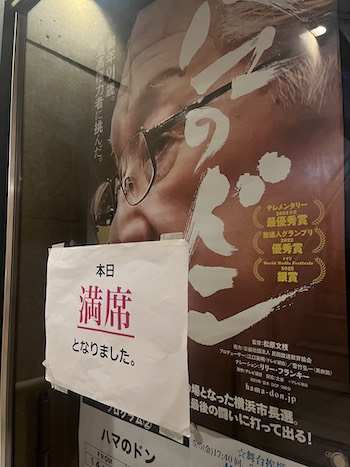
横浜港埋立地へのIR(統合型リゾート)誘致をめぐる動きについて、反対派の急先鋒である港運業の中心的人物・藤木幸夫(1930〜)を軸に描いた『ハマのドン』が公開された。2018年の誘致決定から、横浜市長選挙での反対派の市長当選と誘致撤回まで約4年にわたる経過と、藤木の回顧により人生を過去へ向かってたどる流れとが交錯する映画だ。テレビ朝日が放送した特集をベースとして、生涯学習普及を目指すテレビ局のネットワークである民間放送教育協会の2022年に年1回の番組枠「民教協スペシャル」に選出され、再編集を経て今年、劇場公開に至るという珍しい遍歴の映画である。注目を集めてきた人物が主人公ということもあって横浜市民の関心は高いようで、市内の映画館では公開当初に満席が相次いでいた。
なぜ米国のカジノチェーンは横浜の地を選んだのか、なぜ藤木は反対を決めたのか。横浜市長選で野党が推す候補が当選した背景には何があったのか。本作では、本人や政治家たちへのインタビューを中心として、中央政界と市政の動向、横浜港の歴史などから構成するとともに、作り手は米国へ飛び、カジノ関係者たちの証言も集めて推進側の事情に迫っていく。
冒頭、横浜港の水面から、港湾労働者慰霊碑に向き合う藤木の顔のアップ、そして空撮による横浜港の俯瞰という編集は、この港湾と不可分だった90年間を予告する。横浜大空襲当時の死と隣り合わせだった体験や、終戦直後の青年時代の活動、港運業を起こした父・幸太郎と暴力団との関係も語られ、「ハマのドン」と呼ばれる所以が浮かび上がる。生い立ちの中で築いた人間関係、政治力はやがてIR誘致反対へとつながり、市長選挙で市民運動と共闘し牽引するという、数年前には考えられなかった光景を生み出すに至っていた。
高度成長期の横浜港の歴史を振り返る中で、機械化が進む前の荷役の労働者や、水上生活者たちの姿など、数多くの資料映像が挿入される。とりわけ、水面に艀(はしけ)船が並び、その奥にマリンタワーを望む中村川付近の1960年代のカットは、数多くのテレビドラマや映画が描いてきた、新旧入り混じった高度成長期からバブル期までの横浜の風景を象徴していた。時代が流れ、荷役の現場には巨大なガントリークレーンが導入されて、横浜市役所は高層の新庁舎に移転するなど、風景は更新されていくが、その一方でなお昭和の色が濃く残っている政治の意思決定プロセスも赤裸々に映し出す。IR誘致問題の復習とともに、開港以来、港湾を中心に発展してきた都市横浜の裏面史のふたを開けようと試みているのも特徴である。

地方行政が主題のテレビドキュメンタリーでは、新潟放送の『原発に映る民主主義』(1995)の連作、最近では五百旗頭幸男監督が富山県議会の不正問題を描いたチューリップテレビの『はりぼて』(2020)、石川テレビに移籍後、石川県政の問題を取り上げた『裸のムラ』(2022)といったローカル局発の作品がまず思い浮かぶ。しかし本作では、それらにあった皮肉のこめられた編集や、コミカルなドタバタ劇の要素は控えめであり、ニュース特集の延長線上としてのインタビューによる人物掘り下げが主である。また、横浜港や横浜市役所、桜木町駅前、東横線妙蓮寺駅周辺など市内のさまざまな場所や、地元政界の大物たちも登場するが、一地方の問題に収斂する方向ではなく中央政界との関係が軸である。監督の松原文枝が、東京での政治部記者経験を持った作り手であるがゆえの特徴だろう。松原は映画公開後に刊行した映画と同名の著書『ハマのドン』(集英社新書)においても、政治部経験者の視点から、映画に描かれた以外のエピソードも含めて取材内容をまとめている。
IR誘致反対を明言してからの藤木は、保守主義の現状に対する憂慮の思いと国政批判を語り、誘致を推進する政府側、また同調していた当時の市政と対立する。重要な鍵となっていたのが、長く付き合いがあり後に首相となる菅義偉との関係だった。この、中央=東京と横浜との対決軸の緊張状態は、横浜在住であった評論家・平岡正明(1941〜2009)が著書『横浜的』(1993)に書いた「開港期横浜のエネルギーは強大なものであった。これが、横浜こそ江戸を着磁させる力だったのだ。(中略)あたかも日本の中のもう一つの別の国家である東京の中央集権に烈しく反撥して反東京を檄することは、磁石の、同極は反撥、異極は吸引という作用によるものだ」という宿命を想起させる。IR誘致問題を主要な争点として繰り広げられた横浜市長選挙については、市民たちの地道な活動を基調にしつつも、この中央政界との代理戦争の構図で描いている。8人いた立候補者のうちの3人に絞っていることなど、略式化して整理された印象だ。市内在住だった筆者が当時見てきた混沌模様の感覚とは異なっており、東京からの視点が際立って感じられた。
中央と対峙する人物を描いた作品として、東海テレビの『死刑弁護人』(2012)や『ヤクザと憲法』(2016)といったドキュメンタリーのほうが近いだろうが、本作は主人公のキャラクターの印象の強さが格別である。横浜港運協会会長や横浜エフエム社長を歴任してきた藤木は、地元紙の神奈川新聞に連載した自伝が『ミナトのせがれ』(2004)と題して単行本化され、テレビ神奈川の特別番組や経済番組にも出演するなど、重鎮として数十年にわたってメディアへ頻繁に登場して存在感を示してきた。IR誘致活動が本格化してからは一気に全国区での注目度が高まり、会見や応援演説での「私と菅の喧嘩だ」「顔に大きく泥を塗られた」「俺は命を張っても反対するから」といった発言が全国ニュースで報じられるようになった。それらの場面に加え、本作はさらに膨大なインタビューを行って編み上げており、『ミナトのせがれ』の映像版・続編のようでもあった。重厚な声で、90を超えた齢を感じさせない迫力あるフレーズが次々と登場して流れを牽引する。圧倒的存在感を前に、他の人物は背景と化し、そうそうたる他の政治家たちさえも霞んでしまう。
盟友の亀井静香が、二度にわたって「名月赤城山」の冒頭の一節を口ずさむ場面は象徴的である。赤城の侠客・国定忠治を題材にした東海林太郎の名曲だ。本作で描かれていたのは、米国のカジノチェーンに代表される資本の論理とは対照的な、浅草の木馬亭で演じられる浪曲(浪花節)のような世界であった。反対運動に邁進する原動力は、港湾の先人たちへの畏敬の念、義理と人情である。すなわち本作では、横浜港を舞台に、リリー・フランキーのナレーションが「台詞」であり、藤木のインタビューは「節」として、この浪曲を織り上げていた。

作り手はエピソードを積み重ねながら、例えば読書歴を掘り起こし意外性を探し出して多面的に描こうと試みているものの、その角度は限定されており浪曲的世界を脱するには至っていない。筆者は2000年代初頭の大学在学中、「横浜学」という教養科目の授業で、回替わりの講師で訪れた藤木の講義を聞いたが、語り口は同じで、本作から受ける印象もその時のままであった。話す勢いは常に安定していて弱みがなく、暴力団とのエピソードや半ば勧善懲悪の立志伝に近い物語を通して、人物像はむしろ補強され大きくなり続けていた。物語と映像との葛藤は起こらないため、最後まで藤木本人の意識している範疇に収まっているようであり、「ハマのドン」のイメージを裏切られるところがないのだ。面白さは期待に応えていたとしても、ドキュメンタリーという観点からは物足りなさも感じてしまう。
市長選挙で反対派が推した候補が当選したことで、浪曲であれば華々しく一件落着を迎え拍子木が打たれる段と思いきや、現実には懸案は残っている。新市長を選んだ市民たちが、その後の市政にいかに向き合うかも問われる結果となっているのだ。さらにラストに付け加えられた一節からは続編も予感させられたが、次に描くことがあるとすれば、異なった角度からも人物像を見てみたいと思う。
終盤のスタッフロールには、横浜港の洋上からの空撮、順光に照らし出されたみなとみらい21地区の高層ビル群と、遠くに富士山とを俯瞰でとらえた映像が再び登場する。観光都市、基礎自治体としては最多の人口377万人を有する巨大都市としての要素を凝縮した、真新しく整った横浜の代表的イメージである。本作が浮き彫りにしたのは、このイメージからは想像しがたい、市の中心部に連綿と続く浪曲的世界の存在だ。横浜と東京の二項のみならず、この横浜のイメージと浪曲的世界の対峙もまた、本作の軸であった。(文中敬称略)

【映画情報】
『ハマのドン』
(2023年/日本/DCP/100分)
監督:松原文枝
企画:テレビ朝日
協力:公益財団法人 民間放送教育協会
プロデューサー:江口英明(テレビ朝日) 雪竹弘一(民教協)
ナレーション:リリー・フランキー
製作:テレビ朝日
配給:太秦
公式サイト:hama-don.jp
画像は © テレビ朝日
全国順次公開中!
【著者プロフィール】
細見葉介(ほそみ・ようすけ)
1983年生まれ。会社勤務のかたわらドキュメンタリー映画批評などを執筆。著書に『躍動 横浜の若き表現者たち』(春風社、2019)、『神奈川ニュース映画協会の時代 1950〜2007』(公孫樹舎、2023)。



















