
自宅の庭で 20代始めの筆者
開拓者(フロンティア)たちの肖像
〜中野理惠 すきな映画を仕事にして〜
<前回(第5話)はこちら>
第6話 お金をいただく人生の始まり
1972年、新卒で就職したのは、大手建築会社であった。志望していた新聞社が、その年だけ新卒記者を募集せず、「地元紙はどうか」と伯父が声をかけてくれたのを、「ヤダ」と身の程知らずにも断り、新聞社は諦めて、自分の大学には求人が少ないからと、近くの女子大に通う友人がやってきたので、彼女と一緒に、大学の就職課に通って見つけた職場だった。その友人も同じ会社に就職した。当時、四年制大卒女子を採用する企業は少なくて、教職、公務員、マスコミ、金融機関が辛うじて門戸を開いていたと記憶している。
差別と屈辱を味わった大企業女子準社員の頃
人事部教育課に配属になった。その大企業(今では積極的に女性の登用に取り組んでいる会社として、時々マスコミで紹介される)でのいくつかの出来事は、今でも忘れることはできない。女性は準社員としての採用であり、正社員への登用試験は、男性の準社員にしか開かれていない。準社員の定年は36歳だったと思う。正社員である男性は、社員教育のために、一年間大阪にある会社の寮で暮らすのに対して、準社員である女性は入社前にペン習字の通信教育の資料を受け取り、入社後は、電話の応対訓練を一日受けるだけだった。準社員であることを理由に、女性は正社員である男性の補助的業務であり、給与も当然低い・・・。数え上げればきりがない。大学の求人票でそこまで見破ることなどは不可能だった。毎日のように、<女は男より能力が劣る>とイヤというほど、手を変え品を変え、影に陽に突き付けられる。屈辱と性差別を実感した。つまり、大企業男社会、すなわちこの社会というものを教えてくれたのである。しかしこの僅か1年11か月の体験により、後の人生が決定づけられたのだから、感謝するべきことかもしれない。
働く目的とは
入社直後、確か新入4大卒女子準社員32人だったと思う。全員による座談会が開かれ、入社志望理由を発表する機会があった。「会社に貢献したい」「自分の能力を試したい」などなど、どの人も立派な言葉を口にするではないか。いよいよ私の番になった。「食べるためです」。こんなことを言ったのは私一人だった。バカ正直だったと今では思う。
また、働いている女性の多くは、職場では結婚相手を探すのが目的だと公言してはばからず、周囲もそれを承知していた。女性の幸せは結婚にある、と。感じたのは違和感だったのだろうが、すぐにはそれと言葉にならなかった。どのような環境にも適応できると考えていたからだ。予想もしない毎日だった。待遇について同期入社の女性と一緒に人事課に抗議したところ、ふたりとも、別の部署に配置転換になった。
「オンナのコの異動って滅多にないのよね」
先輩女性に言われた。一緒に抗議した松延みゆきさんは、偶然大学も同じで、20年余り後、地元の神奈川で『ハーヴェイ・ミルク』を自主上映してくれた。

松延みゆきさん(右)と草津旅行したとき(1972年)
働くことの厳しさ
だが、その職場で大きな発見をした。働くことの厳しさ、特に企業や組織の一員として働くことの辛さと厳しさである。当時はサラリーマンを<ドブネズミ色のサラリーマン>と、揶揄するような雰囲気が蔓延していたが、決してそう言ってはならないと心した。
大企業退社
一年半ほど経った頃だろうか、健康状態に変調をきたした。どこが悪いのかわからず病院通いを続けた。秋になったある日、環境が合わないのではないか、と、突然、言葉になり、「会社を辞めるのはどうだろう」と気づき、1年と11か月で大企業を辞めた。退職した途端、病院通いから自由になった。
失業保険を受給しながら、「今度はすきなことを仕事にしよう」と考え、映画の製作会社や映画関係の出版社に仕事を求めて電話を掛けた。当時は映画不況で、製作会社からはまったく相手にされず、ただ一人、「キネマ旬報」の白井佳夫編集長が、電話の相手をしてくれた。
すきな映画を仕事に
「履歴書と、映画について書いたものを送ってください」
それまで映画批評など書いたことがなかったので履歴書だけを送ったところ、ちょうど求人中の外国映画配給会社社長に白井編集長がそれを見せた、というのが映画への道を歩むきっかけとなったのである。失業期間1か月半を経て、映画配給会社に通勤し始めたのは、1974年4月中旬だった。それまで映画配給という業種を全く知らなかった。転職直後の数年間は、驚きと戸惑いの連続であったが、大企業で感じた違和感とは異なり、<水が合う>とすぐに思った。それは今でも続いている。
詩 西脇順三郎
写真を探していたところ、詩集や詩論、詩人の対談集などが出てきた。10代半ばの頃からよく詩を読んでいた。「現代詩手帖」や「ユリイカ」を読むのが、毎月楽しみだった。記憶に残った若手は稲川方人で、繰り返し読んだのは白石かず子、富岡多恵子、吉原幸子、そして西脇順三郎である。
西脇順三郎は高校の現代国語の教科書で知った。「(覆された宝石)のやうな朝 何人か戸口にて誰かとささやく それは神の生誕の日」。行ったことはないが地中海のような明るく乾いた情景なのに、虚無的で、東洋的な雰囲気が漂う。正確ではないだろうが、「僕は脳髄の中で寂しがって歩いているだけだ」「椅子が部屋にあったら日常だが、椅子が崖の上にあったら詩だ」というような文章も記憶から甦る。新鮮だった。
懐かしい本を開くと、なんと、対談集の各所には薄く、鉛筆で線を引いている!・・・数十年後、稲川さんと一緒に十年近く仕事をすることになり、白石さんの著書「愉悦のとき 白石かずこの映画手帖」の発行人に自分がなるとは、当時は想像する由もなかった。
(つづく。次は4月15日の予定です。)
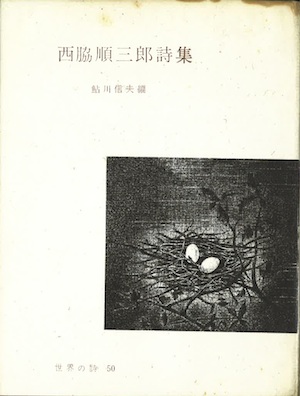 「西脇順三郎詩集」(鮎川信夫編/彌生書房/1967年)
「西脇順三郎詩集」(鮎川信夫編/彌生書房/1967年)
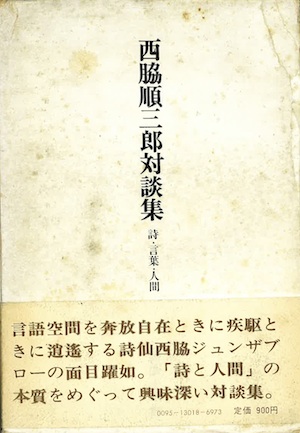 「西脇順三郎対談集」(薔薇十字社/1972年)
「西脇順三郎対談集」(薔薇十字社/1972年)
 「愉悦のとき 白石かずこの映画手帖」(パンドラ/1999年)
「愉悦のとき 白石かずこの映画手帖」(パンドラ/1999年)
【プロフィール】
中野理惠(なかの・りえ)
1950年静岡県出身。1987年に㈱パンドラを設立し、映画・映像の製作・配給、映画とジェンダー関連の出版を業務として現在に至る。早くから視覚障がい者が映画を見る機会をつくることに力を注ぎ、2002年には、日本初の商業劇場での副音声付上映を実現させた。最新プロデュース作品『アイ・コンタクト もう1つのなでしこジャパン ろう者女子サッカー』(10年/中村和彦監督/文部科学省特選)。訳書に『ディア・アメリカ-戦場からの手紙』『アダルト・チルドレンからの出発―アルコール依存症の家族と生きて』など。
![]()


















