
|左、あるいは心臓の搏動を感じる場所
たとえば、「左」ということばを辞書で引いてみる。手もとの新明解国語辞典(第四版)にはこうある。
ひだり【左】⇔右 ①アナログ式時計の文字盤に向かった時に、7時から 11 時までの表示の有る側。〔「明」という漢字の「日」が書かれている側と一致。また、人の背骨の中心線と鼻の先端とを含む平面で空間を2つの部分に分けた時に、大部分の人の場合、心臓の搏動を感じる場所の有る部分〕……
たいへんなことになっている。「左」を定義するために、背骨と鼻の先端を含む平面で空間を2つに分けたうえに、心臓の搏動まで確かめねばならない(しかも、「大部分の人の場合」というおそるべき留保までついている)。
これはことラディカルな語釈で有名な「新解さん」にかぎったことではない。事象や概念を定義することは、ことほどさようにむずかしい。日常に配置されてある自明なものほど、それはますますそうである。「左」という概念を説明するのに、「左」という語を用いてはならない。または対義語である「右」を用いてもならない。
―
連載の第1回だというのに、唐突だっただろうか。
これから月に一度のペースで掲載するこの連載は、「documentary(s):ドキュメンタリーの複数形」という表題のもとに「ドキュメンタリー」の現在のありかたを考える横断的文化時評のこころみである。
ここでわたしがむすぶ約束は、「ドキュメンタリー」という語を用いないということだ(これを仮に「左の法則」と呼ぶことにする)。「ドキュメンタリー」という語は、「左」ほどではないにせよ、「ドラマ」や「フィクション」と同様に日常に配置されていながら、その定義または内実はとてもあいまいである。ここで「ドキュメンタリー」の語のもとで何かを語ってしまうことは、左を「左」と呼び、または「右の反対」と名指してしまうことではないのか。
そうではなく、背骨と鼻の先端を含む平面で空間を2つに分けたうえに、心臓の搏動を確かめること、そして「大部分の人の場合」という危険な留保さえ引き受けること。そうした「左の法則」の遠回りによってしか記述されえないものを、映画やテレビにとどまらない進行形の、そして複数形のドキュメンタリーとして、ここでは書きたいと思っている。
―
|彼女の研究室にスッポンがいるのはなぜか
『ファントム・オブ・パラダイス』(1974/ブライアン・デ・パルマ)のdvdをとても久しぶりにドライブのトレイにおいたのは、①昨年公開された『パッション』(2013)を見てから、デ・パルマ熱がたいへん昂じていたこと、②この冬に起きた、佐村河内守と新垣隆によるゴーストライター騒動にふれてこの映画を思い出さずにはいられなかったこと、のおもに2点だったのだが、思った以上に佐村河内守&新垣隆でおどろいた。
「オペラ座の怪人」Phantom of the Operaから想をえた『ファントム・オブ・パラダイス』は、卓越した作曲の才能をもちながら、ルックスや好機にめぐまれない草食系音楽男子ウィンスロー(ウィリアム・フィンレイ)が、ふとしたことから「デス・レコード」社の悪魔のプロデューサー・スワン(ポール・ウィリアムズ)にまるめこまれてゴーストライター契約をむすび、やがて復讐、破滅にいたる、というあらすじをもっている。
こうしたストーリーラインもさることながら、なによりふたりのルックスにあらためておどろいた。びん底めがねにぼさぼさの頭髪をしたウィリアム・フィンレイの冴えない感じ、対するポール・ウィリアムズは短躯を覆い隠すような金の長髪に色つきめがね、絢爛なスーツをはおってたいへん怪しい。40年後のふたりの日本人に雰囲気がそっくりなのだ。
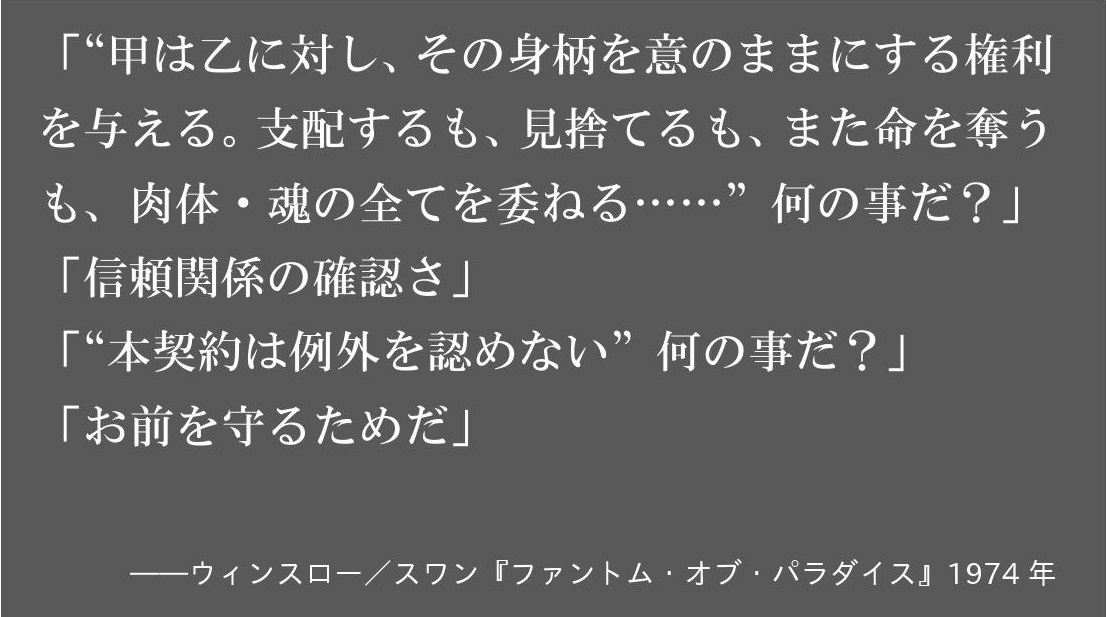
ややあって、テレビにもうひとりの、今度は若い女性があらわれた。理化学研究所所属の細胞生物学者・小保方晴子である。2014年1月にSTAP細胞作製の方法を確立したとして一躍世界的な注目を集めたかと思えば、同年3月から4月にかけて、ひるがえってその研究にねつ造と改ざん、および過失の疑義が呈されて科学界を震撼させた。
わたしは科学に明るくない。現代音楽にも疎い。報道を前にした平均的な視聴者かもしれない。ひとは、これらの騒動をメディアを通じてしか知りえなかった。もちろんそれはこのふたつのケースにかぎったことではなく、複製技術時代の日常的な光景でもある。けれどもなお佐村河内守と小保方晴子のケースがこの連載の興味を惹くのは、彼らがメディアの時代にあらわれた「ファントム」のように思われたからにほかならない。
佐村河内守はなぜ黒を全身にまとい、長髪に髭を生やしサングラスをかけていたのか。小保方晴子はなぜ白衣ではなく割烹着なのか。彼女の研究室はなぜファンシーな色彩に塗りこめられているのか。その研究室ではなぜスッポンが飼育されているのか。そして「佐村河内」や「小保方」などという聞きなれぬ姓で、かれらがあたかも「聖別」されているかのように感じられるのはなぜか?
「映画」なのである。それも、とても出来のわるい。佐村河内守のみならず、マスメディアの裏面でひっそりと作曲家を生きていた新垣隆さえもが、だれも期待していないのに期待どおりの容姿をしていたこと(ウィリアム・フィンレイにほんとうに似ている!)を、わたしは偶然として見逃すことはできなかった。彼らがデ・パルマを参照していたなどといいたいわけではない。しかし、「映画」というものが20世紀を通じて存在しなければ、そして「テレビ」が戦後の60年をおおうことがなければ、彼らがあのようなすがたで画面にあらわれることはなかった、そう思わずにはおれないのである。
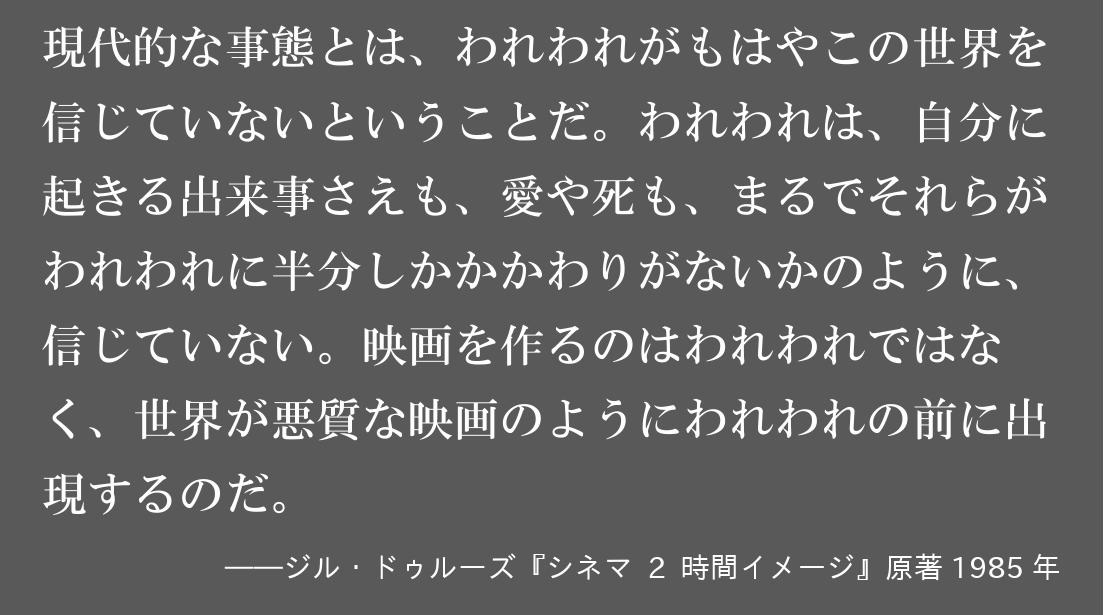
―
|デ・パルマの女たちはなぜあれほどまでにシャワーが好きなのか
ブライアン・デ・パルマは、映画のなかに執拗に映像をとりこんできた映画作家である。彼の作品には、かならずといっていいほど映画やテレビ、監視モニタ等々の画面が登場する。ミケランジェロ・アントニオーニの『欲望』Blow UP(1967)に源泉をえた『ミッドナイトクロス』Blow Out(1981)では、映像と音響の編集が画面内でおこなわれ、『スネーク・アイズ』(1998)ではボクシングのタイトルマッチのライブ中継がそのまま冒頭部に採用される。また『リダクテッド』(2007)ではYouTubeの映像がいくつも画面内で再生されるだろう。『ファントム・オブ・パラダイス』は、そうしたデ・パルマの作品史においても、とびきりのメタ映画(映画についての映画)であるといえる。
みずからの身体が老いてゆくことに耐えられなかったスワンは、あるとき鏡に映った自分にそっくりの悪魔と契約を結び、日常のすべてをカメラで記録することを条件に、永遠の若さを得る。老いることのない彼の本体は「映像」(それは過去のすがたをありありと現在によみがえらせる)なのであり、複数のカメラにおおわれた「パラダイス」という名の劇場は、いわば巨大な映画装置、または「ハリウッド」のメタファーとしてある。スワンが主宰する「デス・レコード」とは、たんにイカしたレーベル名としてあるのではなく、まさに「死の記録」、ないし「死としての記録」を含意していたのではなかったか。
このフィルムが、『カリガリ博士』のメイクと表現主義的な書割り、『市民ケーン』の屋敷のトップショット、『黒い罠』の車載爆弾、『サイコ』のシャワー、といった映画史的記憶を参照しているのは、偉大なる名作へのオマージュというよりは、まさに「パラダイス」が映像を生産し貯蔵するアーカイブであるからにほかならない。そしてここで呼び出された作品たちが、いずれも「語り」と「偽の語り」から成るサスペンスを主題とした「枠物語」であることは、おそらく偶然ではないだろう。
―
テレビが登場して以来、映画はその社会的影響力をその後発のメディアにゆずった。第二次大戦前からテレ・ビジョンの技術はほぼ汎用可能なまでの水準に達していながら、テレビ放送の開始は戦後にゆずられることとなる。この事実が先進諸国において「戦後の国民形成」という政治学をテレビに担わせる契機になったことは、吉見俊哉や水島久光らの多くの研究が指摘している。そうして社会と「鏡像関係」をむすんだテレビは、受像機に社会を映し出し、同時に社会(とそこに属する個人)はテレビによって「作られて」いった。
周知のとおり、日本や合衆国をはじめとする先進諸国の映画産業は、まさにテレビが爆発的に普及する60年代から翳りをみせ始めた。けれども、映画は「テレビではない」かぎりにおいて、テレビ(とテレビ化する社会)に対するある批評的な距離をもつことができた。そして、その系列のもっとも先鋭な作家として、ジャン=リュック・ゴダールとブライアン・デ・パルマが存在している(もうひとりあげるなら、『エドtv』と『フロスト×ニクソン』のロン・ハワードだろうか)。
ゴダールとデ・パルマの映画に頻出する「映像のなかの映像」=「枠映像」は、メディア化した社会を危機的に反映する。そしてゴダールがそれを「et(and)」をめぐる2語の併置(「ベトナムとフランス」「こことよそ」「ショットとリバースショット」……)、つまりは差異を思考するために用いるのに対し、デ・パルマはそれを「サスペンス」の装置とする。
『パッション』ではまさに、偽りの映像を見せられていた観客自身がノオミ・ラパスのアリバイを証言する立場におかれるのであり、デ・パルマにおける「枠映像」は、そこに映されているものが「ほんとう」かどうかを何重にも宙吊りにする(彼が好んで使用する「スプリット・スクリーン」(分割映像)もまた、「枠映像」の一種としてとらえなければならない)。デ・パルマ的サスペンスが提出する不安は、つまり映像の時代の不安なのであり、『ファントム・オブ・パラダイス』をはじめとする彼のいくつもの映画は、映像への「信頼」と「破滅」のはざまに引き延ばされた時間として存在している。


















