野球の本といえば近藤唯之、の時代があった
つまり、本盤は、戦後プロ野球史上に残る名勝負や大記録達成を集成しつつ、より、一球が明暗を分ける綾に拘っている。それを現したナレーションは、近藤唯之の筆による。さらに俳優・西沢利明(声優としてもおなじみでしたね)がゆっくり、意味を咀嚼するように読んでいて、聴き応えのあるレコードになっている。
「男の運命ほど、不思議なものはない。それは男と男の、出会いといってもいい。
あの時、あの場面で、あの人に出会っていなければ、果たして今の私はあったろうか。そういう思いにとらわれている人は、ずいぶん多いと思う。
だが、この思いはサラリーマンだけのものではない。プロ野球の選手だって同じなのである。もしこの試合のこの場面で、この相手と勝負し、この一球が無かったら、自分は果たしてプロ野球選手として生きて行けたかどうか。
思えば男の人生とは、まさにこの一球に懸っているとも言える」
(金田正一、現役引退間際に通算400勝達成。その実況があった後)
「楽に稼いだのではない。息も絶え絶えに、死に物狂いでもぎとった400勝であった。もし金田が、享栄商業を中退して国鉄のユニフォームを着た昭和25年、8勝を稼いでいなかったら、400勝は絶望だったと思う。(中略)卒業式を棒に振り、三年生途中でユニフォームを着たことが、金田を400勝の栄光に押し上げたと言っていい。
だからこそ彼の胸に、幻の卒業式は生涯付いて回るのかもしれない。金田の持ち歌は命のある限り、仰げば尊し我が師の恩、であろう」
リズムのある独特の言い回しが、起こしていても楽しい。封入された自身のライナーノートも「野球はスポーツではない。人生だ、運命そのものだ」と、自著の言い回し全面展開。
近藤唯之は、かつてスポーツ・マスコミの世界で一世を風靡したプロ野球記者。沢木耕太郎や山際淳司の前を走っていた男、と言っていい。本盤が出た当時は、夕刊フジの連載にフジテレビのキャスターと売れに売れていた頃だ。『近藤唯之がつづる』と、わざわざタイトルに銘打つだけのバリューと魅力があった。
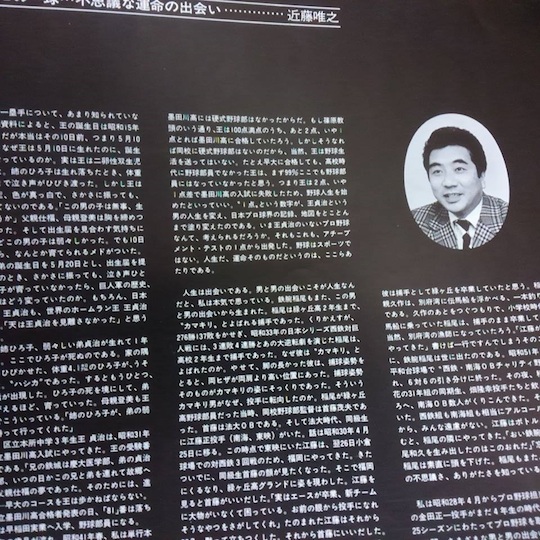
多少、この書き手には思い入れがある。
1990年代半ば、20代の僕が最初にありついた定期的な仕事は、プロ野球関連のビデオソフトのリサーチや台本だった。野球マニアだからつとまったのではない。やる前の知識量はホント、人並み。僕らが子どもの頃は、大抵の男子は12球団の主要選手をスラスラ言えた。ポケモンみたいなものだ。それでも「詳しい?」と聞かれて「ええ、まあ」と即答しないことには、他に働く口が無かった。翌日から、東京ドームの地下にある野球殿堂博物館の図書室に通い、無理くり何とかした。
そんな時によく読んだのが、定期的に新潮文庫から出ていた近藤唯之なのだ。
「野球は記録のスポーツ」と称される。ちゃんとした記事であるほど、日付、得点、勝敗数、順位、打率、対戦成績、年度成績、通算成績……と数字が頻発する。僕ものたうちまわったから多少分かるが、筆力がなければ、面白く読んでもらうのは実はかなり難しいジャンルだ。
近藤唯之のプロ野球本は、そこが上手い。試合や選手の解説に、人間くさいエピソードを必ず織り込む。天国と地獄の境目はこの一球にあり、そこに悲喜こもごものドラマが生まれる、という語り口を確立していた。読みやすく、頭に叩き込みやすいので、ずいぶん助けられた。
データマンとしては、僕は割と優秀なほうだったとは思う。数年後には、スポーツ番組の知らないスタッフから「古いフィルムで背番号も映らず、選手の名前が特定できない」と電話が来ても、「○年○月○日の試合でロッテのピッチャーなら、成田文男です」と即答できる位にはなった。
どのジャンルでも、メシのタネはこれのみと追い詰められたら、誰だって、僕ですら、ものしり博士になれる。しかしそれを面白く書けなければ何の意味も無い。そう思っていたから、知識量は特に自慢でもなかった。そういう片意地も、近藤本に影響されていたのかも。
「プロ野球選手もサラリーマン」から「アスリート」への変化
今は、すっかりプロ野球から遠ざかった。昨季のMVP、ヤクルト山田とソフトバンク柳田の、それぞれのトリプル3の内訳も分からない。当時買い込んだ野球関連図書は、かなり処分した。
近藤本ももうほとんど部屋には無いと思っていたが、本盤を聴いたのをきっかけに探してみると、先の『Number 237』と一緒に、数冊出てきた。『プロ野球監督列伝』(1984)に『プロ野球 優勝その陰のドラマ』(1989)……。なつかしい。お世話になりました。

そんな思いが、ケタ違いに強いライターさんがいた。『小説すばる』2014年7月号(集英社)に掲載されたノンフィクション、「君は、近藤唯之を知っているか」を書いた村瀬秀信だ。
「君は~」は、プロ野球の世界に組織人の悲哀を重ねて大人気を博した近藤の、その記者人生を調査した評伝。新人記者時代から、ホームランを打った打者ではなく、打たれ、うなだれてベンチに下がる投手に取材の目を付けた。擦り切れるほど愛読したのは司馬遼太郎。こういった記述に、そうか、これが近藤本のエッセンスか、と何度も膝を叩いた。
しかもこの村瀬さん、かなりキレるユーモアの持ち主らしく、一文まるごと〈近藤節〉の文体模写で押し通すという、分かる人には分かる、相当面白い試みをしている。
近藤得意のフレーズ、「うなる思い」「うなるような思い」は要所要所で計4回出てくる。「男の人生」「男の運命」は、合わせて14回。パロディとして見事だし、同時に、「男の人生なんて」としつこく繰り返してエレジーを生み出してきた、近藤の型への献心がある。もし〈近藤節〉を知らない読者が(なんか、今どきだと垢抜けなく感じるけど、血の通った文章だな……)と思いながら読んでくれたら、それが何よりの再評価だと願っている節がある。
ただ、プロ野球選手の日々の勝負やトレード、チーム内の確執、引退といったドラマから、サラリーマン社会の共感を引き寄せていく近藤のスタイルは、90年代にはもう、古くはなっていた。玉木正之のように、割とハッキリ批判の対象にする書き手もいたと記憶する。
ビデオ発売元である出版社の人に「近藤唯之の本を参考にするのはいいけど、引用はやめてくれよ」と、釘を刺されたこともある。本当に裏を取って書いているのか、分からないところがあると。
例えばさっき起こしたナレーション。カネやんが「仰げば尊し」を愛唱する話は、近藤が本でも好んで書いてあるネタだが、いつどこの取材で得た情報かとなると、確かにハッキリしない。
高校を中退してプロ入りした男の雑草魂を謳うための、道具立てとしてはよく出来ている。でも、その面白さはノンフィクションではなく、ものがたりだから。
近藤本が、だんだん昭和エピソードのネタが被るようになり、新潮文庫からPHP文庫に移る頃、僕も自然と「出たら買う」状態から離れた。同時期に、鮮やかに始まったのが、朝日新聞スポーツ欄のコラム「EYE 西村欣也」。スポーツ選手の多くは組織に所属するが、その前にひとりのアスリートである、と据えた視点が、大リーグ挑戦の時代の始まりと呼応していた。
その西村さんも定年で、今年の春で連載は終了。平成すら遠くなりにけり。



















