横井庄一という人間の、フワフワとした逞しさ
特に強烈だったのは、前述した戦友の証言の通り、横井さんが現地の村には一切近づかず畑や作物を荒らさなかった、その理由。山狩りを避ける用心のためだが、さらには「半分以上も野生化した人間が、それでも人間なんだという何かを必死で求める気持ち」だったから、というのだ。同じ理由で、小鳥を餌付けして飼ったりしている。
横井さんは、食料の分け前などでエゴを剥き出しにした者ほど先に斃れるのを見ている。自分より年の若い者でも自棄になれば、台風に打たれた後でめっきり身体を弱くするのを見ている。野生動物のほうが寿命は短い摂理を、本能で学び取っている。
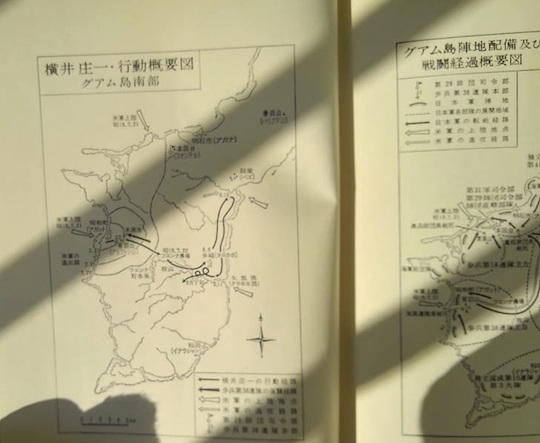
唐突な話になるが、〈性善説と性悪説、どっちが正しいか〉なんて議論、学生時代によくやりませんでしたか。僕は一貫して性善説で、人間の本質は悪だとするシニカルな認識にはいつも負けていた。負けていたんだけど、いつも承服しかねるものが残った。
だから横井さんの本に、いや、ジャングルでの生存に、その答えを見つけられた気がした。
ひたすら生き延びる。それだけの目的が、村人のものを卵一つも盗まず、小鳥の飼育を選択させたと綴る報告には、社会的動物の生存戦略の観点から性善説を裏打ちできる強さがあるのだ。
しかし、そこまで考えると、ハタと行き詰る。
横井さんが超人的なほどにリアリズムなサバイバル術を心身に携えていたとして、ではなぜ20数年も「生きて虜囚の辱を受けず」の洗脳が解けなかったのか?
山狩りの危険の裏をかき、後で現地の人も驚くほど村の近くに住居を作っていたのだから、もう投降しても大丈夫だと、それこそ本能で察することができなかったのか?
こうした疑問に戻ってしまうのだ。理屈で考えれば、矛盾が出てくる。
国立第一病院に入院した横井さんは、4月25日、退院して名古屋へ帰った。この時かなりの野次馬が集まったらしく、「激動の記録1972年」はその騒ぎと、見物に来た女性達のインタビューまで収録している。
見物人A「ここに横井さん来はった言うたからね、一目見よう思うて。元気そうでねー。ほんま健康そうでな」
見物人B「良かった、アハ」
見物人A「おじいさん。優しいおじいちゃんみたい。なんか雑誌で見たらもうねえ、弱りきった感じやったけどもねえ。なんか、英雄になってねえ」
見物人B「うらやましいわ」
見物人A「「ウチらもグアム島に行って……(F.O.)」
うーむ。これぞミーハー。前後の文脈をぶったぎり、残留日本兵さえタレント扱いするハッピーな鈍感さ。
わざわざこんなものを付け足したレコード制作スタッフに、軽佻浮薄な現代人と横井さんを対比させたい、辛い意図があったのは明らかなのだが。今聴くと一周回って、あれ、これが日本人の強みかも……と唸ってしまう奇妙な感慨がある。これ位フワフワしてるから、敗戦国の国民なのに狂わずに済んでいるというか。
というのも、元気を取り戻した横井さんも、今度は都会のコンクリート・ジャングルにすぐさま順応し、実際にタレント活動を始めるからだ。僕の世代は子どもの頃、サバイバル評論家のような肩書で飄々とテレビに出ていた横井さんを、なんとなく覚えている。
ひょっとしたら、現代日本のフワフワ加減に耐え切れず、大日本帝国に殉ずるように愛国的活動のひととなった小野田さんのほうが美しく、しかしセンが細かった。そう言ってしまうことも出来るのだ。
横井さんって結局、何者だったんだろう。やはり、それはそれとして……なのか。
横井庄一の人生を通して僕らが見たのは、観念と現実を別に置きながら、目の前の理不尽な状況が変わってもその都度適応する(できる/できてしまう)、日本人らしさそのものだったのかもしれない。
※盤情報
「ああ最後の日本兵 横井庄一さん」
週刊サンケイ臨時増刊2月26日号「横井庄一伍長の詳細全記録」特別付録
1972
サンケイ新聞社出版局
雑誌特価200円(当時の価格)

若木康輔(わかきこうすけ)
1968年北海道生まれ。フリーランスの番組・ビデオの構成作家、ライター。
ちょっと不謹慎かもな感想を。横井さんの手記『明日への道』には『ロビンソン・クルーソー』や『十五少年漂流記』と通じる一種の冒険物語の面白さがあり、ふだんの生活でも影響を受けました。野菜くずでも調理する、空き容器を捨てずに別の入れ物に活かす……そんな程度ですが、コンビニで割高なものを買う率はめっきり減りました。
また、書き終わってから、『俘虜記』『野火』の大岡昇平が「捕虜の経験があるから」と日本芸術院会員を辞退したのを思い出し、これはけっこうズシーンときた。遠回しの皮肉だったとも、フィリピンで死んだ戦友への思いがあったとも言われているエピソードです。



















