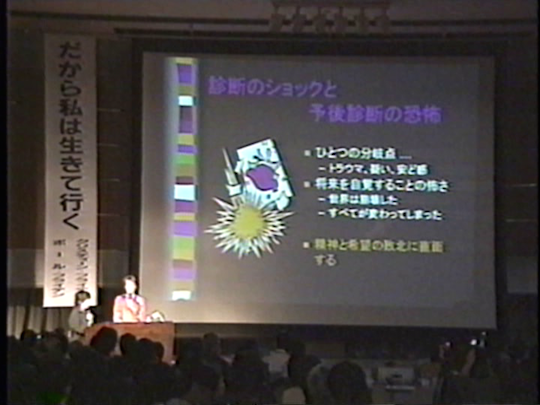
クリスティーンは、自分に投げかけられた質問の一つ一つに、時折ポールの助けを借りながら答えていった。
例えば、5つめの質問。母が自分の顔が分からなくなっても、ほほえんでいて欲しいという考えについてどう思うか。
おそらく質問者は、「笑顔」を心のよりどころにしているが、本当にそれでいいのか、母は幸せなのか、自分の自己満足にすぎないのではないかという不安をかかえているのだろう。クリスティーンに認知症の人を代表して、「それでいいと思いますよ」とお墨付きを与えてほしかったのだろう。だが、それ以上の何を言い得るだろう・・・。
まずポールがひとこと答えた。
「人は愛を与えたり受け取ったりする時にほほえむのだと、私は思います。」
そして、クリスティーンが続けた。
「どうかお母さんに笑顔と愛を送り続けてあげてください。愛を通して私たちはこの世に生を受け、赤ん坊も愛と笑顔に反応します。私は、認知症で他のすべてのものを失っても、愛は最後まで感じることが出来ると信じています。」
私はうなった。
これは「笑顔」や「愛」について、ありがちなきれいごとを、気休めや気分で言っているのではない。46歳で認知症と診断され、娘たちの顔すら分からなくなっても自分は自分と言えるだろうかという問いを自らにつきつけ考え続けた彼女が、「信じたい」と願い、「信じられる」と思った、極めて現実的な、あり得るべき最小限の希望だったろう。おそらくポールとも何度も話し合ったに違いなかった。
多くの人が深くうなずき、笑顔になり、クリスティーンに魅了された。
まさに外側から殻をつき破る、ひと突きだった。
こうした語り合いによって、「認知症の人が語る時代」が幕を開けた。
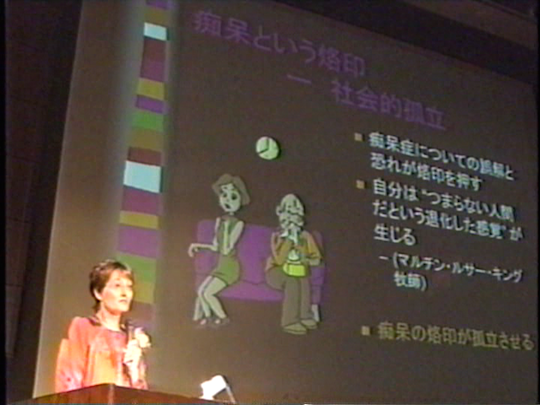
計2回の講演でクリスティーンは何を語ったのか。
講演のタイトルは、それぞれ、岡山「内側から見た認知症 認知症になるとはどのようなことで、私たちを支えるためにあなたは何を出来るのか」、松江「『当事者』にとっての認知症診断 無駄にする時間はない」。
認知症と診断されて8年間の経験が、自分にとって何だったのか、そこからつかみ取ったものを、凝縮して伝えようとしていた。
11月1日に岡山で行った最初の講演の語り始めは、こうだ。
「今日これからお話しするのは、内側から見た認知症についてです。私の経験や友人たちの経験を交えつつ、この病気と生きる私たちの旅はどのようなものかを話したいと思います。」
「この講演では、認知症の私たちが生きることになった新しい世界はどのようなものか、そして私たちが後にした世界にいるみなさんは、日常生活で困難がふえていく私たちにどうかかわればよいかを、具体的に説明したいと思います。」
クリスティーンは、「旅」と言い、「新しい世界」と言う。それまで私たちがなじんできた、「認知症=人生の終わり」という見方に真正面から反対する言葉だ。診断の後にも旅が続いているというのだ。
講演時間は1時間半。クリスティーンが英語の原稿を段落ごとに区切って、ゆっくりと読み上げ、その後で同じくらいの時間をかけて、通訳が日本語に訳す。クリスティーンは原稿を読む時、顔や声に豊かな表情があるので、英語が分からなくても、日本語に訳されたスライドを見ながら、彼女の声に耳を傾けていると、何か伝わってくるものがある。その後で、日本語訳を聞いて、そういうことかと腑に落ちる。内容については後で述べるが、誰も以前に聞いたことのない話だったからか、聴衆の緊張が途切れることはなかった。
旅の始まりは、「絶望」だった。
彼女は、まず認知症を告知された診察室の場面を、「95歳の人のようだ」と言われるほどに萎縮した脳の画像を示しながら描写する。
「私は標準的な認知症のシナリオを伝えられました。『あなたは5年で完全に呆けてしまい、それから3年後には介護状態になって死ぬだろう』というものです。これではスローモーションで過ごすホスピスと同じです。」
「私がもっとも怖れていたのは、認知症の後期になって、自分のことも家族や友人のことも、――おそらく神さえも、わからなくなったときのことでした。」
それは、「アイデンティティの危機」に他ならなかった。
▼Page3に続く


















