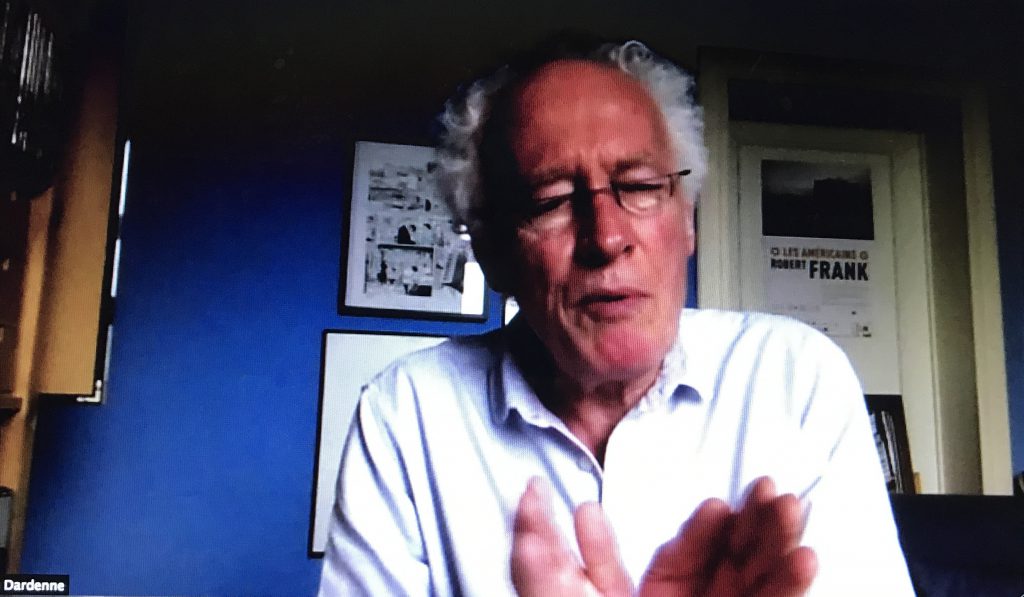
ジャン=ピエール氏
世界的な映画の巨匠として知られるジャン=ピエール・ダルデンヌと、リュック・ダルデンヌの兄弟だが、もとはドキュメンタリー畑の出身であることはあまり知られていない。1970年代半ばからベルギーのブリュッセルを拠点に、労働者の団地における都市計画の問題、レジスタンス活動、ゼネスト、ポーランド移民をテーマにした社会派のドキュメンタリー映画を撮りつづけた。1996年に発表した『イゴールの約束』と1999年の『ロゼッタ』で世界的な評価をかため、その後は、手持ちカメラと長まわしを特徴とするスタイルの劇映画を発表しつづけている。
新作『その手に触れるまで』(19)は、ベルギーに暮らす13歳のムスリムの少年が、イスラムの指導者に感化されて、過激な思想に染まっていく姿を描いている。新型コロナ・ウィルス流行の影響で来日は果たせなかったが、オンライン会議のシステムで、自宅ににいるダルデンヌ兄弟に単独インタビューを試みた。申し合わせたかのように、交互に質問に流暢に答えてくださった2人は、映画の巨匠というよりも、書棚に囲まれた机に座るヨーロッパの知識人という風情であった。
(構成・写真=金子遊)
イスラム急進派の少年を描く
——ベルギーに多くのムスリム系の住民がいることは、日本ではあまり知られていませんでした。ですが、2016年のブリュッセルの空港や駅の爆破事件を経て、わたしたちもそのことを認識するようになりました。今回の『その手に触れるまで』という作品で、狂信的なムスリムの13歳の少年アメッドを主人公にしたストーリーは、どのように生まれてきたのでしょうか。
リュック あなたがおっしゃるように、2015年から16年にかけてフランスやベルギーで大規模なテロ事件が起きました。それは、わたしたちが住んでいるブリュッセルで起きたことでした。そのときに受けた衝撃があと押しをして、この映画を撮ろうと思いたちました。しかし、ヨーロッパに居住しているムスリムの若者たちの一部が、どうしてイスラムの教義において急進化していくのかという問題をあつかった映画は、ほかにもたくさんありました。そこでわたしたちは、イスラムという宗教を真摯に受け止めた映画をつくりたいと考えたのです。
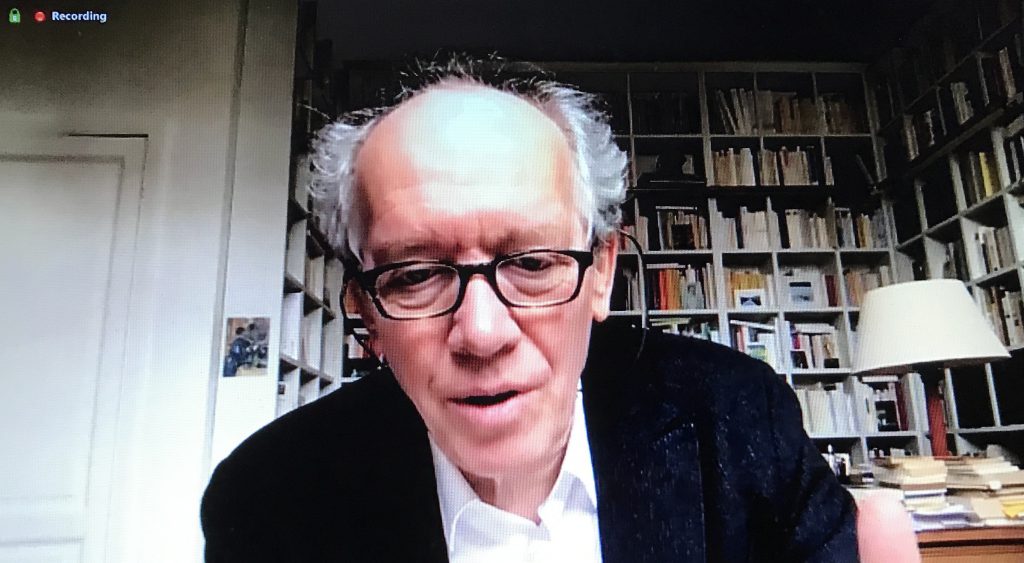
リュック氏
「狂信とは何か」をこの映画のなかで描くために、他の映画とはちがって、すでに狂信化してしまっているアメッドという少年を主人公に据えました。狂信化した状態から、この少年が本当の人生を取りもどすことが、どれだけ難しいのか。そのような状態から脱急進化させることがどれだけ難しいかを描いています。彼にとっては、イスラムの急進的な思想における、「イスラム教徒としての純潔」ということしか頭にないわけです。ですから、自分から見て「正しいイスラム教徒」の像から外れる人たちは、みな不浄で汚らわしい存在だと見なしてしまう。それで、彼(女)たちを触ることもしないのです。純潔さをまっしぐらに求めるあまり、不浄だと判断した人たちを殺すということも辞さない。そうしたふつうの人間の常識から外れた考えを、正義だと思って突っ走っていくのです。
はたして、一度急進化してしまった少年をもとの人生にもどすことができるのか。それは、わたしたちにとっても、この映画をつくる上で「賭け」でありました。ご覧になって頂いたとおり、他にもさまざまな脇役の人物たちが登場し、アメッドのことを助けようとします。狂信的な状態から抜けださせようとしますが、ことごとく失敗します。そして、最後にでてくる家の二階から転落するできごとによって、イスラム指導者との関係が変わります。おそらくそのできごとによって、何かが彼の内側で変化したのではないかと思います。その証拠に、アメッドは転落したあとで母親の名前を呼びます。生の世界に生きている母の名を呼ぶのであって、決してイマーム(指導者)やアッラー(神)の名前を呼んだわけではない。こうして、彼はもとの生活にもどることができるのです。

——ダルデンヌ兄弟の映画の主人公の多くが、少年や少女ですね。通常の映画づくりではオーディションをし、リハーサルを重ね、本番を撮るものですが、あなたたちは特にリハーサルに時間をかけるそうですね。『その手に触れるまで』に出演したアメッドを演じるイディル・ベン・アディや、ほかの人物をどのようにリハーサルし、演出したのかお話し頂けないでしょうか。
ジャン=ピエール いまご質問してくださったなかに、わたしたちの答えはあります。わたしたちは長い時間をかけて、リハーサルを重ねていくんです。撮影の前にキャストを集めて、90日ほどかけてそれを行います。そこに集まるのは、わたしとリュック、それに俳優たちだけです。そのときに、小さなヴィデオカメラを持ってテスト撮影をするわけですが、本番になっても舞台装置や美術は同じものを使います。ロケーションで決められた実際に本番を撮影する場所で、そのリハーサルをおこないます。リハーサルをしている間に、たとえば、立ち位置を変えたほうがいいとか、歩きかたはこうだとか、美術を変えたほうがいいとか、段々と「かたち」ができてくるのです。
そして、俳優たちも自分がもっている恐怖感というものを、そのなかで捨てることができ、カメラの前で自然に演技ができるようになります。これはアメッド役のイディルだけに限ったことではありません。わたしたちの映画に出演するすべての俳優たちが、リハーサルをしているときに、体の動きをとおして自分が演じる役を見つけ、その人物になることできます。イディルが演じたアメッドという少年に関していえば、ムスリムにとっての祈りや禊の行為、そして農場のシーンをリハーサルのなかで実際にやってみることによって、そこで動作をくり返すことによって、彼は自分の役柄に出会っていきました。何度もくり返しおこなうからといって、そこから新鮮さが失われることはありません。
ダルデンヌ兄弟の映画術
——『その手に触れるまで』という映画をリハーサルし、実際に撮影し、そのあとで編集作業を進めていったなかで、監督たちの印象に残っているシーンはどこでしょうか。
リュック そうですね、わたし自身、このシーンが撮れてうれしかったところがありますね。もしかしたら、これはわたしたちにとって初めての経験だったのかもしれません。それはアメッドが少年院に送られたあとで、更生プログラムのひとつである農場作業をおこなうシーンで起きました。アメッドは農場主の娘である、同じような年ごろのルイーズという女の子と知り合います。しばらくあとになって、アメッドとルイーズが田舎の農場で、ふたり並んでいる場面があります。ルイーズは1本の草を摘んできて、アメッドの頬をくすぐったりします。そしてアメッドの眼鏡を外して自分にかけてみたり、そして「キスをして」といったりします。この場面での2人の少年少女の俳優が、とてもすばらしかったですね。そしてまた、すばらしい偶然のいたずらが色をそえています。それは、この場面の撮影中に起きた風のことです。その風によってルイーズの髪がさらわれ、また、そこにある草を揺り動かしているのです。フレーム内にあるものが、とても繊細な動きをしています。これが映画を撮るということの醍醐味なんですね。
『その手に触れるまで』という作品では、この場面にいたるまで、あくまでもイスラムの急進的な方向に硬直化してしまったアメッドという少年の姿をずっと追っていました。イスラムの聖戦で命を落としたいとこを崇拝し、聖典のコーランに夢中になっている凝りかたまった少年です。そのような硬直した場面がつづくなかで、アメッドとルイーズの繊細な場面が現れるのです。ここはうまくいったと思い、わたし自身も満足しています。固定カメラで撮影していますが、眼鏡とか飲み物とか草の茎といった小道具を使い、ふたりが見つめ合ったり眼をそらしたり、些細な動作が起きるなかで、アメッドは自身の性的な欲求を発見することになります。こうした小さなできごとが積み重なっていき、最終的に彼は自分の人生にもどることができるようになったのかもしれません。ただし、この映画のなかでは、狂信が愛よりも強いものとして描かれているのですが。

——ダルデンヌ兄弟のカメラワークや撮影のスタイルは、手持ち、長まわし、広角レンズ、登場人物の至近距離などが特徴です。あなた方のカメラワークと演出のリズムはどのようなものだとお考えですか。
ジャン=リュック あなたは広角レンズといいますが、わたしたちは40ミリくらいのレンズを好んで使っています。人間の視界より若干せまいくらいのレンズですね。『イゴールの約束』という映画からすでに、俳優とカメラのあいだに技術的で人為的なものを入れないように心がけてきました。観客がそこに直接的ものを感じとれるように、と。そのことによって、観客が映画のなかにでてくる人物に共感をもつことが、容易になるのです。たとえば、わたしたちが前もって準備し、これから撮影しようとしている事柄が、あたかもわたしたちにも次に何が起こるのかわからないかのようにして、わたしたちも驚きながら映像を撮ろうとしてきたのだといえます。わたしたちの映画を観て、イタリアの映画監督であるナンニ・モレッティがこんなことを教えてくれました。それは、イタリアの劇作家であるエドゥアルド・デ・フィリポの格言です。すなわち「スタイルを求めれば死が見つかり、人生を求めるとスタイルが見つかる」のだと。

【映画情報】
『その手に触れるまで』
(2019年/ベルギー・フランス合作/カラー/84分)
監督:ジャン=ピエール・ダルデンヌ、リュック・ダルデンヌ
出演:イディル・ベン・アディ、オリビエ・ボノー、ミリエム・アケディウ、ビクトリア・ブルックほか
原題:Le Jeune Ahmed
配給:ビターズ・エンド
公式サイト http://www.bitters.co.jp/sonoteni/
6/12(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショー!
※場面写真は© Les Films Du Fleuve – Archipel 35 – France 2 Cinéma – Proximus – RTBF



















