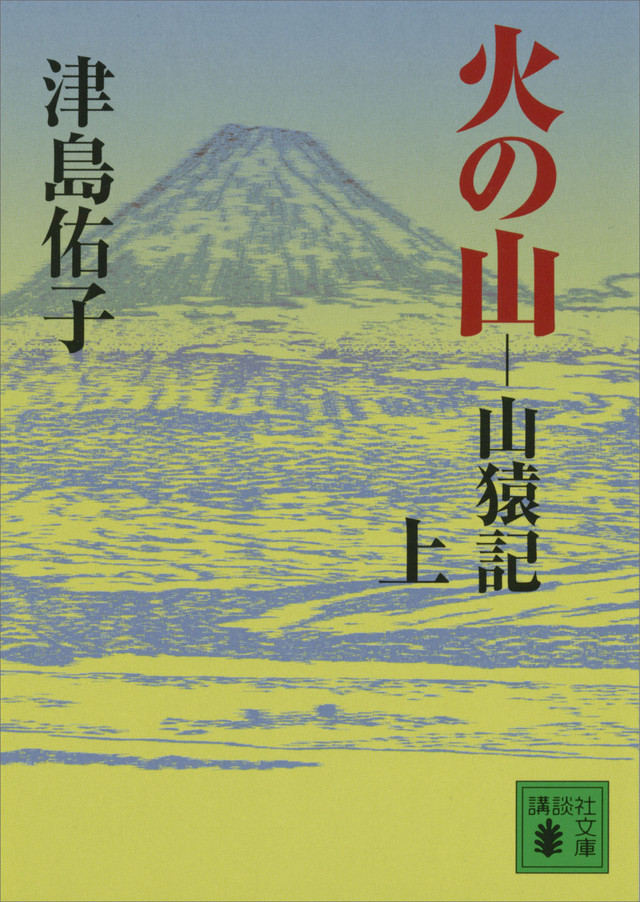
これは作中の登場人物が書いた記録である、と宣言される小説がある。そこでは、かれらの生涯の一時期や、目撃あるいは参加した出来事が語られ、その形式は、渦中で記した日記やノートを基に構成されるか、あるいは後年の記憶を基に語られることが主であろう。とくに後者の場合は語り手の記憶から再構築されるがゆえに、語り手である「わたし」の視点から回想されたさいには、事実を語っていても、語り手の主観や先入観、誇張や願望が含まれ、またそこに欠落があるのも当然だろう。ましてやそれは小説なのだ。と顧みれば、回想録と呼ばれるものは、ほとんど小説なのだろうか。
話は逸れたが、小説において作中人物が書いた記録と明記する場合があるのはなぜかということの一端を、津島佑子の『火の山―山猿記』(以下、『火の山』)(*1)から考えてみたい。
有森勇太郎という作中人物が書いた「記録」が大半を占める『火の山』においては、小説を読む行為が同時に記録を読む行為となる側面をもっている。その勇太郎の「記録」を時系列で考えれば、有森家に代々伝わる言い伝えにはじまり、祖父母が結婚した明治元年から、勇太郎と妻の広子が結婚してアメリカへ渡る昭和二六年までの有森家のメモワールであり、そこに勇太郎の父・源一郎の富士山に関する文章が時折挟みこまれている。(引用資料には、津島の祖父である地質学者・石原初太郎の富士山に関する著作も含まれている)。
七〇を過ぎた勇太郎は帰化したアメリカを拠点に生活しており、姪の由紀子からの「昔の話を聞かせてほしい」という突然の手紙によって、有森家の「記録」を書きはじめるが、アメリカの家には有森家についての資料が乏しく、記憶と、記憶のなかでよみがえる両親や兄姉の声、わずかな手紙を頼りにせざるをえなかった。そうして書き上げられた「記録」は、勇太郎から由紀子へ手渡される。「記録」には「由紀子のために、牧子のために」と書かれてあった。牧子とは勇太郎の娘であり、アメリカで育ち、フランスで暮らすという環境下で日本語を学ぶという選択をしてこなかった。勇太郎もまた牧子との会話は英語で行なってきた。つまり、「牧子のために」と付されたこの「記録」が日本語で書かれているいじょう、牧子がこれを読むには、日本語を学ぶか、あるいは由紀子が翻訳する必要があった。しかし由紀子は「記録」を手渡された数年後に、余命わずかの病にかかる。そこで由紀子は牧子の息子である二歳のパトリス・勇平(以下、パトリス)の未来へ託すため、「記録」をパリの牧子へ送った。
その際に由紀子は「記録」の最初の読者としての追記を加え、手元にあった母であり勇太郎の三番目の姉である笛子の日記と、勇太郎の五番目の姉である桜子のノートを「記録」に綴じ入れた。さらに未来のパトリスへの手紙と、有森家の郷里である甲府、富士山、南アルプス、有森家の墓のようすを記した添え書きも添えて送っている。
そして二〇年あまり後に、由紀子が再構成した「記録」を発見したパトリスの手でまた注釈と追記が加えられる。長くなったが、いじょうが『火の山』を構成する要素の九割以上を占める「書かれた」部分である。ところが『火の山』にはもうひとつ、パリのなかで、あるいはパリと日本で交わされる電話と推測される一人語りの要素も含まれており、そこには勇太郎の「記録」がパリで紐解かれていく時間が流れている。『火の山』の読者は、「記録」を読みすすめていくなかで、このパリの時間にいくども立ち戻される。そこには作者である津島が作中のなかであえて「記録」とした意味があるのではないか、とまずは仮定してみていきたい。
冒頭のパトリスによる一人語りのなかで、由紀子から送られてきた昔の「記録」をパトリスが手にしたことが知らされる。電話の相手は日本人の友人であり、いくら日本語を学んでいるとはいえ、大正生まれの勇太郎の手書きの文章はパトリスの手に負えず、日本人の友人を介してパリ在住のクニコに一緒に読んでくれるように依頼する。クニコはパトリスの母・牧子とおなじ世代であり、次のように提案する。
「わたしがまず、日本語の文章をそのまま読みあげて、パトリスにもわかりやすいように、必要な部分は説明をおぎなっていくということでいいかしら」
クニコとパトリスがどのようにして「記録」を読み、紐解いていったのか、その場面が具体的に描かれることはないが、作中の「記録」には、パトリスによる注釈が記されている。たとえば「おとう(父――P)」というようなかたちで。パトリスの最終的な目標は、日本語の読めない母・牧子のために「記録」をフランス語に翻訳することであり、そのために補ったと考えられるが、一緒に読むクニコに教わったと想像すれば、クニコが日本語で読み上げた文章を、パトリスにわかるようにフランス語と日本語で解説する光景が浮かび上がる。文庫本で一二〇〇頁を超える『火の山』には、その大半を占める「記録」が読み上げられ、解説されるという行為と、それに伴う膨大な時間もまた含まれており、読者はパリの時間に立ち戻らされるたびにそれを意識させられる。
見方を変えれば、由紀子が再構成した「記録」の最初の読者であるクニコの解釈がある程度はパトリスが「記録」を読むことへ影響を与えているとも考えられるが、作中後半には、パトリスの手による長めの注釈のなかで、勇太郎の妻・広子にも由紀子から「記録」のコピーが送られていたことが明かされる。
「おじいさんがまだ日本にいたころの話はおばあさんからぼくの母もトシオおじさんもいろいろ聞いているけれど、それがおじいさんのメモワールから知った話だったか、おじいさんから直接に聞いた話だったか、わからなくなっている—P」
作中では由紀子から広子へ送られた「記録」が、由紀子が再構成した「記録」であるとは明記されていない。しかし、笛子や桜子がどんな人間だったのかを牧子にも知ってほしいと願った由紀子であれば、広子にも同様のものを送っているのではないだろうか。そう考えれば、勇太郎が日本にいたころの話を子どもたちに直接伝えなかったかわりに、勇太郎の「記録」を再構成した由紀子の「記録」と、それを読んだ広子の解釈も含めて、牧子と兄の登志夫に伝えられたとも考えられる。つまり、由紀子が再構成した「記録」の最初の読者はクニコとパトリスではなく広子であり、その後、牧子を介してフランス語で日本の昔の話としてパトリスにも伝えられていたと考えられ(カモンカカというヤマンバの言い伝えをピレネーに住む魔女の話に変奏して牧子がパトリスに伝えたように)、パトリスはその原本である「記録」を読みすすめているという複雑な構成が成されている。
さらに作中では、パトリスがフランス語に訳した「記録」を牧子が英訳して兄に送るという構想があることを、クニコが明かしている。
「パトリスが大あわてでフランス語に直して、それをマキコが英語に直したら、いったいあのメモワールがどれだけ変わってしまうのか、ちょっとそらおそろしい気もするけど、でも、それでいいのよね」
このときクニコが抱いた想いは、あるいは勇太郎を「記録」の執筆に踏み切らせた想いと重なるのではないだろうか。そもそも勇太郎は由紀子からの唐突な手紙に請われて「記録」を書いたが、「記録」の冒頭で「私の記憶を事実として信用しすぎないように」と注文をつけ、本格的な年代記に入るまえに、二人の姉と最後に話し合った場面を置いた。そのなかに二種類の言い伝えが登場する。ひとつは姉や勇太郎がくりかえし聞かされてきた馬の話、山の話、カモンカカ(ヤマンバ)の話などの民話であり、もうひとつは有森家に代々伝わる先代の話である。先代の話とは一言、「信玄堤の工事で活躍した小太郎なる人物が特別にホウビをもらった」と伝えられているだけで、代々の当主がそれぞれの好みに合わせて解釈を施してきた。勇太郎自身の解釈もそこで記されている。いくらでも変奏可能な民話はもとより、代々伝わる言い伝えとその解釈を記すことで、勇太郎は「記録」もまた自身の手を離れたあとは読むものに委ねられていることを示したかったのではないだろうか。そして、その想いが自分の記憶を頼りに「記録」を書きすすめる後押しとなったのではないか。
それでも自分の記憶を基にしているいじょう、「私」が記述の中心となり、「私」の主観が中心となるのは避けようもなく、「私」が有森家の中心人物であるような描き方にエゴを感じた勇太郎は、途中で「有森有太郎」なる人物を「記録」のなかに登場させる。しかしそれもまた戦後を語るにあたり、「私」語りに戻している。そうした葛藤に加えて、日本とアメリカ、日本語と英語の間で揺らぎ、子どもたちとのすれ違いに悩む勇太郎の葛藤も「記録」のなかには流れこんでおり、読む者は有森家の年代記とは別の、勇太郎が書きすすめている時間のなかになんども立ち戻される。
後に妻の広子が言うように、勇太郎にとって「記録」に没頭する時間は「必要な手続き」だった。また、その時間のなかで「記録」を書くにあたり、勇太郎にはそのときそこで話されていた言葉として日本語が必要だったが、それを読む方法は一様ではない。パトリスへ宛てた手紙のなかで、由紀子は勇太郎に「記録」を手渡されたときにこう言われたと明かしている。
「ここに書いたことは、もう忘れるさ。遠い昔の話だ。(中略)こんな時代もあったという記念にはなるかもしれない。こんな時代が本当にあったのか、と自分でも信じられなくなっている、という記念かな」
勇太郎から手渡された「記録」を読んだ由紀子は、追記を加え、勇太郎の姉である笛子の日記と桜子のノートを加えた。それは由紀子によるひとつの読み方であると同時に、次の読者である広子と牧子、パトリスへ向けて、勇太郎以外の視点から「記録」を補完する方法でもあっただろうが、勇太郎の記憶または「記録」への由紀子、笛子、桜子からの応答とも考えられるのではないか。そのなかで由紀子が次の読者へ受け渡したかったと考えられるある一点について、パトリスに宛てた手紙のなかに引かれたつぎの補助線から考えてみたい。
「勇太郎さんの『記録』には、勇太郎さんや私の母の父親、つまりあなたにとって曽祖父にあたるひとの文章も添えられていますが、――昔気質のおそろしく堅苦しい文章なので、ひどく読みづらいでしょうが、あきらめないで、なんとか工夫をして読んでみてください」
なんとか工夫をして、という要請は、パトリスが日本語を母語としないことを考えれば、当然といえば当然であり、もちろんそれは否定できないが、由紀子はつづけて勇太郎の父・源一郎を「山の時間に入り込もうとしたひと」と説明している。勇太郎もまた「記録」のなかで言い伝えを伝える場面において、「人間の時間のなかでなにが起ころうが、動物たちとの世界だけが『本当の話』として私たちの心に生き残りつづけるのかもしれない」と述懐しており、そこでは「人間の時間」という言葉が使われていたが、馬の話、山の話、石を拾い集めて樹木を調べまわる源一郎の存在も含めて、「山の時間」を身近に感じていたはずである。そうした「人間の時間」、「山の時間」あるいは桜子のノートのなかに流れる石の時間も含めて、由紀子は「記録」のなかに多数の時間が流れこんでいると感じ取ったのではないだろうか。由紀子が「記録」に添えた添え書きには、源一郎が調査した溶岩洞穴や富士山の樹海を訪れたときのことや、母・笛子に聞かされたぶどう畑、南アルプスの話を思い出しながら、甲府の有森家のお墓を訪れたときのことが記されている。パトリスへ宛てた手紙には、「私の死んだあとにつづく時間への頼りとして」この手紙を書き残したいという言葉もある。「記録」を手渡したときに勇太郎は自嘲もこめて「こんな時代もあった」とつぶやいたが、由紀子は「記録」のなかに流れている時間こそ、勇太郎が残したかったものであると考え、パトリスや牧子にもその時間のなかになんとか入り込んでほしいと願ったのではないか。そして、二歳のパトリス宛てという不確定な時間のなかに「記録」を送りこんだ。
「記録」のなかに立ち顕れる時間は、勇太郎や笛子、桜子たちが生きた時間であり、いっぽうで生き残ってしまったものたちの葛藤も勇太郎が書きすすめていく時間のうちに含まれている。「自分はこれだけの時間を生き、そしてそれを終えた」。津島佑子は『火の山』において、有森勇太郎の「記録」と明記することで、ひとりひとりの人間が生きた時間が、その生をこえて受け渡され、書き継がれていくというテクストの可能性に挑んだのではないか。その意味では、『火の山』は未完の小説であるといえないだろうか。
*1 津島佑子『火の山−山猿記』(講談社文庫、二〇〇六)
【書誌情報】
『火の山 山猿記』(上・下巻)
講談社文庫 2006年1月発行 本体857円(上巻)、800円(下巻) A6判 656p(上巻)、616p(下巻)
ISBN 978-4-06-275297-8
【執筆者プロフィール】
中里 勇太(なかさと・ゆうた)
文芸評論、編著に『半島論 文学とアートによる叛乱の地勢学』(金子遊共編、響文社)。


















