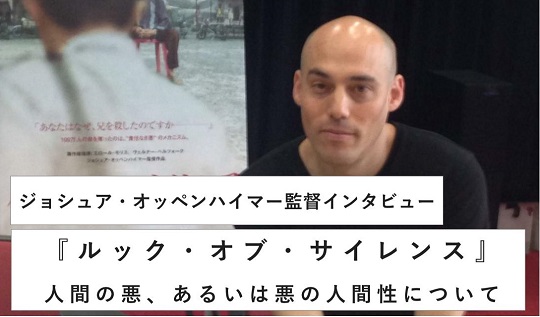
きょう7月4日、ジョシュア・オッペンハイマー監督の新作『ルック・オブ・サイレンス』が渋谷シアターイメージフォーラムで封切られた。昨年同館で連日長い列を作った『アクト・オブ・キリング』の続篇に位置づく作品である。
1965年、インドネシア。軍事クーデター(未遂)後のスハルト政権下において、100万ともいわれる人びとが「共産主義者」のレッテルを張られて虐殺された。20世紀後半最大の虐殺ともいわれる9月30日事件である。
前作『アクト・オブ・キリング』は、虐殺の実行犯に当時の殺人を演じさせるという、ともすればおぞましい手法によって人間の悪を描き、インドネシア国内だけでなく、各国に衝撃をもたらした。
『ルック・オブ・サイレンス』は、前作とは真逆の視点を採る。同じ時代の虐殺によって兄を殺された青年アディが、加害者側の人間たちと対峙する、その道行きの過程をおさめている。けばけばしい色彩に飾られた前作とは異なる表題通りの静けさが全篇を重く蔽う本作でも、描かれるのは人間の悪である。
本作の公開にあたって来日したジョシュア・オッペンハイマー監督に聞いた。
[取材・文=萩野亮(neoneo) ※2誌合同]
★あわせて読みたい
【Report】行為と演技、虐殺の〈アクト〉をめぐって――世紀の問題作『アクト・オブ・キリング』
【Review】 〈グロテスク〉から遠く離れて――『アクト・オブ・キリング』 text 井上遊介
PLOFILE
ジョシュア・オッペンハイマー Joshua Oppenheimer
1974年、アメリカ、テキサス生まれ。ハーバード大学とロンドン芸術大学に学ぶ。政治的な暴力と想像力との関係を研究するため、民兵や暗殺部隊、そしてその犠牲者たちを10年以上取材してきた。これまでの作品に、『The Grorbalization Tapes』(03/クリスティーヌ・シンとの共同監督)、『The Louisiana Purchase』(98/シカゴ映画祭ゴールド・ヒューゴ受賞)、『These Places We’ve Leaved to Call Home』(96/サンフランシスコ映画祭ゴールド・スパイア受賞)など受賞歴のある映画のほか、多数の短編がある。イギリス芸術・人権研究評議会のジェノサイド・アンド・ジャンル・プロジェクトの上級研究員で、これらのテーマに関する書籍を広く出版している。
―

© Final Cut for Real Aps, Anonymous, Piraya Film AS, and Making Movies Oy 2014
|沈黙を撮る
――この作品はまさにサイレンス(沈黙)についての映画であると感じます。ことばであるよりも、沈黙する人びとの表情や時間がこの映画の核を成しています。そのなかで主人公のアディさんが、ただでさえ危険な行為であるにもかかわらず、自分の顔を隠すことなくさらしていることが映画にとって非常に重要であると思いました。このことはアディさん自身が望んだことなのでしょうか。
ジョシュア・オッペンハイマー(以下JO) この作品は2012年に撮影されました。『アクト・オブ・キリング』の編集を終えて、公開を待つ短い期間に撮っています。『アクト・オブ・キリング』がインドネシアで公開されたら、自分はもうそこにはいられないだろうと想像できました。今度の映画ではアディがメインの協力者になるとは思っていましたが、そのときはまだ主人公になるとは考えていませんでした。わたしは当時から彼にビデオカメラを渡していて、メモ代わりに、作品の視覚的な手がかりとなるようなものを撮るようにお願いはしていたんです。1960年代の虐殺について、サイレンス(沈黙)が何十年もつづいている状況でしたから、それがどんなものであるのかを現在の観客が共感できるような作品にしたいと思いました。恐怖による沈黙、思い出したくないがゆえの沈黙、それらをしっかりととらえなければならないと感じました。
2012年にアディと再会したとき、彼はこう言いました。「ジョシュアが加害者への取材をするのを何年も見てきて、自分は変わった。兄を殺した人間と対峙しなければならないと強く思っている」と。被害者の遺族が加害者に対峙するなどということはそれまでインドネシアで一度もなされたことがなく、あまりにも危険であるため、わたしは彼にやめるよう諭そうとしました。すると彼は、撮影されたテープのなかから、唯一わたしに送っていなかったものを見せてくれました。そのシーンというのは、映画の最後に使っている、アディの父がいまどこに自分がいるかもわからず恐怖に駆られている、あの場面でした。
テープを再生しながら、ずっとアディは泣いていました。その場面が撮られたときは、ラマダン明けの正月のような時期で、家族みんながいる時間だったにもかかわらず、アディの父は誰のことも思い出せない、でも恐怖だけはおぼえているという、すべてを忘れてしまった初めての日だったと言います。彼はどうすることもできず、思わずカメラをもって撮り始めていた。――父にはもう遅すぎる。自分の家族を殺した者は権力の座につき、自分たちは恐怖の檻に閉じ込められたまま、それが日常になってしまっている。その恐怖から解放されるためには、加害者と対峙しなければならない、そう彼は思ったのです。
それは復讐心から来るものではありません。ただ相手を理解し、もし彼らが自分から責任を取るようなことがあれば、やっと自分は加害者を赦すことができるし、お互いに恐怖によってつながれた状態ではなくともに生きてゆけるだろう、と。だからこそ会いたいんだと彼は言いました。
匿名で協力してくれたインドネシアのスタッフたちに相談すると、方法はあるかもしれないと言われました。『アクト・オブ・キリング』を撮っているなかで、組織の上の人間と接触していたために、下っ端の人間はわたしが上の者と懇意にしているというイメージをもっているようでした。だから、ある程度の安全性は確保されるのではないか、と。『アクト・オブ・キリング』が公開される前ですから、このタイミングでなら撮れるかもしれないという話になっていったのです。
ただ、わたし自身はアディの気もちはよくわかるけれども、加害者に会ったところでおそらく何も得られないだろうとは彼に言いました。30分や1時間、ひとりひとりに会ったところで、そのひとりが謝罪する勇気をもつかといえば、もたないだろう、と。かえって恐怖を増幅するような結果になるのではないかと。
いっぽうで、これを映画にすることそのものに意味があると考えました。それだけ社会にひびが入っているということ、いまだに傷が強く残っているのだということはとらえることができるし、それをとくに若い観客が見たときに、真実や和解、正義のために立ち上がるきっかけになるかもしれない。個別の対峙のなかでは成果のようなものは得られないかもしれないけれど、もっと大きな結果を残すことができるかもしれないと思いました。
この映画はその対峙をドラマチックに描きたかったわけではありません。むしろこのサイレンスをより詩的な形式で撮りたかった。アディの父はその後亡くなってしまいましたが、彼を含む多くの人が60年代の虐殺とその爪痕による恐怖にしばられながら亡くなってゆきました。そういったすべての方への弔辞であり、記憶にとどめるためのサイレンスです。そのわたしの意図が成立しているかどうかは、アディが自分の父を撮ったシーンを最後にもってきたときにうまくはまるかどうかだと思いました。
――映画の公開によって加害者の安全性が揺らいだりはしなかったのでしょうか。
JO 加害者の村では、彼らの家族を慮って上映をしていません。また出演してくれた人のうち、必要最小限な名前しか出していません。彼らは、この映画に出ることのリスクを100%はわかっていないようでもありました。けれども、これらの映画によって大きく人生を変えられたというような人はアディ以外にはいません。
―

© Final Cut for Real Aps, Anonymous, Piraya Film AS, and Making Movies Oy 2014
|インドネシア社会へのインパクト
――小学校の授業のシーンがありますが、いまだに反共的な教育が行なわれている事実に衝撃を受けました。『アクト・オブ・キリング』も『ルック・オブ・サイレンス』も、ともにインドネシアで多くの観客を集めたということですが、どのような層の人が見ているのでしょうか。そして映画によって世論はいまどのように動いているのでしょうか。
JO 『アクト・オブ・キリング』をインドネシアで公開したとき、公開のいわばインフラを作ったわけですね。NGO、宗教団体、被害者遺族の団体、大学やシネクラブ、そういったところで何千回も試写会を行ない、大都市から地方の村々までを網羅して見せることができました。くわえて今回は、国立人権委員会とジャカルタ・アーツ・カウンシルというふたつの国家機関が配給元になっています。草の根的な上映に加え、こうした公式の配給によって、労働者階級から上流階級まで、地方から大都市まで、さらに多くの人に見せることができました。メインとなるのは知識層で、彼らにとってはこの映画はマストです。
『アクト・オブ・キリング』の157分版では、60年代当時のプロパガンダフィルムが挿入されています。それといまだに同じようなことが学校では教えられています。ところが、いまではインドネシアの「歴史教師協会」がオルタナティブな歴史教科書を作成しています。それが完成すれば、政府のカリキュラムに則ったものに加え、「実はこうだったんだ」というオルタナティブ版も教えるということになります。
2本の作品は、メディアや一般の方がたが、いまも根強い恐怖・汚職・腐敗といったものについて、公に話すことができる触媒に間違いなくなっています。前作でこじあけた空間を、今度の作品はさらに広げることができたと思います。試写の状況も同じで、前作では200人ほどの閉じた試写会で全員を招待していたのが、今回は初日に500カ所、すべて公に開かれた一般試写で、すでに3500回ほどを数えています。作品を見ることで、いままでことばにすることもできなかった恐怖の深さをあらためて目にし、加害者と被害者が恐怖という絆で結ばれたまま同じ共同体で生きている、その沈黙のなかで自分たちはどうするべきなのかを考えるきっかけになっていると思います。
――ジョコウィ大統領も見ているのでしょうか。
JO わかりません。ただ、彼の母親の家でDVDを受け取っている写真を友人が撮っています。ジョコウィは、1965年の虐殺について認知し、掘り下げることを公約で掲げて選挙に当選した人物です。『ルック・オブ・サイレンス』ほど、インドネシアでパブリティを集め、緊張を生み、語られた作品はなく、現地メディアは2014年を代表する1本だと書いていますが、大統領という立場においては、見たことを公にしないほうがよいという政治的な判断もあったのではないかと思います。
―

© Final Cut for Real Aps, Anonymous, Piraya Film AS, and Making Movies Oy 2014
|「悪の凡庸さ」を超えて
――『アクト・オブ・キリング』が日本で公開された折、ハンナ・アレントの「悪の凡庸さ」(『イェルサレムのアイヒマン』)という語を用いた批評が数多く出たのですが、わたしはそれに違和感をもちました。ナチの合理化された官僚機構に埋め込まれて犯罪を行なったアイヒマンとインドネシアの虐殺の加害者とは峻別しなければならない面が多々あると感じます。監督ご自身はアレントの議論をどのように考えていますか。
JO ハンナ・アレントの洞察は、ただ弄すべき表現ではありません。わたしは彼女の考え方には同意するけれども、そのことばだけを単なるフレーズとして受けとめるのではなく、それを挑戦として受け止めなければならないと思います。日常のなかに凡庸なものとして悪があるなかで、わたしたちはどのように生きてゆけるのか。もしかしたら、その問いがこの2本の映画が始まる鍵になったのかもしれません。
「鋭い浅さ」acute shallowness以外はアイヒマンには責任がないとアレントは言いましたが、わたしは魂が浅いなどということは信じません。悪をなすために、人は自分に嘘をつき、自分に距離を置きます。だから「悪の凡庸さ」というフレーズの次のステップをわたしは模索しているのかもしれません。「邪悪さの人間性」というものをわたしはこの2本の映画で掘り下げようとしたのです。邪悪さの根源には、あまりに人間的な罪悪感や罪への思いがあるのだと思います。
――人権団体の依頼を受けて初めてインドネシアに入ったのが2001年だということですが、あらためて2本の作品を完成させて思うことは何でしょうか。
JO 自分にとって特別な旅になりました。この経験が自分を映画作家に育ててくれた。いちばん重要なのはエンパシー(共感)というものを学んだことです。たがいに共感しあい、思いやりあい、人を「悪魔」、あるいは「悪」であると決めつけることをわたしたちがやめられれば、真の人間的な社会を作り上げることができるのかもしれません。そうした社会においては、暴力は想像もできないような本来あるべき存在になるのだと思います。
邪悪な行為にいたる者もひとりの人間です。わたしたちは彼らを「モンスター」であると決めつけておしまいにしてしまいたがるけれども、彼らも自分たちと何の変りもない人間であるわけです。このことは人によってはつらい真実であるかもしれません。けれども逆に、モンスターと自分たちが思っている以上に似ている存在だと知ることは、人間性が大切にされる世界をつくることにつながる可能性があるとも考えられるわけです。(了)
[2015年6月1日 イメージフォーラムにて]
―
★あわせて読みたい
【Report】行為と演技、虐殺の〈アクト〉をめぐって――世紀の問題作『アクト・オブ・キリング』
【Review】 〈グロテスク〉から遠く離れて――『アクト・オブ・キリング』 text 井上遊介
|公開情報
 ルック・オブ・サイレンス
ルック・オブ・サイレンス
製作・監督:ジョシュア・オッペンハイマー 共同監督: 匿名 撮影:ラース・スクリー
製作総指揮:エロール・モリス『フォッグ・オブ・ウォー』 / ヴェルナー・ヘルツォーク『フィツカラルド』 / アンドレ・シンガー
2014年/デンマーク・インドネシア・ノルウェー・フィンランド・イギリス合作/インドネシア語/103分/ビスタ/カラー/DCP/5.1ch/日本語字幕:岩辺いずみ/字幕監修:倉沢愛子
配給・トランスフォーマー 宣伝協力:ムヴィオラ 原題:THE LOOK OF SILENCE
© Final Cut for Real Aps, Anonymous, Piraya Film AS, and Making Movies Oy 2014
公式HP:www.los-movie.com
★7/4[土]シアター・イメージフォーラム他全国順次公開!
―
|取材・文
萩野亮 Ryo Hagino
1982年生。映画批評、本誌編集委員。立教大学非常勤講師。編著に『ソーシャル・ドキュメンタリー 現代日本を記録する映像たち』(フィルムアート社)、雑誌連載に「キネマ旬報」星取評。
![]()


















