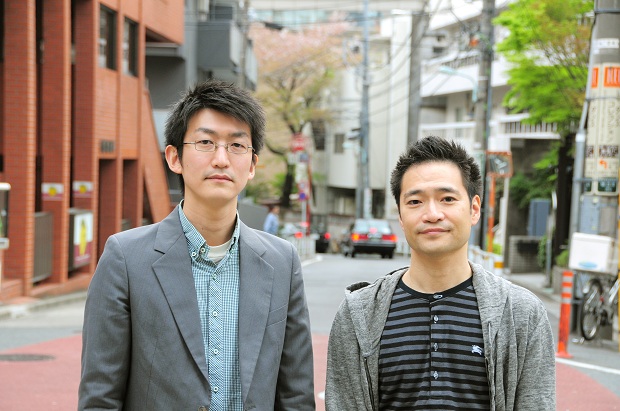岡本和樹監督作『隣ざかいの街−川口と出逢う−』(2010)の上映会が、7/2(月)UPLINK-FACTORYにて開催されます。
この作品は、川口市情報・映像メディアセンター メディアセブンで2009年11月~2010年3月に行われた映像制作ワークショップ「記憶の手触り-川口と出逢う-」を通して製作されたものです。
ワークショップは15名の映像制作未経験の参加者とともに、映画監督・岡本和樹の指揮、同じく映画監督・大澤未来によるサポートのもとに行われました。「ある街を複数の眼によって観察する」という趣旨に沿って、ビデオカメラを渡された参加者たちは街に出て、自ら被写体を探し、取材をしました。2週間に一度のペースで行われたワークショップの場で岡本・大澤とともにディスカッション、指導を重ね、最終的に岡本の手によって編集が行われ121分の本編が完成し、同時にワークショップそのものの風景をドキュメントした作品『記憶の手触り-川口と出逢う-』(監督:大澤未来/56分)も製作されています。
なお、今夏には同メディアセブンにて、岡本和樹演出による新しい映像制作ワークショップの開催を予定しています。
今回は上映会の開催にあたって、岡本監督のたっての希望で、小説家の星野智幸さんとの特別対談が実現しました。今回は後篇をお送りします(前篇はこちら)。なお全文は上映会にて配布のパンフレットに収録されています。
―
|上映会概要
日時|2012年7月2日(月)19:00開場/19:30上映開始
料金|1000円(ドリンク付き/予約できます)
上映作品| 『隣ざかいの街−川口と出逢う−』(2010)
トークゲスト|諏訪敦彦(映画監督)
萩野亮(映画批評/neoneo編集主幹)
岡本和樹(本作監督)
※ご予約などくわしくはこちら。
―
|受動的な媒体
岡本:その他者と共にある世界の複雑さと、そのうねりが、星野さんの小説にはずっとあると思っているんです。そういう意味で、僕は星野さんの小説はドキュメンタリーだと思っています。さっき星野さんは僕に対して、岡本個人じゃないものをやろうとしていると言ってくれたけれども、僕からすれば星野さんこそが、星野智幸という文学の才能を見せつけようとしているわけではなくて、何か社会に蠢いているものを受け止めて、それに対して問い返すという形で小説を書いているのではないかと感じているんです。
星野:岡本さんがドキュメンタリーって言ってくれたことが、本当に僕にも大きな自信になり続けていて。それで、もう一回今回見直しながら、ドキュメンタリーってこういうものなんだなと確認できたのは、映像に限らないんだけど、基本的に「聞く」ことだと思うんですよ。この作品の撮影だって、撮っている側の人が、「自分はこう思うんですよ」「こう思うんですよ」と畳みかけたあげくに、「で、どう思いますか?」とやっていたら、ドキュメンタリーにならないですよね。そうじゃなくて、向こうが喋りたい気持ちになったらそれに任せて、こっちはどう反応していいかわからなくても、受け止めきれるかわからなくても、とにかく受動的な媒体に自分がなるっていうかね。そういうことがドキュメンタリーなんだなって、今回すごく感じました。取材している人もそうだし、それが集積して一本になった作品もそうだし。
今の状況の中では、「自分の存在の希薄さを克服したい」「自分の存在を示したい」という気持ちの人が多いと思うんです。そういう気持ちはすごくわかるし、重要なことでもあるんですけど、そういう人が、一方的に言葉を発するあまり、逆にコミュニケーションの取れない状況を作り出している。必要なのは、それぞれが聞き合うっていう態度だと思うんです。だから、それぞれがドキュメンタリーをするような感覚で人と接するようになれば、お互いが聞き合うということになり、そうすれば自分が喋る番もくるわけで、そういう関係性になれるといいのかなと思っているんです。
小説の場合は、どうしても一人で作業する部分が多いから、自分から聞きに行ったかどうかってことが表に出にくいけれども、ドキュメンタリー映像の場合は、やらないと作れませんからね。その力っていうのは、若干羨ましいなと思いながら見ていたんですけどね。
岡本:でも星野さんの小説は、そういう意味での所謂「小説」っぽく思えないんですが、そこには何か秘密があるんですか?
星野:デビューしてずっと書き続けていくうちに、なんかもうすごい危機感にまみれていったんですよ。単純に自分が枯渇していくって感じがすごくあって。それはネタがなくなるとかそういう意味じゃなく。なんというか、どんどん独善に陥っていくっていうかね。でも、独善に陥っている人の特徴って、自分が独善に陥っているって気付かないことなんですよね。なので、そうなることへの恐怖というか、その孤独感の恐怖っていうのがすごくあったんです。だから、具体的にどこという頭があったわけじゃないんだけれど、「現場に出なきゃ、現場に出なきゃ」っていう焦りが2000年代の半ば頃からずっとあった。現場っていうのは、例えば原発事故だったらそこの現場に行くとか、そういうことじゃなくて。要は、この川口でやったWSのような、そういう意味ですよね。具体的な他者のいる場に身を置く、っていうのかな。そういう意味での現場に出るということを、2000年代の半ば位から、仕事の性質上、意識してやらないと、ひきこもって独善的であるのが普通になって、独善的であるということすらわからなくなっちゃうと思ったから、けっこう意識して行うようにし始めたんです。それを意識すると、なんとなく文学業界から遠のいていく自分がいるわけですけど。それで、ホームレスサッカーに関わってみたりとか、路上文学賞をしてみたりとか、様々ですね。それでも、つまみ食いみたいなものだけどね。
岡本:それをやって、何か変わりましたか?
星野:すごくショックだったのは…。2003年に『ロンリー・ハーツ・キラー』っていう小説を書いたんですけれども、その時まで僕は、日本の社会の問題っていうのは、食っていけなくなることではなくて、黙っていても生きていけてしまうことなんだと思っていたんですよ。若い人もそうだと思っていた。実際に大学で教えていても、創作科だっていうのもあるけど、「創作したいから就職はちょっと考えてないんですよ」とか学生が言うのを聞いていると、要するにバイトしてれば食っていけてしまって、むしろ死というものが身近に感じられないっていうことの方が問題なのかなってずっと思っていたんです。『ロンリー・ハーツ・キラー』はそういう観点から実は書いたんですが、「でも、それは男の価値観であって、女の人の価値観はそうではない」っていうのが、その時の考え方だったんですね。でも、それから1年か2年の間に、小泉時代真っ盛りだったわけですが、ワーキングプア等と言われる存在が顕在化していって、衝撃を受けました。自分が「生きていけてしまう社会の現実感のなさ」みたいなことを考えていた間に、既に世の中はそうじゃなくなって、食っていけないという状態が普通になっている層が、若い世代にも高齢者にも、こんなに拡大していた。それを自分は全然知らなかったということに、ひどくショックを受けたんです。
何故知らなかったのだろうって考えると、やっぱり現場に出ていなかったからなんですね。知識として知らないというだけでなく、今の世の状態を自分は感知できず、違う社会像を思い描いていた。そのことがショックだったんです。
現場に出て他人と知り合って話すというのは、知識としての情報を集めるんじゃなくて、感触としての情報を仕入れることなんです。感触で仕入れる情報とうのが僕にとっては、生きる上でも仕事の上でも、何よりも大事で。小説を書くのも、言葉で得た情報は最終的には必要なんだけども、やっぱりまず感触からスタートする。現場に身を置く作業が還元され始めたのが、2007年位の『無間道』とかその辺になるんだけどね。自分で書いていて納得がいくというか、そういう気持ちにようやくなれたんですよ。それまでの4、5年間は、空回りじゃないけど、どこかそういう独りよがりへの不安を抱えながら書いていたんです。そういう感覚で生きているっていうこと自体が辛かったですね。
|文学空間=踏み出す場
星野:路上文学賞を始めた時に考えたのが、文学とはどういう場か、ということです。書く側は、自分の独善的な言葉じゃなくて、そこから一歩外に出て言葉を発し、読む側も、こっちにわかる言葉で書けと要求するんじゃなく、自分のテリトリーから一歩外に出て、自分ではわからないかもしれない言葉にアクセスしてみようとする。どちらも自分の領域・テリトリーじゃない場所に一歩ずつ踏み出して歩み寄ろうとするのが、文学空間だというふうに考えたんですよ。
それは映像のドキュメンタリーでも基本的には同じことだと思っていて。
岡本:まったく同じですね。
星野:受ける側、発する側って、ドキュメンタリーではすごく複雑ですよね。話す人・聞く人、作る人・見る人、そのほかすべてがそういう関係性の中で進行する。しかもめまぐるしく立場が変わるので、簡単に線引きできない。小説の場合は、文章の中に自分の癖なんかが自然に出ちゃうものだし、他人の実録であっても書き手の頭を経由するわけだから、どうやったってそこに自分がブレンドされてくわけですよね。ドキュメンタリー映像の場合には、その部分はいったい何に該当するんですか、編集ですか?
岡本:映像の場合は、撮影と編集の二段階があると思うんです。先ずは、撮影段階でのフレーミング。見るということは私の視線・視点でしかあり得ないわけで。相手がもっている最も本質的なものを撮りたいと思っても、そこに本質を見出そうという撮り手の意志がないとそれは画面に写らない。それは、画自体のフレーミングもそうですが、どんな話をするかという意味内容のフレーミングも同様です。相手が話していることを受け止めると同時に、その話の中の何を自分は深く聞きたいかということがはっきりしていないと対話になっていかない。そして、編集段階でも、映像自体に本質的な何が映っているのかを、虚心に受け止める姿勢は必要ですが、いくら虚心と言っても、そこから何かを見出すということはそもそも一つの意志ですし、更にそれを作品として組み立てていく際には、より強力な意志が必要となります。それはフィクション以上の意志かもしれません。
星野:川口の場合だと、撮っているのはみんな個々の参加者ですよね。編集は岡本さんとクレジットされているけれど、映像全部を編集したんですか?それとも、撮った人も少し編集をしたのか、その辺の兼ね合いはどんな感じでやったんですか?
岡本:今回に関しては、編集はもう完全に僕がやりました。本当はそこも議論しながら僕一人の力学じゃなくてやりたかったんですけども、結果それはWSという時間の制約と、その条件内での作品の質のことを考えて、そうせざるを得ませんでした。WSをやっている時に一番問題だったのは、全員とは言わないですが、自分の意志がはっきりしない人が多かったということです。他人の声に耳を傾けることをやって欲しかったわけですが、それ以前に、そもそも自分の意志自体をあまり持っていない。「あなたがどうしたいか、どう思うかを考えながら撮ってください」という単純なことが通じない。例えば、風景を撮るときに、何をどう撮れば良いのかということの答えは、撮る人当人の中にしかないわけです。それはカメラの教則本に書いてあるわけではないし、僕がこう撮りなさいと指導するものでもない。フレームは、その人が何をそこで本質的だと思っているかでしか決まらないわけですから。
これは画だけの問題ではなくて、インタビューにしても、WSの中で「僕が聞きたいことじゃなくて、あなたが何をその人に会って聞きたいのかを素直に質問すれば良いだけですよ」と言っても、ありませんとまでは言いませんけど、どうしていいのかわからないというような感じで。そういう状況で、撮影段階の指導でも、そして編集に関しては完全に、僕が指揮者としての力学を行使してしまったということが、僕の中では、悔いとして残っているんです。もうちょっと、編集も含めてみんなが全体で考えられるものになれば良かったなと。
星野:でも逆に言うと、そういうふうに、最初から「ドキュメンタリーとは何か」ということも考えないし、そもそもそんなに抽象的に社会の問題や物事を普段あまり深く考える経験をしていない人達が、ああいうふうに街を見て、街のことを考えて、そして、それぞれの人の中で、割合は違うにせよ、何かが発動したっていうことは大きな違いですよね、やっぱり。やる前とやった後の変化はすごく重要なことですよ。
岡本:それでも、どうしても悔いが残るんです。あの時、ずっと言ったのは、「人の声を聞くということと、あなたが自分のことを考えるっていうことは別の問題じゃないんですよ」ということだったんです。
星野:撮っている自分が記録になっていく。だから相乗されて、出来上がっていくわけでね。
岡本:それがコミュニケーションでしょ、ということが言いたかった。そして、それが震災後、本当に重要な意味を持っていたと気づいたんです。自分が言いたいことをただ言うだけでもないし、相手の話をただ聞くだけでもなくて、その間に何かがあるんじゃないかと。
星野:やり取りしていく循環の中で、っていうことですよね。(了/全文は7/2の上映会にて配布のパンフレットに収録されています。)
―
|プロフィール
星野智幸 ほしの・ともゆき
1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。2年半、新聞記者を務めた後、メキシコ留学。1997年『最後の吐息』で文藝賞を受賞し、デビュー。2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞。2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞。2011年『俺俺』で大江健三郎賞。他に、『ロンリー・ハーツ・キラー』『無間道』など。2002年と2004年〜2007年、早稲田大学で創作の教員を務める。
岡本和樹 おかもと・かずき
1980年生まれ。表現と現実との関わりをテーマに作品を作っている。これまでの作品:『帰郷‐小川紳介と過ごした日々‐』〈共同監督〉(2005年)/『あがた森魚 月刊日記映画「もっちょむぱあぷるへいず」2007年1月~8月号』〈共同監督〉/『演劇実験室・天井棧敷の市街劇や元劇団員の現在を追った『世界の涯て』(2007年)/写真映画「ヤーチャイカ」のメイキング『もうひとつのヤーチャイカ』(2009年)