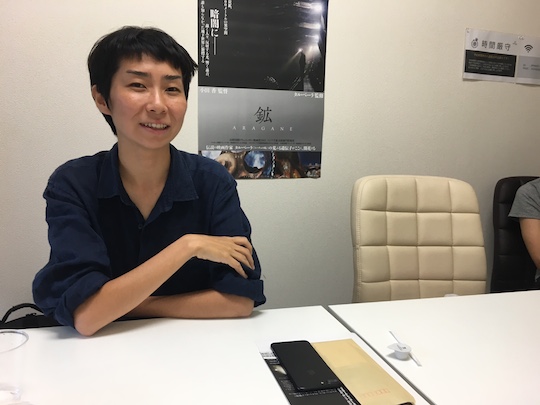 小田香監督
小田香監督 ——たしかに“異世界”という感じでした。撮っている時はどのような感覚でしたか。
小田 だいたいは50ミリで、観たまんまの距離感で撮っていますが、クローズアップはズームレンズで、遠い場所から三脚をつけて撮っています。
どこに人が立っていて、立っているということはヘッドランプがあって、光がどんな動きをしていて……というのは、イメージとしてはとらえていました。ショットの世界観は、自分の意識とそんなにずれは無かったです。ただ、そのイメージが何を意味するのかは現場では分からず、撮っている時は精いっぱいで、頭で考える余裕はなかったですね。
——どの程度意思疎通があったかは分かりませんが、映画を観ていて、小田監督が、坑夫の人たちにすごく受け入れられている感じがしました。
小田 撮影中は、とにかくこの人たちの邪魔をしてはいけない、という意識がほとんどでしたね。もちろんこれを撮りたい、というイメージはあるけど、いらんことをして事故が起きたら元も子もないし、狭くて限られた空間なので、まずは邪魔にならないところにカメラを置かないと成立しないと思っていました。
いつも一緒に坑道についてくれたベゴという現場監督の方が、気を使ってくれた部分もあると思います。わたしがカメラに集中していた時は常にそばにいてくれたし、。怪我なく、大きなトラブルも無く撮影ができたのは、彼がいたことが大きかったと思います。 『鉱 ARAGANE』より
『鉱 ARAGANE』より
——炭坑の構造や、歴史的な情報を映画に入れなかったのは、なぜですか。
小田 鉱山の歴史や、どういうプロセスで掘られ仕分けられるかなど、一通りは聞き、カメラを向けたこともありましたが、それは私の最たる興味ではありませんでした。撮影の半ばぐらいで、どういうふうに舵を取ったらよいか迷った時期もありましたが、わたしが惹かれているのは、やはりあの鉱山という地下の空間自体と、鉱山の労働だったのです。
もっとも、それしかできなかった、というのもありますね。ドキュメンタリーだから、それっぽくショットを撮って、情報を入れ、ナレーションを入れる、という形式もあり得ますが 私のやりたいことではないし、中途半端な気持ちでそれを入れても失礼だから。この『鉱 ARAGANE』が、私のできたことの全て、私の視点だったと思います。
——ショットショットは大胆ですが、作品全体では、鉱山に入って、掘削をして、鉱を出る……といった“時間”が論理的に構成されていますね。
小田 撮影の最終日に、ベゴに坑夫の方たちの一日の流れを箇条書きで書いていただいたんですね。入って、こういう作業があって、重機の現場があって、出てきて、シャワーを浴びて、帰り、次のシフトの点呼があって、その繰り返しなんだと仰っていて、忠実に構成したつもりです。
——ひとつだけ、坑夫が現場監督のような人に文句を言うシーンがあって、そこが印象に残りました。
小田 実は、あのシークエンスを入れるのは最後まで迷いました。あそこだけ映像言語が異質だから。なんで入れたかといえば、言葉は通じないから本意は分からないけれども、私、50ミリで、近い距離で撮っていたから、皆さんも撮っているの意識されているんですね。一種のパフォーマンスかもしれない、とも思いました。であるならば、私の目撃したこととして、入れてもいいんじゃないかと思いました。
——あのシーンがあることで、映画の間口が広がったような気もしました。
制作途中でタル・ベーラ監督のアドバイスは、どういうかたちで入るのですか。
小田 生徒の中でも、彼が来て欲しい人と、そうでない人がいます。彼が来ることで、現場のパワーバランスが崩れることがあるからです。私の場合はドキュメンタリー的な手法で撮っていたので、彼はまず炭坑には入らないとは思いますが、彼が来たら、炭坑の人たちとの関係がややこしいことになるかなと思って、呼びたいとは思いませんでした。
撮影中のアドバイスとしては「あなたが何に惹かれているのか。正直に撮りたいものを撮りなさい」ということだけでした。編集段階では、ものすごくショットに厳しい人だと思いました。2、3回ほどプレビューがあって、一緒に観るんですが、ここがいい、これはダメ、しか基本的には言いません。でも私が中途半端なショットを入れていたら、すぐに「これは抜きなさい」という指示が飛ぶのです。いつも的確で、あれは彼が映画を撮るなかで培った才能ではないでしょうか。今でも彼だったらどう観るかなとか、このショットは甘いんちゃう?とか、ショットを考える指針にはなっています。 『鉱 ARAGANE』より
『鉱 ARAGANE』より
——原作ものの劇映画の構想から、結果としてドキュメンタリーの『鉱 ARAGANE』なった。ご本人としては、手法の変化をどう捉えておられますか。
小田 今はフィクションとノンフィクションの境界が揺らいでいて、ドキュメンタリ―でスクリプトを書く人もいれば、劇映画で即興でやられる方もいますから、特にどちらにこだわりがあって、ということはありません。
私が映像でやりたい事としては、いま分かっていることや知っていることを伝えるというよりも、私が知らないもの、これから理解していきたいと思っているもの、忘れたらあかんと思っているものをキャプチャーしたい気持ちの方が強いです。それに向いているアプローチがドキュメンタリーだったのだと思います。
——現地で上映会をした、その経験が大きかったと聞きました。詳細を教えていただけますか。
小田 坑夫の人たちに何十人も集まってもらって、映画のラストに出てくる点呼用の部屋で上映会をしたんです。カーテンがつけられないから明るいままで、『鉱 ARAGANE』は暗い映画だから、ほとんど見えないんですけど、皆さん立ち去ることもなく、最後までみてくださって、「よく頑張ったね」とか、暖かい言葉をかけてもらいました。地上勤務の方からは「地下がどうなっているかが分かって良かった」とか。自分たちが撮られている高揚感をフィードバックとしていただけのは嬉しかったですね。
語弊のある言い方かもしれませんが、彼らは普段、映画を観る人たちではないので『鉱 ARAGANE 』の映像世界に耐えられるか心配していましたが、みなさん映画の理解者というよりは、私を支えてくれたんだと思いました。よう頑張ったな、という意味で。
結果を共有してもらえた。この事実が私としては大きかったんです。もちろん世界の映画祭を回って、日本でも公開できるのは嬉しいけど、まずはあの人たちにみせるべきではないのか。その思いが常にありましたから、みせられて良かったです。
 撮影現場「ブレザ炭坑」での『鉱 ARAGANE』上映会。最前列左から3番目が小田監督
撮影現場「ブレザ炭坑」での『鉱 ARAGANE』上映会。最前列左から3番目が小田監督
——最後に、完成から丸2年。この『鉱 ARAGANE』上映をしていく中で、起きた気持ちの変化などはありますか。
小田 『鉱 ARAGANE』に限らず、映画を作ることを、私自身が一番楽しいと思っているんです。私が映画から一番喜びをもらっているから、それを人と共有するというのはどういうこと? って、いつも考えます。観る人たちに、映画を通して何を提供できるのか。1000円とか1800円って決して安くないですもんね。
昨年大阪で上映した時からずっと思っているのは、『鉱 ARAGANE』で私が提供できるのは“体験”なんじゃないかなって。ボスニアの地下の世界を体験してもらって、こういう人たちが今も地球にいて、日本と全く逆の場所で働いている。そのことを意識しもらうだけでも、嬉しいなって思っています。
【映画情報】
『鉱 ARAGANE』
(2015年/ボスニア・ヘルツェゴビナ、日本/DCP/68分)
監督・撮影・編集:小田香
監修:タル・ベーラ
プロデューサー:北川晋司/エミーナ・ガーニッチ
提供:film.factory/FieldRAIN
配給:スリーピン
本編写真は全て©film.factory/FieldRAIN
公式ウェブサイト:http://aragane-film.info
10月21日(土)〜新宿K’s cinemaにてロードショー、以下全国順次公開
『鉱 ARAGANE』トークイベント開催!
日時:10月21日(土)
ゲスト:樋口泰人さん(映画評論家・爆音映画祭ディレクター)&小田香監督
小田香監督短編作品特別上映!
各回『鉱 ARAGANE』の前に上映
10月26日(木)『呼応』(2014年・19分 監修:タル・ベーラ)+小田監督トーク
10月27日(金)『ひらいてつぼんで』(2012年・13分)
10月28日(土)『FLASH』(2015年・25分)
【監督情報】
小田 香 Oda Kaori
1987年大阪府生まれ。フィルムメーカー。
2011年、ホリンズ大学(米国)教養学部映画コースを修了。卒業制作である中編作品『ノイズが言うには』が、なら国際映画祭で観客賞を受賞。東京国際LGBT映画祭など国内外の映画祭で上映される。
2013年、映画監督のタル・ベーラが陣頭指揮するfilm.factory (3年間の映画制作博士課程)に第1期生として招聘され、2016年に同プログラムを修了。2014年度ポーラ美術振興財団在外研究員。2015年に完成されたボスニアの炭鉱を主題とした第一長編作品『鉱 ARAGANE』が山形国際ドキュメンタリー映画祭2017・アジア千波万波部門にて特別賞を受賞。その後、リスボン国際ドキュメンタリー映画際やマル・デル・プラタ国際映画祭などで上映される。
映画・映像を制作するプロセスの中で、「我々の人間性とはどういうもので、それがどこに向かっているのか」を探究する。
![]()


















