 ©疾走プロダクション
©疾走プロダクション
—インタビュー—
お互いの人生をかけた、1:1の勝負
——インタビューについては先ほどのように監督以外にも他のインタビュアーがいらっしゃいますよね。弁護士の方や他の人によって撮られた映像もいくつかありました。
原:他の人といっても、取材はいつも私の奥さん、小林と一緒に行くんですね。それで聞いてみる?ってたまに彼女にふって、彼女がインタビュアーとして声をかけるっていうシーンはあります。それは別々にではなく一緒に行って、たまにあなたが聞いた方がいいんじゃないかってノリで聞いているんです。
——基本的にはほとんど監督がインタビューをされている形なんですね。
原:そうです、基本的にはね。なぜ私が聞いているのかという理由を説明しておきますと、これは作家の個性、考え方なんですけど、私はカメラを必ず正面に置くんですよ。で、受ける方はインタビュアーに向かって、目を見て答えるでしょう。人間の自然な行為ですよね。だから私はカメラが正面にあって、相手が目の前にいるという状況を作る。相手は私の目を見るから、私の目がカメラの中心になるようにします。映像のモニターを見ながら相手の目を見てるんですよ。そこに私の顔を持っていくんです。で、可能な限り相手の目線をレンズの目線に近づける。だから私が聞くんですよ。正面の目線が一番というのは、スクリーンに映ったとき、観客にストレートに届くという構造になるんでね。それで私が聞く。方法の一つですね。
——かなり印象的でした。1:1という構造が伝わってきます。
原:そうなんです。だから正面なんですよ。インタビューってのは1:1の勝負、お互いの人生をかけてるんです。優しくインタビューするからいいってもんじゃなくて、お互いの人生のすべてをかける、極端に言うと、サシの勝負だって感覚があるんですね。だからもう目一杯聞きたいことをズバっと聞いて、相手も自分の人生をかけて答えてくれるのが正しいインタビューだと思っているんです。
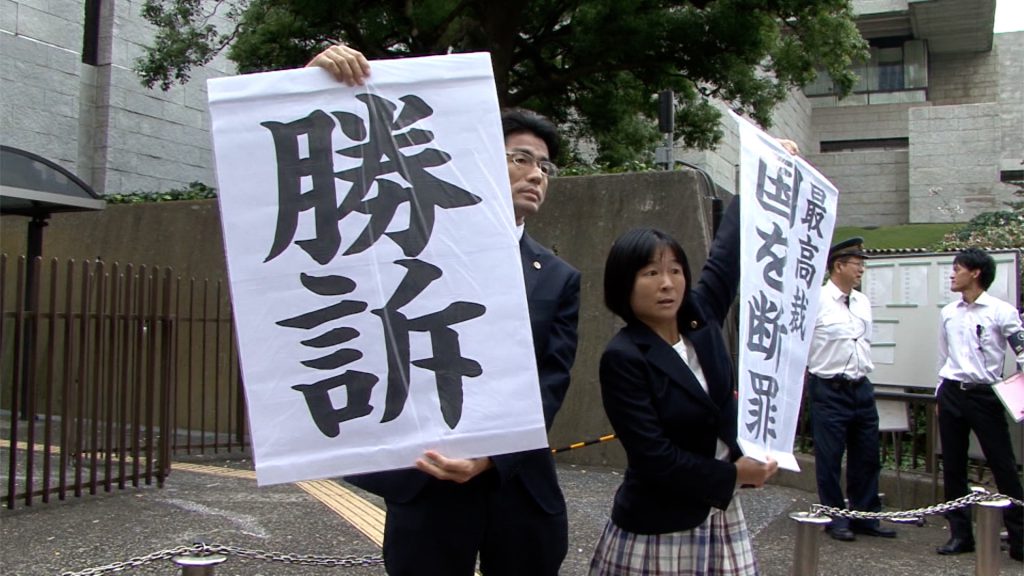 ©疾走プロダクション
©疾走プロダクション
—編集—
丁寧に丁寧に、心情を映像から探して組み立てる
——先ほどから何度か話は出ていますが、編集についてお聞きしたいと思います。編集は秦岳志さんが担当されていましたが、そこに監督はどのくらい携わられているんでしょう。
原:監督の体質というか好みもあるんでしょうけれども、私は編集をやってるすぐそばに四六時中いて、ここはこうしたい、ああしたいっていうふうに言わないほうがいいっていう感じがあるんです。編集マンは誰に頼んだらいいかなってことは考えますよね。こちら側がお願いする人を選ぶわけですから。それで、『神軍』のときの鍋島さんというアイディアもあったんです。ただ鍋島さんはすごく上手な人なんですけど、とにかく短く短くっていうことがすごく上手な人だし、自分も短くしたがる人なんですよ。短くすることで映像のテンポを作っていく。だけど、今度の作品は鍋島さんじゃないだろうって感じがしたんですね。
それで秦さんに出会って、あぁ、秦さんの方がいいなあって思ったんです。秦さんはとっても優しい人なんですよ。それで、被害者の人って弱者っていわれますよね。弱者っていわれる人の心情を丁寧に丁寧に映像から探してきて組み立てて、その人の感情を作り上げていくことをしたんです。そういう作業は長くなるけど、でも秦さんに編集を頼んで良かったなって思ってます。だから秦さんが、「4時間くらいの長さですが一応最後までいきました」ってなったところで、じゃあ見せてくださいって言って見るわけです。それで、構成の小林と編集の秦さんと私とで、あのシーンは落としていいんじゃないかとか、ここはもっと短くていいんじゃないかとか、ここはもっと長くしてくれとかいろいろ注文を出してまた秦さんが一人で作業すると。で、できたって言ったらまた全部を見てどうしようってことを繰り返しながら少しずつ凝縮していくんです。だからあんまり細かいことを言うと煩わしいっていうか、編集マンは編集マンの整理があるんですよ。整理っていうか表現の世界の仕事なんで、むしろ編集マンの持っている整理がきちんと出た方がいいと思うんです。編集マンを選んだ時点で編集マンに委ねるっていうことですね。映画って集団作業なんですよね。監督にとっては監督作品でも、編集をしている人にとっては、自分の作品っていう要素が必ずあるわけですよ。カメラマンが別の場合はそのカメラマンの撮影作品っていう要素がそこに入ってくる。それのトータルで一本の作品が成り立っている。そういうものだと思います。
——感情を作り上げるという話が出ましたが、そういった編集もあって、人物像が多角的に描かれているように思えました。というのは、ある人物の描かれる映像がいくつか組み合わされるわけですが、それぞれ異なる聞き手が存在しています。原告の人を支える柚岡さんが同じフレームに入って聞き手になる場合もあれば、スピーチの場面では通りがかりの人が聞き手に回って、会見のときはマスコミに向けて、だとか、いろいろな人に向けての発言がありました。そうやって様々な聞き手を用意して多角的に見せるというのが特徴的でしたし、これは、自分たちの思いを聞いてほしいという原告の方の強い気持ちも表していると思います。
原:あぁ、なるほど。それは作り手の世界観ですよね。つまり人間って、社会がないと生きていけない生き物でしょ。社会には色んな人がいて、好きな人がいれば嫌いな人もいると。色々交錯し合いながら一つの巨大なカオスを作っていって、その中で生きていくのが人間のあり方というイメージがあるんです。だから、実に多様に絡み合っていることを映像にしようと思うと、そういうシーンを作っていこうと思うようになるんですね。
これでいいのか、平成のニッポン人
時代が求めて、できる。それが映画というメディア。
——公式カタログに、今回の作品はまさに平成のニッポン人の自画像を描いたものであるという記述がありました。監督は今回の作品を通じて平成のニッポン人にどのような印象を持たれましたか。
原:『神軍』の奥崎謙三さんみたいな人は、まさに昭和って時代に作られているんですよ。だからね、映画ってどんなに過去を扱っていても、カメラが回った時代の空気感が必ずカメラに写りこむという信念が私の中にあります。ましてや昭和って時代が認めてきた、受け入れた生き方の人を主人公にしてるわけだからね。あれはやっぱり昭和っていう時代でしか生まれなかったドキュメンタリーだよねっていう思いが非常に強いんですよ。
で、さっきも言いましたけど、そういう過激な生き方は昭和という時代とともになくなっていったと、今はもうああいうふうな過激な生き方ってのはありえないと。生活者しかいない。しかしその生活者が権力から虐げられる、過酷な生き方を強いられるっていう状況がどんどんきつくなっているような実感があるんですよね。だから、泉南の人たちが、ああいう国がやるべき政策をしなかったために、しないとどうなるかってことを知っててしなかったという結果として、被害者が生まれていくわけじゃないですか。その構造というのは福島の原発の構造も同じ、水俣病も同じ、他のなになに問題というのもほとんど基本的には同じだっていう感覚があるんですよね。
問題は、6年前に地震があって、原発事故があって、そのときに巨大な不幸があったにもかかわらず、日本人は秩序正しく行動したことが賞賛を浴びたことがありましたよね。あれは頭にくる。それはもう大きな間違いで、秩序正しくて日本人がああいう行動をしたんじゃないんです。豊臣秀吉の時代に、刀狩りってのがありました。秀吉が武器を全部取り上げました。で、武器だけじゃなくて、権力に刃向かう牙も全部抜かれたんだろうっていうってのが私の持論なんです。それ以来日本人は上の者に対してものすごく臆病であると。こんなんでいいのかよ日本人という思いがずっと私の中にあるんですよ。で、それがまさに泉南の人たちに向けた思いなんです。もっと、国に対して、権力に対して喧嘩を売らんとどうしようもないやないかっていう感覚が非常に強い。今どんどん税金も増えて、弱者が痛みつけられるなかで、自分たちが怒らないとどうするんだよっていうメッセージが、この映画にないと意味がないと私は考えているんです。だから映画って、監督個人の才能で作るんじゃないんですよ。時代が求めるんですね。
——最後に、次回作についてお聞きしたいと思います。
原:水俣を仕上げないといけない。もういい加減に。これが難しいんですよね。撮れたって感じがしないもんだからね。また同じ悩みを持つわけですよ、アスベストのときと。アスベストでそう言いながら出来た作品を、みんなが面白いって言ってくれるんだから、きっと水俣もそういうふうになりますよって言われます。そんなん分からんもんねえ、映画ってやってみなきゃどうなるか(笑)。
【作品情報】
『ニッポン国VS泉南石綿村』
(2017年/日本/215分)
2018年3月10日より、ユーロスペース他全国順次公開
監督:原一男
製作:小林佐智子
構成:小林佐智子 編集:秦 岳志 整音:小川 武
音楽:柳下 美恵
助成:大阪芸術大学 芸術研究所 JSPS科研費
製作・配給:疾走プロダクション
配給協力:太秦 宣伝協力:スリーピン
【執筆者プロフィール】
原田麻衣(はらだ・まい)
京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程在籍。IndieTokyoに所属し、数々の映画上映に関わる。論文に「トリュフォー作品における脚ショットと女性像」(CineMagaziNet! No. 21掲載予定)。



















