 2001年 ニュージーランドの国際会議で発表した石橋さん
2001年 ニュージーランドの国際会議で発表した石橋さん
「視線の病」としての認知症
第4回 「逆転の発想」が切り拓いた新時代
(前回 第3回 はこちら)
認知症というのは、自分が自分でなくなっていく病気だと、多くの人が恐れていた。ところが石橋典子さんの視点はまるで違った。
「家族からもモノのように扱われることがあまりに辛くて、自分を押し殺し、捨ててしまわないと生きていられないような状態を生き抜いた人たちこそ、自分が自分であることの究極を生きているのであり、私たちはその人たちを憐れみ見下すなどもってのほかで、畏れ敬わないといけない。最も忌み嫌われる認知症老人こそ、最も敬われ、貴ばれるべき人である。」
石橋さんは、親鸞が「善人なおもて往生をとぐ。いわんや悪人をや」と説いたのと同様、常識をひっくり返す「逆説」によって語った。
1990年代から2000年代にかけて「認知症ケア」を切り拓いたパイオニアたちには、そういう逆説を語る人たちが多かった。「認知症になっても以前と変わらぬ暮らしが出来る」というのではなく、「認知症になったからこそ出来ることがある」というものの見方。そうした語りの中では、一般に「周囲を困らせる厄介者」とされる人たちは、「大切なものに気づかせてくれる先生」とされる。
今ふりかえると、こうした「逆転の発想」は少々ロマンチックで、時代錯誤な印象を持つ人が少なくないのではないかと思う。多くの人にとっては、「認知症になったからこそ」よりは「認知症になっても」のほうがリアルであり、しっくりくるだろう。だが、リアルだからと言って正しいとは限らない。
私が指摘しておきたいのは、「認知症を病むことが自分であることを極める道である」という直観に衝き動かされ、ロマンチックな夢をみた人たちこそが「認知症ケア」という道なき道を切り拓いた、ということだ。それは単に「ケアの質を向上させる」などということではなく、当時、人間ではなくなってしまったとすら考えられていた人たちに人間であることを取り戻させる「人間回復のケア」であり、「人間発見のケア」だったのだと、私は思う。
私が初めて小山のおうちを訪ねた2001年、石橋典子さんは時代の転換点となる人物との出会いをする。いや、時代が、ロマンチックな魂の持ち主である石橋さんを「その人」と出会わせたことが、認知症の時代の大きな転換を引き起こした、と言うべきであろう。この「出会い」は、一瞬の出来事ではなく、ジワジワジワジワと浸みとおるように時間のかかるプロセスだった。後に、この転換点以降を「認知症新時代」という表現で呼ぶようになる。
私は取材者としてこのプロセスに立ち会ったというよりは、むしろ体ごと巻き込まれた。そして、「出会い」のプロセスの一部として、認知症についてドキュメンタリーを作り始め、今に至っている。
その始まりについて以下に記す。
2001年11月6日、私は石橋さんとの番組の企画を進めるため小山のおうちを訪ねた。私が考えていたのは、石橋さんがここに通う老人たちに折々に書いてもらっていた手記を通して彼らの世界を見ていくドキュメンタリーの企画だった。「認知症の老人が自らの思いを文章に書く」ということは、その当時、他では聞いたことがない話だった。認知症になると言葉を失い、意味のあることは話せなくなり、まして書くことなど出来ないと思われていた。それが認知症というものなのだと。ところが石橋さんは、言葉を失ったと思われていた人も、自分を取り戻せば話せる場合があることを立証したばかりか、さらに、その人たちに思いを文章に綴ってもらい、仲間の前や家族の前、さらには学会の場などで、折々に本人に読み上げてもらっていた。本人は自分が書いたことは忘れているが、自分の書いたことだから読むと気持ちがよみがえり、感窮まって泣いたり笑ったりする。当時よく言われた「認知症になると本人は何も分からないからいいけれど」というのが思い込みであることに気づかせ、見方や関わり方を変えるように促す活動だった。
訪ねると、石橋さんは興奮の中、私の顔を見るなり、待ちきれないように話し始めた。「川村さん、素晴らしい人に会ったのよ。」それは、小山のおうちの話ではなく、前の月にニュージーランドのクライストチャーチで開かれ、世界52か国から1000人以上が集まった国際アルツハイマー病協会国際会議の話だった。石橋さんは小山のおうちで行っていることについてポスター発表するため、医科大学の研究者たちとともに参加していた。
石橋さんは、本人によれば、英語といえばハローとサンキューしか言えないほど苦手だったが、せっかくここまで来たのだから、記念に一つくらい人の話を聞いて帰ろうと、メイン会場に入った。壇上では、一人の女性が英語で講演を始めたところだった。会場は満員。石橋さんは、何を言っているのか分からなかったが、持参したビデオカメラで撮影し始めた。スクリーンに映し出されたスライドのイラストを見ると、絶壁にしがみついている人物や、地面に開いた大きな亀裂をまたぎ越えようとする姿、そしてしっかりと握られた手。
そのとき石橋さんは直観した。
「この人は自分と同じことを言っている」。
講演が終わると、聴衆が一斉に立ち上がり、長い長い拍手をした。感動して泣いている人もたくさんいた。石橋さんもまた感激して涙を流した。その拍手は、自分のしてきたことや考えてきたことに対する賞賛や励ましでもあると考えたからだ。そして、講演していた女性が会場の外で自分の著書を売り始めると、長い行列について本を買い求め、サインしてもらって、握手し、名刺ももらった。
そんな話をし終えて、石橋さんは私に尋ねた。
「川村さん、この人は一体どういう人なの?」
石橋さんが持ち帰ったペーパーバックの表紙には、丸いめがねをかけたこげ茶のショートヘアのきりりとした表情の女性の顔写真の上に、手書きの文字が重なっている。題名は、直訳すると、『死ぬとき私は誰になっているの?』。ひっくり返すと、本の内容が短く紹介されていた。
「『クリスティーン・ボーデンは46歳でアルツハイマーと診断された』と書いてあるから、アルツハイマーの患者さんですね。」
「そんなはずはないわよ。あんな素晴らしい講演をして、みんなが感動して立ち上がって拍手したんだから。私はここでお年寄りに手記を書いてもらってみんなの前で読んでもらっているけれど、アルツハイマーの人があんな長い文章を書いて、見事に語るとは考えられない。川村さんの英語は信用出来ない。」
私は提案した。
「私の妻は英語の通訳で翻訳もする人だから、松江の私の家に行って、彼女に訳してもらったらどうでしょう?」
石橋さんは、自分の車に私を乗せる。宍道湖の西の端の出雲市から東の端の松江市まで、1時間弱走った。この日も、空は鉛色の雲に覆われ、つかの間日が差したかと思ったらまた曇り、雨が降ったりやんだりする天気だった。湖岸には、風に吹かれて細かな灰色の波が打ち寄せていた。松江が近づいた時には、もう日が暮れかかっていた。暗くなった湖面の向こうに街の灯りが遠くまたたく。これから何が始まろうとしているのか、私には思いめぐらすもとになる経験が全くなかった。
この時、妻は初めての子を妊娠していて、まさに臨月。大きなおなかを抱えていた。石橋さんが本を渡すと、すぐに声に出して訳した。聞きながら、石橋さんはガタガタと震え出した。ニュージーランドで自分が聴き、満場の人々とともに拍手した講演を行った女性が認知症の本人であったことを信じたのだ。
それは、認知症について従来の常識を覆すような実践を行ってきた石橋さん自身の認識を改めさせるような事実だった。自分が聴いたあの講演で彼女は何を言っていたのか?この著書に彼女は何を書いているのか?
放心していたように見えた石橋さんの目がキラキラと輝き始めた。そして、「この本を全部訳してちょうだい」と妻に言った。
妻は、16日後が出産予定日で今にも子どもが生まれる。おなかが突き出しているのでパソコンに向かえないし、パソコンに向かうとつわりで気持ち悪くなるから無理だと押し返した。だが、それで引き下がるような石橋さんではない。
石橋さんは、ニュージーランドで使ったビデオカメラも持ってきていた。撮影した映像を再生すると、音声は聞きづらかったが、彼女が会場で「自分と同じことを言っている」と思ったスライドの文字ははっきりと読めた。亀裂をまたぎ越える人物のイラストには、「犠牲者からサバイバーへ」、最後のスライドには、日の出のイラストとともに「希望の地平線」と記されていた。
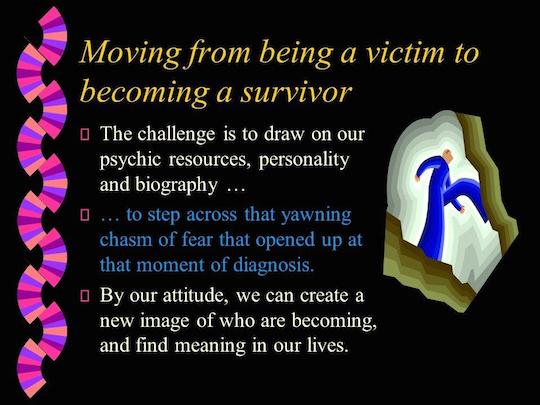 石橋さんがみたスライド
石橋さんがみたスライド
妻は、そのスライドの文字と、本の裏の内容紹介、序文、目次を訳して、カセットテープに吹き込むことなら出来ると思うと提案した。石橋さんはなおも本の全訳にこだわったが、とりあえずそれで納得した。
そして出産予定日の11月22日の夕方、私は妻からカセットテープと手書きのメモを渡され、すぐに速達で石橋さんに送ってほしいと頼まれた。妻は2週間あまり、お腹をさすりながら本を読み、ビデオを見て、カセットに吹き込んでいた。まるで石橋さんから魔法をかけられたようで、この翻訳を終えないと子どもが生まれない気がすると、言っていた。私は車に乗って閉まる寸前の松江中央郵便局に駆けつけ、投函。「出したよ」と妻に電話した。すると妻は、「あっ!」と声をあげた。破水して、水が足を流れるのを感じたのだ。私は再び車で自宅に帰り、妻を乗せて産婦人科に向かった。
その日、長男が生まれた。
そして、私たちは1年ほどの間すっかり忘れていたのだが、カセットテープに封じ込められた「その人」の言葉は、石橋さんによって方々に運ばれて、芽吹くべき種をまいていた。
(つづく。次は12月1日に掲載する予定です。)
【筆者プロフィール】
川村雄次(かわむら・ゆうじ)
NHKディレクター。主な番組:『16本目の“水俣” 記録映画監督 土本典昭』(1992年)など。認知症については、『クリスティーンとポール 私は私になっていく』(2004年)制作を機に約50本を制作。DVD『認知症ケア』全3巻(2013年、日本ジャーナリスト協会賞 映像部門大賞)は、NHK厚生文化事業団で無料貸出中。




















