|山岡はなぜコマを超えて山岡でいられるのか
ところで、これまで『美味しんぼ』に登場してきたのは実在の店や人物だけではない。Wikipedia(アクセス2014/11/30)によれば、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(秋本治)の両津勘吉と中川巡査が登場したり、『笑ウせえるすまん』(藤子不二雄A)に登場するバー「魔の巣」を模した「馬鹿の巣」が描かれたこともあった。『美味しんぼ』は、長い連載の歴史のなかで、こうしたパロディと、実在の人や物が平面に文字通りフラットに共存する、きわめてマンガ的といえる手法が採られてきたのである。そこには複数の描画のレベル(レイヤー)が存在し、コントロールされている。
こうした描画のコントロールは、かつて四方田犬彦が『漫画原論』において記号学を用いて論じたように、マンガの人物においてはかれらのアイデンティティにかかわることである。つまり、コマを超えて山岡が山岡であるためには、複数の山岡に一定以上の類似関係が認められなければならない。うっかり眉を細く描いてしまったら、髪をベタで塗りつぶすのを忘れてしまったら、山岡はとたんにアイデンティの危機におちいってしまう(いや、不安にさせられるのはもっぱら読者である)。「類似」とは徹底的に客観的に判断されるものであり、マンガ的人物はたえずこの審判にさらされている。あらためて述べるまでもなく、「類似」とはきわめて映像的な経験なのである。
たとえば実写映画がこうした「類似」をめぐる判断と不安を一見まぬかれているように思われるのは、カメラによる対象の再現力が信じられているからである。けれども、実写映画が「類似」の問題を無条件にクリアしているかといえば、決してそうではないだろう。日常的な経験として、ひとは映画の登場人物をしばしば混同し、さらにはあらかじめそれを回避するために作り手は人物間の差異を強調する。ひとりが黒を身にまとっているなら、もうひとりはたとえば赤を。ひとりが短髪なら、もうひとりは長い髪を。ひとりが裸眼なら、もうひとりはめがねを……。映画におけるこうした「類似の回避」は、ひとつの約束事として暗黙の裡に守り通されているかにみえる。
マンガと同様、そして映画的人物もまた、ショットを超えて自己同一性を保つために、容姿や演技を一貫させていなければならない(ときに素材が「つながらない!」とあくせくするのは編集マンである)。ショットとショットのはざまにはたしかな断絶が存在するのであり、そこに連続性(コンティニュイティ)を構築することこそが、何よりもグリフィス以降の「古典映画」をめぐる命題としてあった。
―
ところで映画もまた、マンガにおとらず政治家を数多く描いてきた映像領域である。まさにグリフィスによる『國民の創生』(1915)において、ジョゼフ・ヘナベリーがリンカーンを演じて以来、多くの俳優が政治家を演じてきた。合衆国の大統領ともなれば、その数は枚挙にいとまがない。
ここであらためて重要になるのが「類似」の問題なのである。すでに述べた、マンガや映画のコマを超えた人物のアイデンティティにかかわる「類似」が「存在論的類似」であるとするなら、政治家など有名人物を描く際にくわえて焦点となるのは「存在的類似」といえるかもしれない。俳優がリンカーンを演じるならば、かれはリンカーン(のイメージ)に類似していなければならない。『國民の創生』のジョゼフ・ヘナベリーも、『リンカーン』(2013)のダニエル・デイ=ルイスもそれをクリアしなければならなかった(ようにみえる)。
『美味しんぼ』にせよ『リンカーン』にせよ、こうした「存在的類似」がリアリズム上の問題となるのは、描写対象となる人物のイメージが、ほかでもない映像によって、ひろく知れわたっているからである。伝記映画とは、先行する報道映像や記録映像によってイメージを制限される特異なジャンルなのであり、すでにあるイメージがキャスティングや演出にさえ影響をあたえうるほぼ唯一の映像領域だといえる。
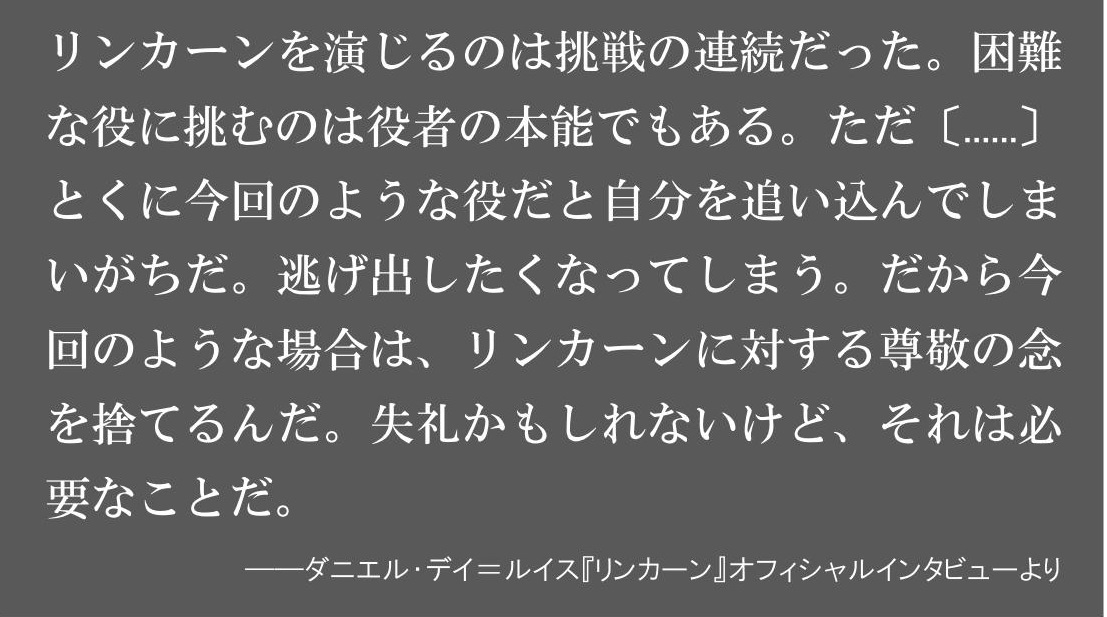
―
|マルコ・ベロッキオの伝記映画はなぜあれほどまで自由なのか
ベニート・ムッソリーニの半生を、「もうひとりの妻」としてかれを愛し憎んだイーダ・ダルセルの視点から描いた『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』(2009)は、そうした伝記映画のなかでは異形の作品だといえる。ファシスト党をひきいたイタリアの悪名高きかつての独裁者もまた、アドルフ・ヒトラーほどではないにせよ、映画史のなかでくりかえし演じられてきた。もっとも有名なのは、『ブラック・シャツ』(1974)と『砂漠のライオン』(1981)で二度演じたロッド・スタイガーだろうか。そのほかにも、『ムッソリーニと私』(1983)のボブ・ホプキンス、『ムッソリーニとお茶を』(1998)のクラウディオ・スパダロなどが、このイタリアの政治家を演じている。また、チャールズ・チャップリンの『独裁者』(1940)でジャック・オーキーが演じたナパロニがムッソリーニを模していたこともよく知られている。
イーダ・ダルセルは、若きベニートと恋に落ち、かれとのあいだに一子をもうけた。しかし、ベニートはべつに妻子をもっており、やがてイーダと息子を隔離させて歴史から抹消する。女は息子に、父親と同じ名まえをつけた。これは史実である。
『愛の勝利を』でマルコ・ベロッキオは、ありし日のムッソリーニ本人のすがたを記録したニュース映像を挿入している。そこに映っているのは、この映画でムッソリーニを演じた俳優(フィリッポ・ティーミ)のすがたとは似ても似つかぬ実在人物の肖像であり、両者が同一人物であるとはとうてい見なすことができない。ニュース映画の引用を終えて、ベロッキオは主人公にこう云わせている。
「ムッソリーニを見たわ、ニュース映画で。巨人のようでまるで別人だった。」
おそるべきせりふである。このひとことをもって『愛の勝利を』は、ニュース映画のムッソリーニ本人と俳優によって演じられた人物の同一性(存在論的類似)を担保してしまう。マルコ・ベロッキオは、俳優をモデルとなる人物に似せようという伝記映画の苦労にほとんど価値を見出していない。むしろそうした類似的リアリズムの呪縛から解かれた場所でこのフィルムは撮られている。
このシーン以降、ムッソリーニはニュース映画の実像においてしか登場しない。この場面が重要なのは、歴史=映像に登録された施政者と、歴史から抹消された女とを決定的に分かつ瞬間であるからだ。三浦哲哉はこう書いている、「神の存在、そしてあらゆる旧い価値を否定した彼は、テクノロジーの力を借りて、自分を超人的な「映像」へと生成させる。すべては自由であり、同時に虚しい。ムッソリーニへの愛は、また、空虚な「映像」への愛を意味し、したがって、実質を欠いた不毛な愛に留まるしかない」(「不毛な世界で愛は始まる」)。
かの女は、スクリーンに映るかれを一方的に「見る」ことはできるが、かれが視線をかえすことはない。そしてこのフィルムでフィリッポ・ティーミがふたたび画面に登場するのは、イーダが産んだ息子ベニートとしてである。成人に近づいたかれは、ニュース映画で見た父の演説をまね、やがて狂気してゆく。総統の息子でありながら、母親と同様に政治的に存在を消されたかれは、いわば父との「類似の煉獄」のなかで神経をすりへらしていった。同じ俳優によって演じられたその狂気は、ほとんど「映画」というテクノロジーの狂気である。
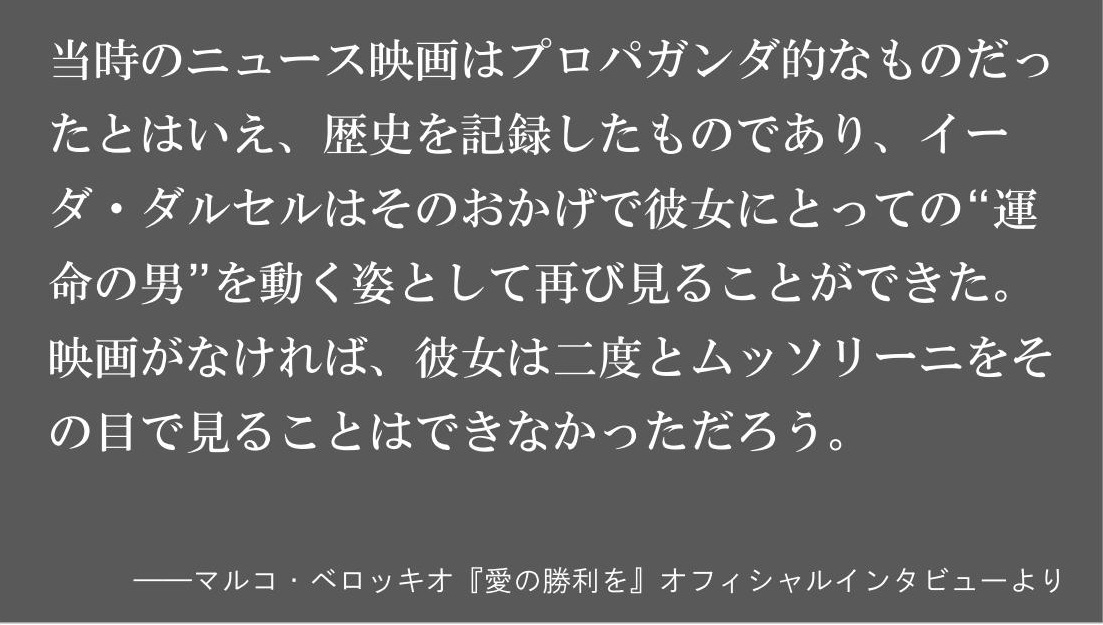
くらべるのはもちろん無謀だと知っているが、『愛の勝利を』におけるベニート・ムッソリーニの肖像は、『美味しんぼ』の井戸川克隆前双葉町長の肖像とほとんど対極に位置している。映画とマンガという違いこそあるが、フィクションが実在の人物を描こうとするとき、あるいは「現実」を語ろうとするとき、直面する類似的リアリズムの問題に両者は行きあたっている。『美味しんぼ』がマンガ的表現の限界のなかで、かぎりなく写実的に描くことでマンガをダイレクトな「メッセージ」に還元しようとし、『愛の勝利を』は「存在的類似」の不安をいかにもあっけらかんと超えて、自由でしなやかな「愛」の「ストーリー」を語ろうとする。
『美味しんぼ』で描写される井戸川前町長は、むしろ『愛の勝利を』に挿入されるニュース映画のムッソリーニ氏本人に、似ているのである。「福島の真実」編は、だからニュース映画ならぬ「ニュース漫画」の様相をおびているのであり、井戸川氏が鼻血をふきとった紙片をうつした自身の写真をフェイスブックに投稿したとき、『美味しんぼ』は「ニュース漫画」としてのただしさが追認・担保されようとする。マンガと写真というメディアを超えていながら、かれが「まるで別人」ではないことが、証明されようとする。
そのことをどう受けとめるべきかは、この連載の関心にない。ただひとつ、ニュース映画が施政者たちの格好のイデオロギー装置として機能してきた、前世紀の歴史を想起するばかりである。
-
|参考資料
雁屋哲・花咲アキラ『美味しんぼ』110巻、小学館、2013年
『週刊ビッグコミックスピリッツ』24-26号、小学館、2014年
四方田犬彦『漫画原論』、ちくま学芸文庫、1999年
茨木正治『メディアのなかのマンガ 新聞一コママンガの世界』臨川書房、2007年
スティーヴン・スピルバーグ監督『リンカーン』オフィシャルインタビュー、YouTube「20世紀FOX公式チャンネル」、2013年
三浦哲哉「不毛な世界で愛は始まる」、『nobody』35号、2011年
マルコ・ベロッキオ監督『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』劇場公開パンフレット、 エスピーオー、2011年
-
★「documentary(s)」連載一覧はこちら。
|プロフィール
萩野亮 Hagino Ryo
1982年生れ。映画批評、本誌編集委員、立教大学非常勤講師。編著に『ソーシャル・ドキュメンタリー』(フィルムアート社)、共著に『土瀝青 場所が揺らす映画』(トポフィル)など。「キネマ旬報」新作星とり欄連載中。
![]()


















