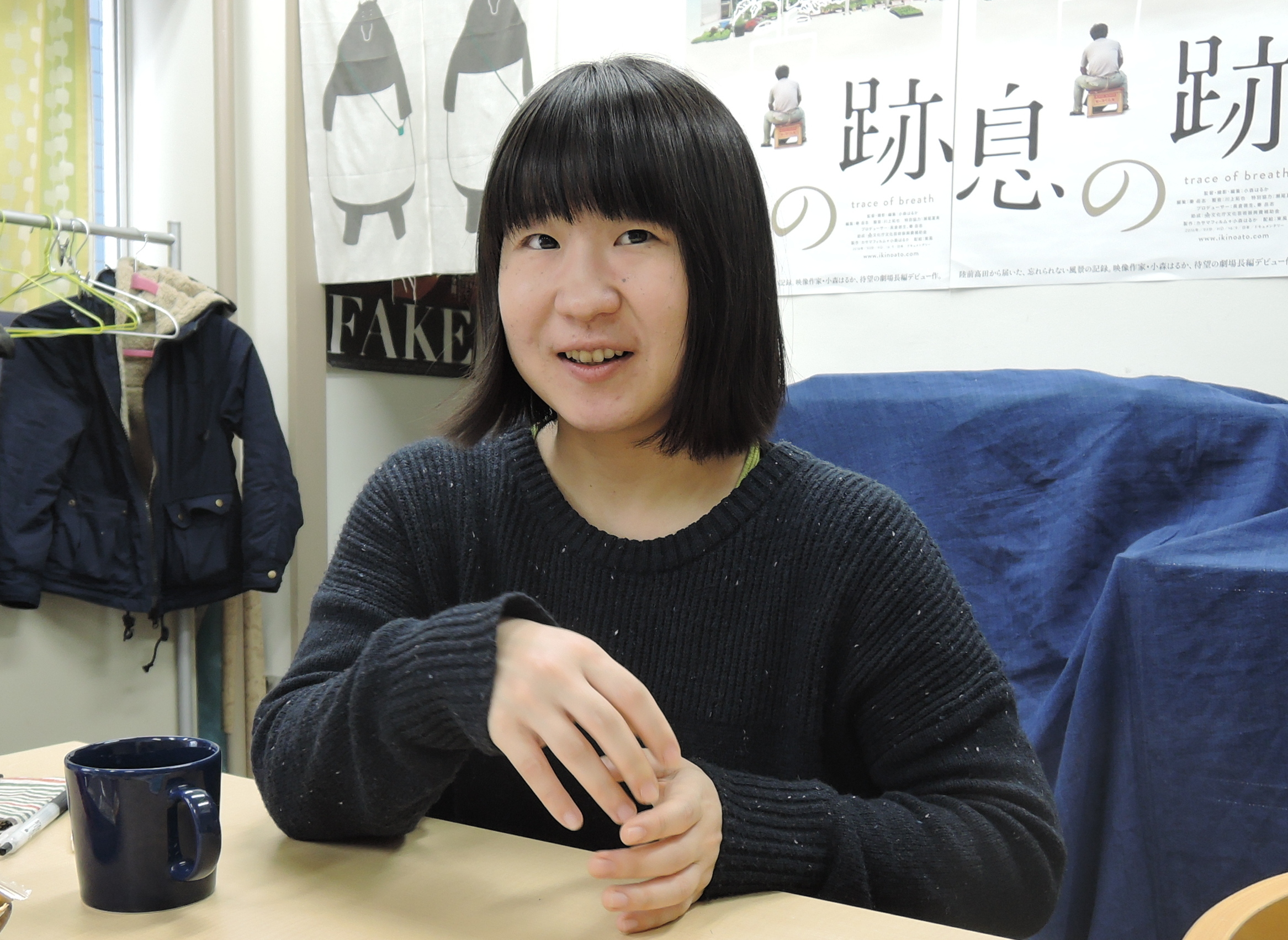 『息の跡』は、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市で「たね屋」を営む佐藤貞一さんの物語だ。津波で流された店舗を自力でプレハブを組み復活させ、英語や中国語を独学で学んでは、被災の手記を外国語で出版する。震災後に陸前高田に移住し、街の記録を続けていた大学院生の小森はるか監督は、そんな佐藤さんに魅せられ、「たね屋」と佐藤さんの記録を始める。その約2年をまとめた映画が、現在、公開されている。
『息の跡』は、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県陸前高田市で「たね屋」を営む佐藤貞一さんの物語だ。津波で流された店舗を自力でプレハブを組み復活させ、英語や中国語を独学で学んでは、被災の手記を外国語で出版する。震災後に陸前高田に移住し、街の記録を続けていた大学院生の小森はるか監督は、そんな佐藤さんに魅せられ、「たね屋」と佐藤さんの記録を始める。その約2年をまとめた映画が、現在、公開されている。
たね屋という手作りの空間で展開される佐藤さんの語りは独特で、実に様々な示唆に富む。イメージは「津波の被害」に留まらず、時空を越えた街の歴史やそこで暮らす人間の不可思議へと膨らんでゆく。これ以上はぜひ、劇場で映画を見ながら体感し、想像頂きたいのだが…では、カメラのこちら側の小森監督は何を思い、どのようなものとして佐藤さんの話を受け止め、「たね屋」という空間のフレームを切り取ったのか。話を聞きたいと思った。
(構成・編集=佐藤寛朗)※2017年2月取材
たね屋の佐藤さんに出会うまで
——震災後の陸前高田に住んで何かをしたいと思ったのは、どのようなきっかけだったのですか。
小森 2011年3月に東日本大震災が起きて、どうしていいのか分からないなかで、同級生で、絵と文章の作家の瀬尾夏美さんから誘いがあって、3週間後に東北に行ったんです。ちょうど大学の卒業と大学院への進学を決めたタイミングで、時間はあるのにできることは何も無くて悶々としていたのですが、瀬尾に誘われて、ボランティアならわたしにも何かできるかなと思って東北に行きはじめて、そこからずっとふたりで行動していました。
陸前高田に引っ越したいという提案は、かなり早い段階で瀬尾の方からありました。まだいろんな沿岸の地域に通っている時ですが、風景や人の気持ちが東北へ行く度にすごいスピードで変化していることに気づいて、その変化に追いつきたいということと、瀬尾は絵を描くので、アトリエを東北に構えて絵を描きたいと言っていました。それは2011年5月頃のことで、わたし自身は「え?引っ越し!?」みたいな気持ちだったんですけど、
——ちょうど大学院に進学した頃に震災が起きたということですが、その頃、どんなことを表現としてやりたいと考えていたのですか。
小森 私は絵がうまくかけるとか、そういう才能は無いけど表現には関わりたいと思っていました。映画は共同制作だから、何かの一員だったら自分にもできるかもしれないと思って、映像の学科がある大学を受験して、結果的に東京藝術大学の先端芸術表現科へ進学しました。その学科は、表現方法が自由な学科でした。写真、絵画、身体表現などいろんなメディアに触れましたが、やはり映像で表現したいと思いました。だけど具体的に何をしようと思った時に、ビデオカメラを持ったことすらなくて専門学校に行こうと思い、映画美学校に通うことにしたんです。
映画美学校のフィクションコースは、インディペンデントの劇映画を目指す人たちが多かったと思いますが、インディペンデントであれ、制作現場はスタッフも役者もそれぞれの役割や技術を求められるような映画の作り方が基本でした。わたしはその作り方が向いていないのではないかと気づいて、作る仕組みから考えないといけないと思いました。役者もスタッフも一緒になって、共同して何かを作るプロセスそのものが映画になればいいと思ってたんです。監督ではなく、カメラマンとして出来事に立ち会いたかったので、役者さんの方から出てきたアイデアにカメラを持って着いていくように映画を作れないかなと思って、実験をし始めていた時期ではあったんです。だから震災前から作り方の中に、ドキュメンタリー的な要素は含まれていたと思います。
——陸前高田には、表現の手がかりを探しにいったということなんでしょうか。それとも、被災の現実にうちのめされたことの方が大きかったのでしょうか。
小森 映画でやろうと思っていたことは、あくまで映画の枠の中での話で、それを震災の後に同じように実践したいとは思わなかったですね。それよりも震災という大きな現実に対して、自分が何をしたらよいのか分からなかったし、方法論も持っていなかったですけど、ボランティアなどをしていくうちに何かがつながるかもしれないという、現実と表現との接点を模索する意識はありました。今回の『息の跡』も、佐藤さんとの関係性の中で作品ができていったと思うし、私がこう撮りたいから佐藤さんこうして下さい、という映画ではないので、たまたま佐藤さんに出会うことができて、たまたま居合わせることができたら撮らせてもらえたものの集合体というか。その中でお互いカメラに記録することを意識するような関係性が生まれていったような気がします。 『息の跡』より©2016 KASAMA FILM+KOMORI HARUKA
『息の跡』より©2016 KASAMA FILM+KOMORI HARUKA
すぐには、カメラを回せなかった
——「たね屋」の佐藤貞一さんに出会ったのは、陸前高田に越してから、どれぐらいの時期ですか。
小森 実際に陸前高田へ引っ越したのは2012年の4月です。佐藤さんには2012年の5月とか6月には出会ったような気がします。
はじめて会った時にお話がすごく面白くて佐藤さんの魅力に引き込まれました。その後、ちょこちょこ顔を出すようになって、撮影を始める前の段階では、ふらっとお店に立ち寄るような間柄にはなっていました。
——佐藤さんの第一印象はいかがでしたか。
小森 最初から朗読を聞かせてくれたんですよ。店のものをいろいろ見せてくれたりとか、
覚えているのは、その時にお客さんがフラッと入ってきたんです。恐らくご家族を亡くされて、その後はじめて自分で花を育ててみようと思って、何を育てたらいいかを相談に来られたんですね。その時の佐藤さんの態度や、話し方や、お客さんを元気づけている姿を見た時に、この店が背負っているものが、陸前高田の人たちにどれだけ必要とされているのかが分かった気がしたんです。佐藤さんがここでたね屋を営んでいることが、とても尊いことに思えたんです。
お店のものを手作りで作っている芸術家のような佐藤さんと、地域のたね屋としての佐藤さん。両方の佐藤さんに最初に出会えたのが、自分にとっては大きかった気がします。あの店にどういう日常があるのかを、長い時間をかけて、見てみたくなったんですね。
——そのような佐藤さんの二面性を追いたくて、撮影をお願いしたということでしょうか。
小森 その場では思わなかったですけどね。引っ越してから何をするかが全然決まらず、もやもやしている時間が半年ぐらいあって、佐藤さんを撮ろうと決めたのは、7ヵ月後の2013年1月です。それまではカメラを回さずに、ふつうに佐藤さんのところに遊びに行ったりしていました。
——なぜ、すぐにカメラを回さなかったのですか。
小森 陸前高田では、佐藤さんを撮影する前からカメラを回すことはありました。地元の人から「お祭りを撮って欲しい」とか、「サッカーの試合を撮って欲しい」というお願いがあると、喜んで引き受けていました。あとは、まちを歩きながら風景を撮ったりしていましたが、自分から何かテーマを見つけて、作品のために撮るということはできなかったんです。はっきりした動機がないと、撮らせてくださいというお願いもできないですよね。何を撮りたいのかが定まるまでに7ヵ月かかった、ということです。
——撮影を始めるまでの7ヵ月間、なにを探していたのか。詳しく聞かせていただけませんか。
小森 その時期は復興計画の説明会が盛んにあって、会議に出たり、説明会に出たり、レポートを作ったりする記録の仕事を一生懸命やっていました。それが何になるのか分からないけれども、町で起こることの全部を記録しておきたい、そういう感じで関わっていました。
そこで街の人々と関わりができていく実感はあったし、私が映せない、かつてどのような町だったのかということ、どんな人がいて、どんな風があったのかという細部を少しずつ知るようになりました。そういう中で一人一人の生活をもっとそばで見ていたい、それを記録したいという気持ちが出てきたんです。
——地域に「記録者」として関わることに、自分なりの意味を感じていた、ということですか。
小森 当時はそんなに何かを作らなくてはいけない、という思いも無かったので、町の人たちと関われるだけで幸せでした。どの人も魅力的だったし、そういう人たちと出会えて生き方を見られるだけでも、私にとっては情報量の多すぎる毎日で、十分なことと思ったのですが、じゃあ、ここに何しにきたんだという焦りも同時にあって、自ら作ることを始めないと、ただ住んでいることだけで満たされてしまう。そう思って悩んでいた時に、佐藤真監督の映画『阿賀に生きる』(92)に出会ったんです。岩手にいながら著作を読んで、佐藤真さんが今もし生きていたら、会いたいなと思ったんですよ。
——地域によそ者が定住して撮影をする、という意味では同じですが、撮影スタイルは全く異なります。どうして、『阿賀に生きる』だったのでしょうか。
小森 本を手にしたのは、定住して撮影した人たちの映画があるということを知ったからでしたが、制作の方法を学ぶというよりも、佐藤真さんが阿賀の家に引っ越して、なにを撮ったらいいか分からなくて、阿賀野川沿いをずっと歩いていた話を、自分の状況と重ねていたのかもしれません。
佐藤真さんは、新潟水俣病が公表されてから随分時間が経ったころに阿賀にきて、人々も風景も美しいけど、今さらなにが撮れるのかを悩んでいたそうです。私も震災前を知らないくて、だけど写したいと思うのは震災前の町だったり、そこにあった暮らしだったりして。それは私には伝えられないし、映せない。今更何をしにきたんだ?と自問する中で、津波で流された後のまちをただ歩いて、風景を撮ることしかできなかった。佐藤さんが阿賀野川沿いをひたすら歩いていたという気持ちがわかるような気がしました。
——『阿賀に生きる』も、特に前半は何を撮れるのか、の模索のようすが、画面に現れている映画だと思いました。
小森 私はその模索の部分に救われたと思います。撮れずに悩んでいていいんだ、という。それで、『阿賀に生きる』のカメラマンの小林茂さんや呼びかけ人の旗野秀人さんに何度か会いにいって、お話しを聞いたりする中で、撮りたいものがみえてきたところがあったんです。
阿賀に行くと『阿賀に生きる』が現在も地元の方達にとって必要な映画としてあることに、あらためて驚きました。映画っていろんな土地を回って、世の中に共有するものとしてあるのかと思っていましたが、映画が作られた土地である阿賀では、現在も毎年上映会が開かれて、旗野さんや患者さんが『阿賀に生きる』を背負って今も生きている。そこに感動して、こういう未来が20年後にあるとしたら、私は映画を作りたいと思ったんです。 『息の跡』より©2016 KASAMA FILM+KOMORI HARUKA
『息の跡』より©2016 KASAMA FILM+KOMORI HARUKA
▼page2 佐藤さんを撮る、ということ


















