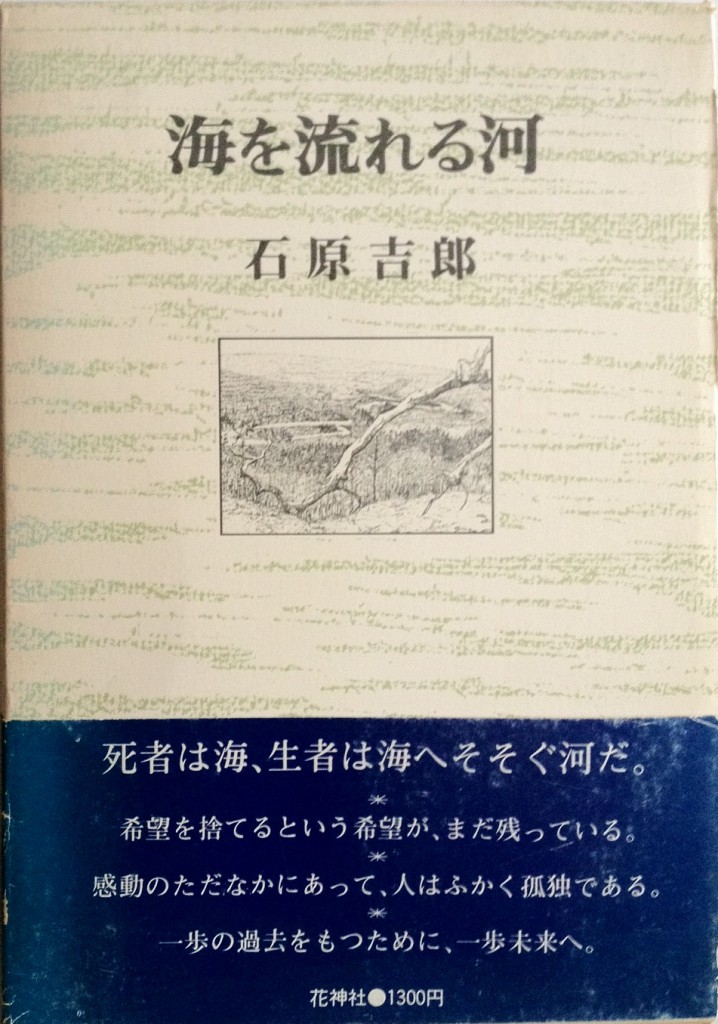「いつの頃からか私には、海を流れる河というイメージが定着し、根をおろしてしまった」(石原吉郎「海を流れる河」)
敗戦後、ハルビンから旧ソ連領へ移送され、その後8年あまりのあいだ収容所での日々を送った、詩人・石原吉郎。1949年に形式だけの裁判によって反ソ・スパイ行為による重労働25年の判決を受けた彼は、国際法に違反する「隠し戦犯」として抑留、強制労働への従事を強いられる。1953年、スターリン死去による特赦で帰国。その後、1963年に第一詩集『サンチョ・パンサの帰郷』(思潮社)を刊行、『日常への強制』(構造社、1970)、『水準原点』(山梨シルクセンター出版部、1972)など、多数の詩集、評論集を発表し、1977年に死去した。
評論集としては、石原の生涯に多大な影響を与えた友人・鹿野武一との収容所での交流から想起された「ペシミストの勇気について」をはじめ、シベリヤでの収容所体験に関する文章を集めた『望郷の海』(※1)が名高い。だが、ここでは1974年に刊行された『海を流れる河』(花神社)という評論集を取り上げたい。
書名にも採られた「海を流れる河」は、わずか5ページのエッセイであり、「海を流れる河」というイメージの基底に横たわる身体性を、詩的な描写で描き出す。
「海を流れる河」という主題につづき、読者はまず、「河」という名の詩を目にする。「河口」、「河の終わり」であり、同時に海のはじまりであるところを知覚した河は、その閾をのりこえ、あふれだす。海にまぎれることなく、河はその流れを維持し、海を進む。その流れは「海よりもさらにゆるやか」なものだった。海へまぎれず、「ふたすじの意志で」、「岸をかぎ」ったその河を、歴史の海にひとり立ちつづける河、と読むこともできる。広大な歴史の海にまぎれず、「ゆたかな河床」を生みつづける、わたしという流れ、あるいはわたしの物語。このとき海は、囲い込むことのできない無数の河の流れによって、内腹を貫かれている。
1940年夏(※2)、朝鮮半島を経由しハルビンへ渡った石原にとって、海は「無辺際の広さ」としてあこがれ慕うものだった。(それは後に、再び海を渡る石原に失望を抱かせ、「海さえも失った」と思わせるものとなる)。そして1948年、シベリヤ抑留中の石原は、「海を流れる河」というイメージの源泉となる河と出会う。
「東シベリヤの密林のただなかで、そのとき私が見た河は、かならずしも流れるようにして流れてはいなかった」
一所に在ることを強いられ、自らの生の行く末すら、ただ見送るしかない石原は、目の前を流れる河が、北上し北氷洋へ至ることを知りながら、「そのように河を見ることに私は耐えなかった」と述懐する。そして河の上流に過去、下流に未来、目の前の流れの幅に現在を見る。過去現在未来、目の前で絶えず生まれかわる「河」もまた、石原にとって見送るものである。つねに「死」が隣接する状況下に在る石原は「永遠の継続」、「永遠の未完了」を「河」に託す。そのとき「河」は、「目指すところへ」至ってはならない。海へまぎれず、さらに北へ向かわなければならない。
東シベリヤに在り、「母国」を目指す南への指向と同等に、石原は北への指向を抱く。「河は海へまぎれずに流れつづけることが自然」であると考えた石原にとって、北を目指すこともまた「自然」だった。それは「母国を遠のこうとする志向」であり、そこに現れた「ある種の予感」については「望郷と海」(『望郷と海』収)に詳しい。
それは「望郷」から「怨郷」、そして「忘郷」へ至る道すじである。
ここで石原が言う「望郷」とは、敗戦により崩壊した「きのうまでの日本」が石原を希求し、石原自身もまたそれを希求する、その結びつきのことである。たとえそれが、「望郷が招く錯誤のみなもと」だったとしても、当時の石原にとって、それは縋りつかねばならない一条の観念だった。移動の自由を奪われた身に起こる「望郷」は、「植物の感情」であり、自らの意志で地を這うこともできぬ、「海をわたることのない想念」だった。「私が陸へ近づきえぬとき、陸が、私に近づかなければならないはずであった」と心中で叫ぶ、その思慕が錯誤であることを知りながら、「それが、棄民されたものへの責任である」と強く言い放つとき、それを信じなければならなかった石原の状況を示唆する。
そして重労働25年の判決を受けた後に、「故国とその新しい体制とその国民」に忘れ去られることへの恐怖が、石原を襲う。刑務所のなかで、「おれがここで死んだら、おれが死んだ地点を、はっきりと地図に書きしるしてくれ」と叫ぶ石原が拠りどころとするのは、すでに崩壊した体制である。新しい体制に捨て去られる、という性急な断定を、石原は状況の急迫における「錯誤」と認めたうえで、なおそこに「確固としたリアリティ」、「具体的な恐怖」を感じた。結びつきを希求する旧体制の「故国」による義務の放棄、新体制による忘却、この二重の棄却によって、石原に「怨郷」の想いが起こる。「もし忘れ去るなら、かならず思い出させてやる」。
その後、重労働25年の刑地として送られた東シベリヤの密林において、「ついに忘れられた」という想念に駆られた石原は、自身もまた「故国」を忘却していく。「多くの囚人にたちまじる日本人を、〈同胞〉として見る目を私は失いつつあった」。自我にかかわりなく生きる樹木の群れを羨望し、「望郷の想いはおのずと脱落した」。
「海を流れる河」へ立ち返ろう。
「故国」に背し、北を指向する河に、「終焉があってはならない」。
強制労働生活において、肉体労働の疲労のなかにいることだけが、安堵のなかにうずくまっていられることだった。重労働への従事を強いられるなかで夢想した「安堵のような死」が、石原に幻視を促す。河が注ぐのであれば、それは北氷洋のさきの「ひろごり」でなければならない。それは「巨きな安堵の海」、「死者の海」である。
しかし、目の前を流れる河に終焉はない。河は流れつづけなければならない。そこで石原は、「死」や「疲労」といったわれを失う安らぎに換え、「衰弱」ということばを持ち出す。「衰弱」は「終焉」に至らない持続であり、つねにその身を意識し、その身に刻まれつづける。「いま病む者は、その病いを終ることなく病まねばならぬ」。東シベリヤの密林に在る石原において、安らぎを志向する存在の放棄よりも、未完了に流れつづけること、衰弱しつづけること、そこにひとつのリアリティ、論理があった。
歴史という広大な流れに翻弄されながら、われを見失わず「海よりもゆるやかに」流れる、ひとつの河。無数の河。石原は、恣意的な区切りによって捻出される歴史に抗うひとつの可能性として、海にまぎれず流れつづける河や、衰弱しつづけるからだの、その遅々とした強度を現出させた。
(※1)『望郷と海』(筑摩書房、1972)、その後『望郷と海』(ちくま学芸文庫、1997)、最近刊として『望郷と海』(みすず書房、2012)がある。
(※2)「自編年譜」では、「1941年」となっている。
【書誌情報】
『海を流れる河』
花神社 1974年 絶版
(2000年同時代社より復刊も、版元品切れ中)
【著者紹介】
石原吉郎 いしはら・よしろう
詩人。1915年、静岡県伊豆土肥村に生まれる。1938年東京外語ドイツ語貿易科卒業。大阪ガス入社。翌39年応召、41年、関東軍のハルビン特務機関へ配属。敗戦後、シベリア各地の収容所を転々とする。49年2月には、反ソ・スパイ行為の罪で重労働25年の判決を受ける。スターリン死去にともなう特赦で1953年12月に帰国。翌54年に『文章倶楽部』に詩の投稿をはじめ、翌年には詩誌『ロシナンテ』を創刊、続々と詩を発表する。詩集に『サンチョ・パンサの帰郷』(1963、思潮社、第14回H氏賞)『水準原点』『禮節』『北條』『足利』『満月をしも』、詩・評論集に『日常への強制』、歌集『北鎌倉』、句集『石原吉郎句集』、エッセイ・評論集に『望郷と海』(筑摩書房、1972、《始まりの本》みすず書房、2012)の『海を流れる河』『断念の海から』『対談集 海への思想』『一期一会の海』など。1977年11月14日、自宅で入浴中に急性心不全のため死去。
【執筆者プロフィール】
中里勇太 なかさと・ゆうた
1981年宮城県生まれ。編集業・文筆業。『KAWADE道の手帖 深沢七郎』(河出書房新社)に作品解説を寄稿。他に評論「死後・1948」(文藝別冊「太宰治」)、「応答としての犯罪的想像力」(文藝別冊「寺山修司」)、「わたしたちは想像する」(祝祭4号)など。Zine「砂漠」クルー。昨年は岩淵弘樹監督『サンタクロースをつかまえて』のパンフレット編集(製作:砂場)もつとめた。
【関連記事】
記録文学論 【①】【②】【③】【④】【⑤】【⑥】